- ニュース
- 【開催報告】2022年度第2回スタディセミナーが開催されました
【開催報告】2022年度第2回スタディセミナーが開催されました

- Posted
- Mon, 18 Jul 2022
スタディセミナー「フランスにおける医療情報の利用と保護について―デジタル・ツールの出現と「私生活を尊重される権利」」
主 催: 早稲田大学比較法研究所
日 時: 2022年7月7日(木) 16:30~18:00
場 所: オンラインによる開催
講 師: 塚林 美弥子 早稲田大学社会科学総合学術院・講師(任期付)
参加者: 63名(うち学生19名)
2022年7月7日、第2回比研スタディセミナーが開催されました。報告者は早稲田大学社会科学総合学術院講師(任期付)の塚林美弥子先生であり、報告タイトルは、「フランスにおける医療情報の利用と保護について-デジタル・ツールの出現と「私生活を尊重される権利」」でした。司会は、比較法研究所幹事の大橋麻也先生が務め、塚林先生の報告の後、質疑応答がなされました。
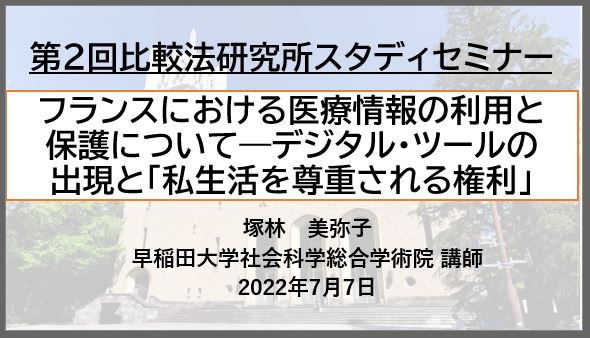
塚林先生は、今回のセミナーにおいて、フランスの医療情報共有システム・DMPの概観、DMPが提起した憲法上の問題、医療情報と私生活尊重権の保護、この3つの内容に分けて報告されました。
塚林先生は、まずDMPの定義や導入の背景を紹介しました。つまり、DMPとは「治療の予防、連携、質、および継続性を向上させる目的」を持つ情報化された医療文章であり、DMPシステムは、医療従事者、治療や予防に携わる施設間による医療・診療情報の効率的な管理・共有することで、患者の権利保障・治療の効率化・医療費の削減の実現に資する制度です。DMPシステムはフランスにおいて2004年に導入決定され、2005年に実験的運用が開始されました。
塚林先生は、DMPシステムの具体的中身である登録情報や共有範囲などを検討した後、DMPシステムにある法的な権利および導入時の争点について検討されました。
塚林先生は、秘匿性の尊重等がDMP実施の最低限の条件としつつ、具体的には、マスキングの権利、情報の取り扱いについて事前に知らされる権利、異議申立ての権利があると紹介し、さらに、DMPシステムの導入が「私生活尊重権」の侵害であるか否かについて、検討されました。
司法裁判所および欧州人権裁判所による判例の蓄積から、私生活尊重権は人権宣言第2条に基づく独立した憲法的価値を有するものとされる背景の中、憲法院は、2004年8月12の判決において、人権宣言第2条が私生活の尊重権を含むことを再確認したうえ、DMPを憲法適合的と判示しました。本判決においては、憲法的価値の「私生活尊重権」が確定されると同時に、他の憲法的価値(公衆衛生保護など)とのバランスが考慮され、当該権利が不当に制約されているとは結論されなかったのです。
最後に、塚林先生は、DMP変遷の議論を検討し、医療(健康)情報は、「無限の広がり」、「流動的」な性格があり、新たなデータツールや医療装置の発展などにより争点が生じると考え、「私生活尊重権」と「医療情報保護」の関係性やDMP今後の発展を検討されました。
報告後の質疑応答では、医療従事者の意見が異なる場合のDMPの実際運用上の処理の仕方、DMPのようなシステムの日本への導入可能性、異議申立ての権利の対象、DMPの行政監督機関、私生活尊重権と個人情報保護法情報上の自己情報コントロール権の関係性、医療従事者の守秘義務という大前提の下でのデータ保護、医療情報の範囲における情報の重要度による区別的対応の有無などが検討されました。
(文:魯潔・早稲田大学比較法研究所助手)
参考
開催案内

