- ニュース
- 【開催報告】公開講演会「ラテン・アメリカの立憲主義:普遍性と特殊性のはざまで」(セザール・ランダ氏 ペルー・カトリカ大学 教授)が開催されました。
【開催報告】公開講演会「ラテン・アメリカの立憲主義:普遍性と特殊性のはざまで」(セザール・ランダ氏 ペルー・カトリカ大学 教授)が開催されました。
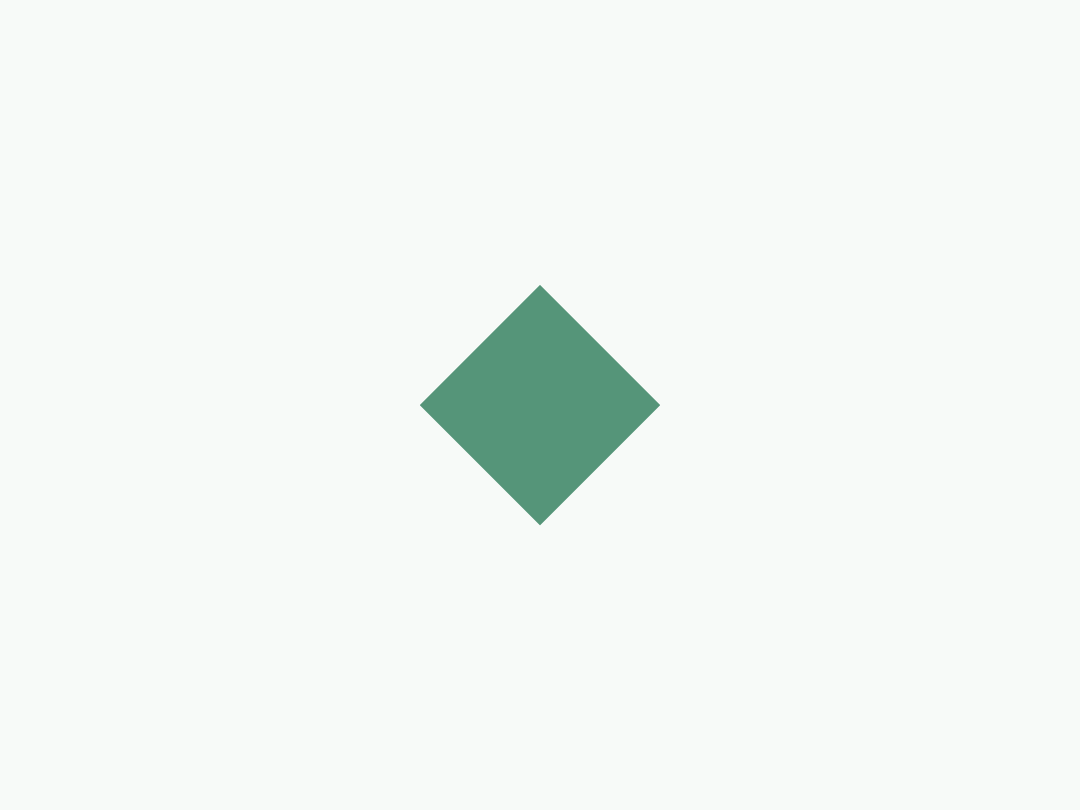
- Posted
- Wed, 19 Jul 2017
公開講演会概要
2017.7.18
日時 2017年7月18日(火)13時00分~14時45分
場所 8号館3階大会議室
講師 セザール・ランダ教授(ペルー・カトリカ大学法学部)
司会 中村民雄
演題「ラテン・アメリカの立憲主義―普遍性と特殊性のはざまで」
対象 教職員7名・院生・学生8名
言語 英語
講演概要
南米諸国の多くは、1980年代以降の新しい憲法をもち、また21世紀に入っても憲法改正が相次いでいる。アルゼンチン(1994年制定)、ボリビア(2009年制定)ブラジル(1988年制定)、チリ(1981年制定)、コロンビア(1991年制定)エクアドル(2008年制定)、ペルー(1993年制定)、パラグアイ(1992年制定)、ベネズエラ(1999年制定)などである。これは独裁政権や軍事政権を脱却して立憲民主国をめざす選択をしたこと、そして北米経済に従属した経済体制のもとで各国の経済成長にもかかわらず一定層にのみ富が集中し、国内での所得の再分配が十分になされないため、国際経済のあり方に批判的な政権が誕生したりしたことを反映している。
今回の講演会では、こうしたラテン・アメリカ諸国の比較的新しい立憲主義の特徴と抱える課題を、ペルー憲法裁判所の元長官であり、ペルーのカトリカ大学の憲法学教授ランダ先生に語っていただいた。講演では、憲法裁判所は、立法部と行政部の法的仲裁役であり、また国民と国との憲法異議の訴えを取り持つ意味での仲介役であるとの位置づけがなされた。とくに憲法裁判所の制度のもとで、憲法上の基本的利益の保護(amparo)を求める個人から政府等に対する憲法異議の訴えにもとづき、法律で保護された利益の保障という段階から、憲法上の基本的権利の保護(次々に改正され変転する法律では必ずしも安定して保護されない利益となるが、憲法上の権利保障であればこの変転を超越できる)の段階へと展開していると位置づけうることが一般論として紹介された。しかし同時に南米の国ごとにこのamparoの実践は異なっていることも紹介された。最後に、南米諸国に共通の米州人権委員会・裁判所の制度が紹介され、とくに米州人権裁判所の判決で加盟各国の立法が米州人権条約違反とされる例、そしてそうした判決を受入れる加盟国、受入れない加盟国など様々の反応があることも紹介された。
質疑では、ペルーがケルゼンの構想したような形式の憲法裁判所の形態をとった経緯は何か。各国の憲法裁判所が保護すべき基本権として考える範囲と、米州人権裁判所が考えるそれとはずれる可能性があるが、それをどう調整するのか。amparoの訴えの過程で、異なる憲法上の権利同士が衝突するとき、ペルーの憲法裁判所はどう解決するのか。ヨーロッパ諸国の法概念や法制度を南米諸国はよく導入するが、母法とは内容が相当に異なったり、時には同じ言葉で別物を語っていたりすることはないのか。こうした質問が次々と出され、講師による応答がなされた。 (文責:中村民雄)
- Tags
- イベント


