- ニュース
- 【開催報告】シンポジウム「Brexitとイギリス政治・憲法―不文憲法国の憲法準則と政治実務のズレをめぐって―」を開催しました
【開催報告】シンポジウム「Brexitとイギリス政治・憲法―不文憲法国の憲法準則と政治実務のズレをめぐって―」を開催しました
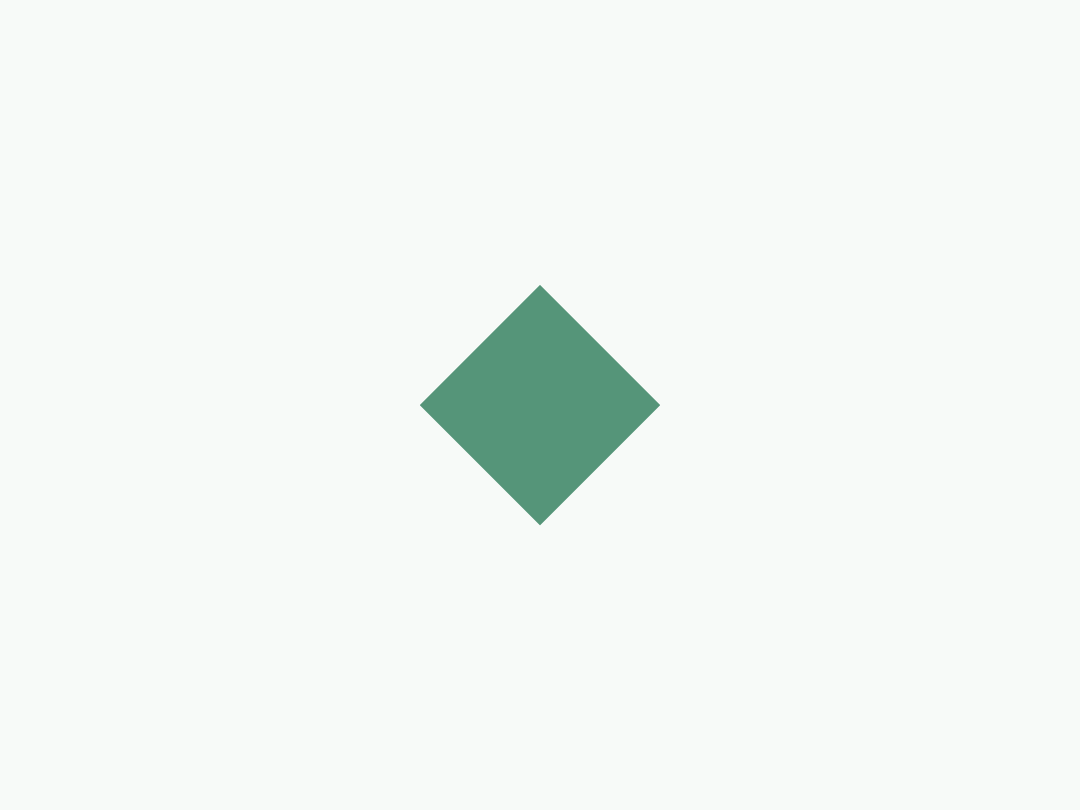
- Posted
- Wed, 01 Feb 2017
イギリス最高裁判所研究会主催 比較法研究所共催
シンポジウム 「Brexitとイギリス政治・憲法―不文憲法国の憲法準則と政治実務のズレをめぐって―」
2017年1月28日(土)午後3時から5時半
26号館 地下多目的講義室 (会場参加者 45名)
司会 中村英俊(早稲田大学准教授)
報告1 中村民雄(早稲田大学教授) ― 討論1 倉持孝司(南山大学教授)
報告2 若松邦弘(東京外国大学教授)― 討論2 小川有美(立教大学教授)
成果の概要
このシンポジウムでは、2016年の国民投票以降、EU脱退(Brexit)の道を進み始めたイギリスでの訴訟を中心に、法学と政治学の視点から報告と議論がなされた。
まず中村民雄は、Brexit訴訟の経緯を紹介した。(国民投票後、政府は脱退通知を政府一存でできると考えていた。市民がこれを違法と確認するよう求める訴訟を提起した。2016年11月3日の高等法院判決も、2017年1月24日の最高裁判決も、政府一存ではできず国会の立法を事前に要すると判断した。判決に対して脱退派の新聞・市民・政治家が過激に反発し、とくに高等法院判決に対しては一部メディアが判事らを「人民の敵Enemies of the People」と非難するほどだった。)そのうえで、中村は最高裁判決について、理由づけと結論は妥当だとしつつも、逆にそれゆえに、法と政治の乖離が目立ち、代表民主主義のみ考える「国会主権の原則」は直接民主主義の国民投票の正統性を十分に位置づけられておらず、今回の判決でもこの点は何ら考察がなされなかったと指摘した。そこで理論的にはこの際、「国民主権」へと転換することも考えうるが、イギリスの政治風土ではまだそういった根本的な変更論はでそうにない、と報告した。
この報告に対して倉持孝司は、あえて反対の見地からいくつか質問をし、中村報告の明確化を求めた。たとえば、本件はBrexit政治に影響を与えうる政治的事案であるのに法的問題だけを判断したことが妥当だったのかと問うた。また、法的に裁くにせよ、脱退通知は手続開始の通知にすぎず、撤回も可能かもしれず、結論が見えているわけではないから、外交大権により政府が一存で通知できるとする主張のほうが適切なのではないか、などを問うた。これに対して中村から応答がなされた。
次に政治学の見地から、若松邦弘は、今回のBrexit判決は結局脱退に向けた政治の「手続」に対する異論であったが、国会議員の三分の二は投票前、EU残留派だったから、脱退通知の前に国会の立法を要するという手続になれば、国会で脱退の結論が逆転する可能性があり、脱退派も僅差の多数であって基盤の脆弱さを感じていた。だから通知前の手続を問う訴訟に対して脱退派の国民や多くの議員から激しい攻撃がなされたと論じた。
小川有美は、視点をヨーロッパに移し、ヨーロッパ諸国で国民投票がどのように政治的に用いられてきたかを概観し、スウェーデンでは国民投票の結果とは逆の決定を国会がした例もあることや、大きな傾向的特徴としては、政権党が勝てる見込みがあるときに国民投票をするといえるが、近時は政権党の政策が逆に国民投票で否決される例が重なっていることも指摘し、この現象をどう分析するかの視点をいくつか紹介しつつも、結論としては、イギリスだけでなくヨーロッパ諸国をふくめ、国民投票をどう政治と法の中に位置づけるかはまだ論議が足りないと論じた。
その後、司会者は会場からの質問を求め、活発な質疑応答が行われた。たとえば、アメリカでのトランプ政権の誕生とBrexitは何らかの結びつきがあるか、日本での憲法改正では国民投票が要件だが、Brexitやヨーロッパの国民投票からの教訓はあるのか、Brexit判決後、スコットランドはどういう立場をとるだろうか、Brexit判決の最高裁が国会や政府に対して司法権を強めようとしているのではないか、イギリス最高裁の裁判官の任命過程は民主的に統制されているのか、といったさまざまの質問がよせられ、盛会となり、時間も30分延長して終了した。
(文責:中村民雄)
参考
開催概要
- Tags
- イベント






