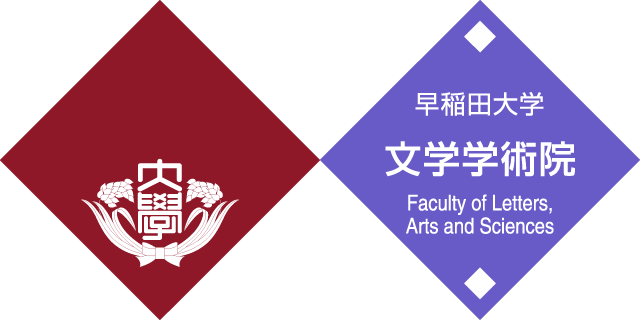- 学生報告書
- 御手洗靖大 文学研究科 日本語日本文学コース
御手洗靖大 文学研究科 日本語日本文学コース
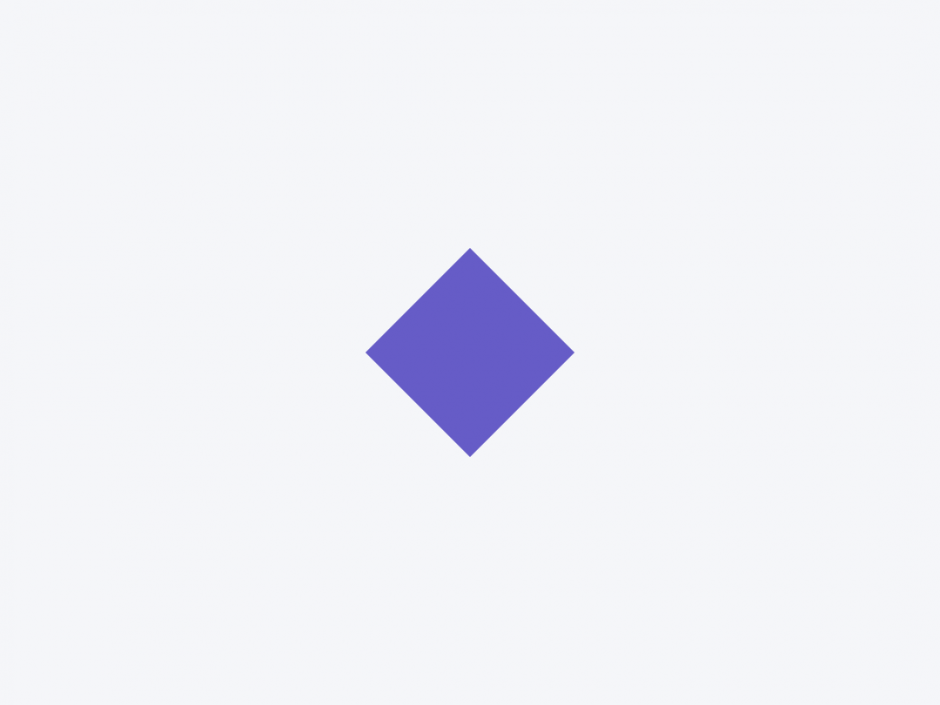
- Posted
- Tue, 19 Dec 2023
ブリティッシュコロンビア大学ワークショップ参加報告
早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程 御手洗靖大
2023年11月23日の夜に羽田空港を発ち、バンクーバー空港に到着したのは同日14時ごろ。陣野英則先生と草野勝氏と私は、迎えに来てくださったクリスティーナラフィン先生と共にブリティッシュコロンビア大学(The University of British Columbia、以下 UBC)へ向かった。UBC 所蔵の飛鳥井雅章自筆本『吉野記』を基軸に、UBC アジア学科(Department of Asian Studies)と早稲田大学の大学院生が自身の研究と該書を絡めて研究発表をするワークショップに参加するためである。
今回の旅程は現地時間で11月23日から25日間の3日。UBCの院生との交流や、UBCのキャンパスツアーを挟みつつ、『吉野記』の調査と発表を行う。
初日は初めての時差ぼけに感激しつつ、すでに晩秋から冬の景色となったUBCをご案内頂いた。キャンパス内は広大で自然も豊か。リスもいる。日が暮れてからUBCの院生と初顔合わせのディナーである。
おのおのの研究を話しつつ、時々まざる早口の英語をなんとか聞き取りながら楽しく過ごした。UBCのいわゆる博士後期課程の院生は、講師として授業を持っている。ここで大学での教歴を積むのだそう。院生の、人文系研究者してのキャリアをいかに構築していくかということをここは組織で考えている。そんな現実の話もしつつ、一日目を終えた。
二日目は、『吉野記』の実見調査をさせて頂いた。三井本家の一つであり男爵に叙されてもいる南家伝来の本は、豪華本とよぶにふさわしい美しい装飾料紙である。ただし、列帖装ではあるが、表紙もなければ綴じられてもいない。
自筆とされる本文の和歌は、五七、五七、七の三行で記され、折詠草の書き様である。そして、全ての和歌が下句の始まりで墨継ぎがなされており、意識的な書写がうかがえる。
その後、大阪万博のパビリオンを移築したアジアセンターで『吉野記』にちなんだ研究発表を行った。報告者は、平安和歌専攻という立場から、吉野という歌枕を確認しつつ、吉野という歌枕にとらわれない該書の和歌を取り上げた。蔵王堂まできた雅章は、名所の四本桜(四隅に桜が植わっている)をみて、飛鳥井家の家職である蹴鞠の場を思い描いて歌を詠む。和歌の伝統にのっとらない歌が詠めるのは、雅章がその地に立ったことを意味する。観察をもとに歌を詠むのは、一般的にイメージされる前近代の和歌とは異なる。ここにいわゆる「古典和歌」が志向しない個性をみいだして良いかもしれないと考えた。
その後はアジアセンターの裏の新渡戸稲造を記念した日本庭園の散策。北米の背の高い杉の木に囲まれた苔の庭は独特の居心地よさがある。ちょうど、講演に来られていたサーロー節子氏ともすれ違った。この場所ですれ違うことに何か特別な縁を感じたのは私だけではないだろう。
三日目はクリスティーナラフィン先生のアレンジメントでフライトまでバンクーバーをめぐった。SDGsへの配慮、LGBTQ+フレンドリーな町、カナダの様々な常識を教わりながら、社会との繋がる人文学者であり続けることの必要性は、なにも日本だけではないことを思い知った。
一度も雨の降らなかったバンクーバーの青空に、どんどん外に出て行く勇気をもらった。