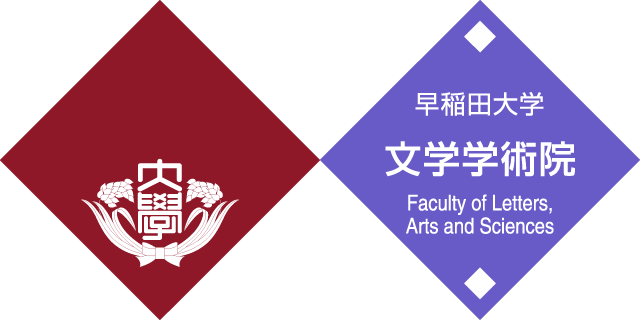- 学生報告書
- 安陪岳 文学研究科 日本語日本文学コース
安陪岳 文学研究科 日本語日本文学コース
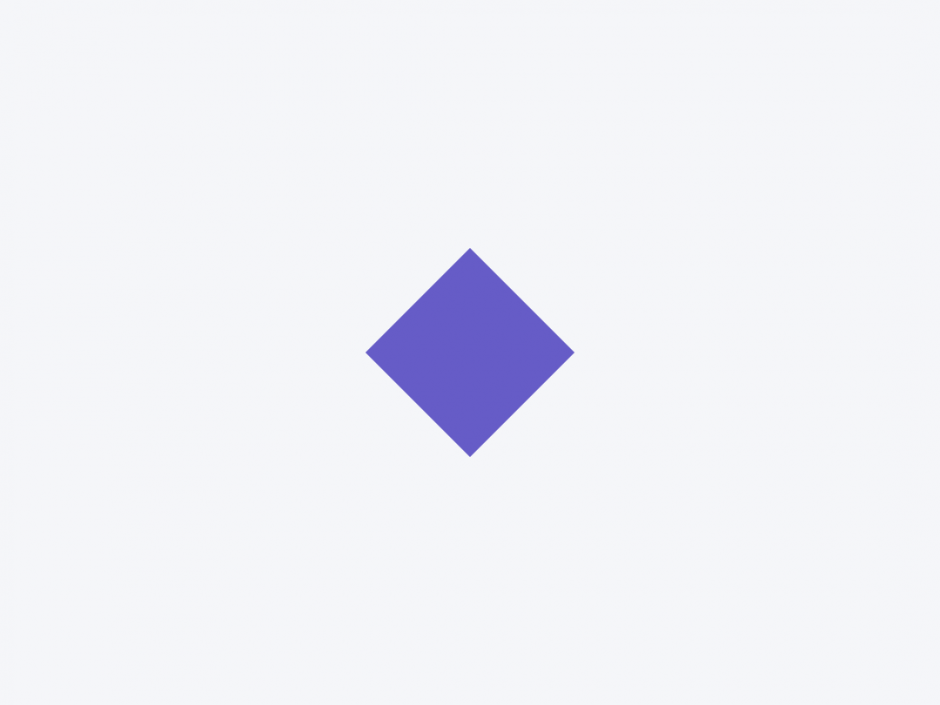
- Posted
- Wed, 20 Sep 2023
スタンフォード大学ワークショップ参加報告
文学研究科日本語日本文学コース 博士後期課程2年 安陪岳
私はこのたび、8月24日から25日の2日間にわたってスタンフォード大学で開催された、国際ワークショップに参加する機会を得た。テーマは「教室の中の国際日本研究―いかに教えるか―(Workshop on International Japanese Studies in the Classroom)」である。海外でのワークショップ参加を検討している方を念頭に、今回の経験に関して率直な感想を述べたいと思う。
旅程は8月23日の昼過ぎに、派遣メンバーである陣野英則先生、光井理人さんと羽田空港に集合することから始まった。約10時間のフライトでサンフランシスコ国際空港に23日の昼前に到着する。今回のワークショップのホストであるIndra Levy先生が空港まで迎えに来てくださり、先生のお車で宿泊先のゲストハウスに向かった。その日は翌日のワークショップに備えてゆっくり休んだ。一番の気がかりは時差ぼけだったが、幸い私はほとんど悩まされることなく翌24日を迎えることができた。時差ぼけ対策として2、3日前から早寝早起きを心がけ、フライト中は現地時間を意識して睡眠を取ったことが、結果的に有効だったと思う。
 ワークショップの会場はスタンフォード大学内のCenter for East Asian Studiesが入っている建物内の会議室で、24日の午後からスタートした。Session1 はBritish Columbia大学のChristina Yi先生、Bard CollegeのNathan Shockey先生、スタンフォード院生のLin Walshさんの3人が発表した。北米の大学で日本文学を教える際の授業の作り方がテーマだったが、彼らの話す高速の英語に付いていくのが精一杯だったのが正直なところである。
ワークショップの会場はスタンフォード大学内のCenter for East Asian Studiesが入っている建物内の会議室で、24日の午後からスタートした。Session1 はBritish Columbia大学のChristina Yi先生、Bard CollegeのNathan Shockey先生、スタンフォード院生のLin Walshさんの3人が発表した。北米の大学で日本文学を教える際の授業の作り方がテーマだったが、彼らの話す高速の英語に付いていくのが精一杯だったのが正直なところである。
休憩を挟んだのち、Session2ではスタンフォードの院生で日本からリモート参加のJason Beckmanさん、光井さん、私の3人が翻訳を使った日本文学の授業をテーマに発表した。私自身は高校1年生の新科目「言語文化」を念頭に、『伊勢物語』の英訳を使った授業の可能性について発表した。発表は英語を織り交ぜつつ日本語で行ったが、参加者の多くが日本語を母語とする話者ではないことを意識し、声の大きさやスピード、語彙などに気を付けた。ディスカッションでの受け答えは何とか切り抜けた感じだったが、最後にLevy先生から「ぜひこのような授業をしてほしい」という言葉を頂いたのが嬉しく、印象に残っている。
25日(ワークショップ2日目)は、Levy先生、スタンフォードのAriel Stilerman先生、Calgary大学のBenjamin Whaley先生の3人が情報技術をテーマに発表した。大学レベルの宿題すら高精度に答えてしまうChatGPTに対する危機感は参加者に共通のものだった。一方で教育用のアプリが教育格差の是正に貢献する事例など、「どう使うか」を問うことが重要であると感じた。この後、大学の図書館内に併設されたDavid Rumsey Map Centerを見学するツアーがあった。ここは資産家のDavid Rumsey氏が収集した世界中の地図を保管し、デジタル化している場所である。直感的に地図を操作できる巨大なタッチパネルなどがあり、体験型の施設としても楽しい。これらのデジタル化資料はネットで無料公開されているので興味がある方は見てほしい。
ワークショップの最後は陣野先生、スタンフォードに滞在中の田中ゆかり先生、十重田裕一先生の3人が日本で研究職を得るために必要な方法や考え方について発表した。あくまでも北米の院生向けの内容だったが、日本の大学に所属し研究する自分自身の状況と照らし合わせ、相対化できたのは有益だった。ワークショップ終了後は、僕と光井さんにスタンフォードの院生の方2人を合わせた4人で、大学の近くにある町のレストランで夕食を共にした。緊張が解け、同世代の方と遠慮なく話せたこの時間は一番楽しかった。
以上、簡単な報告をしてきたが書けなかったことも沢山ある。例えば会食は上記の他に参加者の方とのランチが2回、ディナーが1回あった。こうした機会に得られた交流や情報が大きかったことは言うまでもない。言語について触れておくと、やはり英語ができるに越したことはないと感じた。特にディスカッションや食事の席では自分の英語の能力をもどかしく思った。私自身は今回の参加が決まってからの数か月、できる範囲で英語の学習をしてきた。その成果は確実にあったが、この経験を糧に研鑽を積みたいと思う。最後に一緒に参加した陣野先生、光井さん、そしてスタンフォード大学のLevy先生、そして院生の方々に感謝したい。特に現地の院生の方々と交流できたことは今回の最大の収穫だったと思う。今回の派遣で得たつながりを他の研究者にも広げていくことが今後の自分の役割だと感じている。