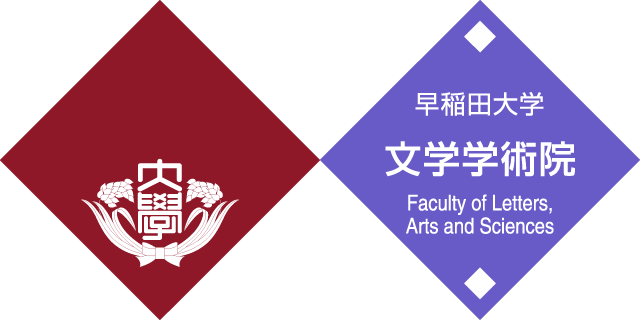- 学生報告書
- 西村こと 文学研究科 日本語日本文学コース
西村こと 文学研究科 日本語日本文学コース
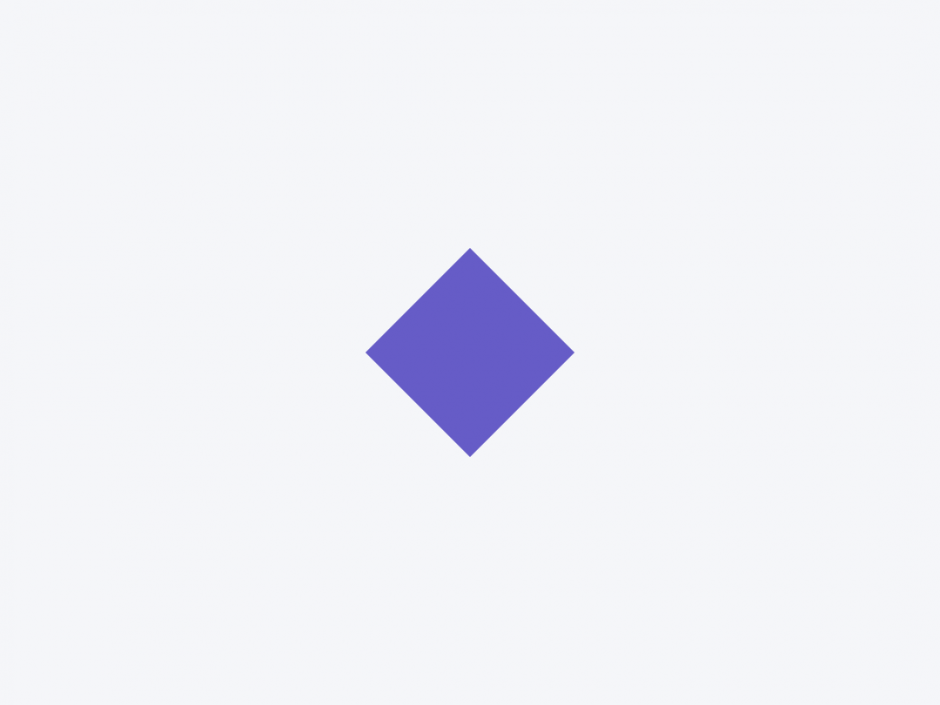
- Posted
- Thu, 01 Jun 2023
UCLAシンポジウム参加報告
文学研究科日本語日本文学コース修士二年 西村こと
UCLA-早稲田 国際シンポジウム(2023年4月28日~30日)に参加した。私にとってはアメリカ合衆国に行くのも、大規模な国際シンポジウムに出席するのも初めての経験であったため、緊張と期待が入り混じった気持ちで当日を迎えた。
ロサンゼルス国際空港で柳井イニシアチブ関係者の方ならびに登壇者の方々と合流しUCLAのキャンパスにバスで向かった。夜の到着ということもあり車窓を流れる風景は暗かったが、浮かんでは消えていく大きなヤシの木のシルエットからカルフォルニアらしさを仄かに感じた。
本シンポジウムは“Kyarachters On the Other Side of Narrative”と題され、様々な「キャラクター」を巡る問題が提示され議論された、刺激的なシンポジウムとなった。
第一日目はキャラクターに付された「役割語」のご研究で知られる金水敏先生、そして谷崎潤一郎と映画の関わりの研究で知られるThomas Lamarre先生によるご発表など多様な角度からのキャラクター概論が展開された。自明のものとして享受してきた、フィクションにおけるキャラクターという存在について考えさせられた。大河ドラマに長年携われていた大森洋平さんと吉川邦夫さんの、これまでに大河で演じられてきた「徳川家康像」の違いについてなど制作側の方々のお話を拝聴したのも得難い機会であった。
続く二日目では、日本古典文学/演劇(午前)と近現代文学(午後)に見られるキャラクターについて論じられた。近代文学は自身の専門でもあるので、殊に心待ちにしていた。アンヌ・バヤール=サカイ先生による夏目漱石『坊っちゃん』の分析、東日本大震災を取り扱った小説について等の御発表があり、それぞれから大きな刺激を受けた。私は谷崎潤一郎の作品を現在研究しているので、なかでもKristin Sivakさんの日本近代文学におけるServantsの表象と機能についての研究発表に関心をもった。大岡昇平『野火』を導入に、夏目漱石『吾輩は猫である』、谷崎潤一郎『細雪』、三島由紀夫『仮面の告白』をシームレスに繋いでゆく論の組み立て方を斬新に感じた。またServantsという英単語から日本人の私が喚起する、洋風な一軒家で清潔な白い前掛けを着け粛々と主人のために立ち働く人というイメージと、Sivakさんの用いている Servantsの意味をすり合わせてみたくなった。続く質疑応答では「書かれた時代や時代コンテクストが違う三作品を、どのような意図でとりあわせたのか」そして「「書生」、「女中」など近代日本における家庭内使用人に対する呼び分けをどう考えるか。Servantの定義とはなにか」を英語で質問する幸運に恵まれ、有益な応答を発表者の方から頂くことが出来た。シンポジウムで質疑応答を経験したことは今回の収穫のひとつである。

シンポジウムでの質疑応答の様子
一日のプログラムが終わった後、十重田先生、山本先生、そして登壇者の方々と賑やかなディナーがもたれた。そこでみなさまが温かく接して下さったことには感謝の言葉を言いつくせない。忘れがたい時間となった。
三日目は日本語学とサブカルチャー研究の観点からの発表が続いた。田中ゆかり先生の方言とそのキャラクター性についてのご研究と、Jポップ、ゲームやアニメを対象とした御発表など新しく知る事ばかりの目まぐるしい一日となった。キャラクターとステレオタイプ的発想の近しさについて思いを馳せた最終日であった。
いま振り返れば二日目のシンポジウムで私が疑問に思った点には、考えるべきところが含まれていたと思う。「日本人」である私にとっては明治時代に書かれた作品と昭和に書かれた作品は、考えるまでもなく全く違ったものとしてカテゴライズされてしまっている。両者をhorizontalに並べる発想は頭に浮かべてみたこともなかった。また当然のように「書生」や「女中」は別物だと受け取っていたが、それにServantsという新たな共通する位置を与えることで、別の見方が生まれてくるかもしれない。日本語母語話者である以上、言わず語らずの肌感覚で納得できることが多いからこそ、作品の読みが曖昧なまま限定されてはいなかっただろうかと内省させられた。
短い期間での滞在だったので十六時間の時差になかなか慣れることが出来ず、毎日早朝に広大で人気のないキャンパスを散歩していた。上着のないTシャツ姿では朝まだきは肌寒いくらいであり、滞在最終日には冷たい雨さえ降った。UCLAの学生の方々によれば、春のアメリカ西海岸には珍しい異常気象がつづいていたようであった。気候ですら私が勝手に築き上げていた「あたたかくて陽気なカルフォルニア」というイメージを裏切る。研究においては自分自身が、自分の中にあるパラダイムを意識しそれを適切に解体していかなければならないだろう。
最後に、本シンポジウムの登壇者の方々、そしてUCLAの学生の方々、そして関係者の方々が温かく受け入れて下さり、気さくに接してくださったことに心からの感謝を述べたい。またUCLAに伺い、再会することの出来る機会を待ち望んでいる。その暁にはようやく「典型(ステレオタイプ)的なカルフォルニア」を体験できるかもしれない。