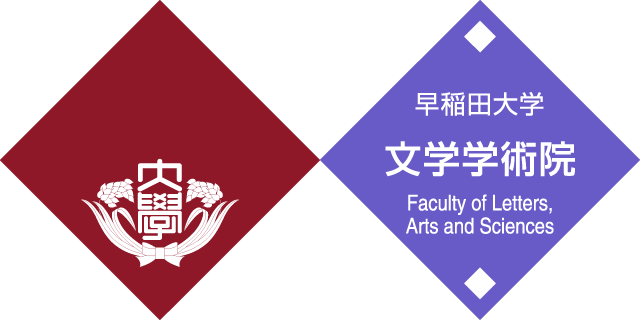- 学生報告書
- 甲斐温子 文学研究科 日本語日本文学コース
甲斐温子 文学研究科 日本語日本文学コース
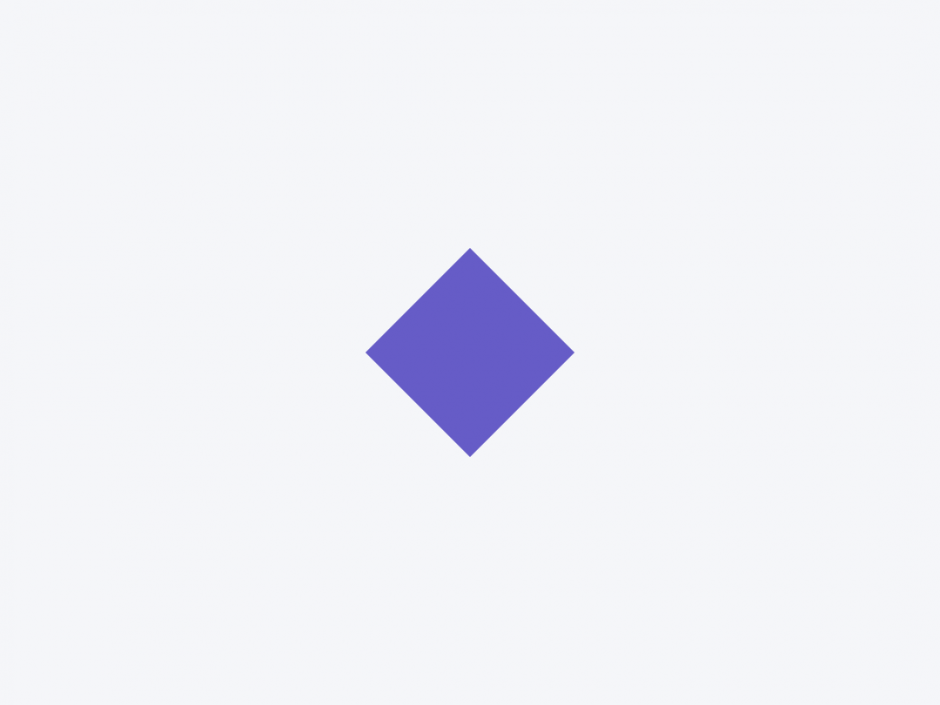
- Posted
- Tue, 28 Mar 2023
ブリティッシュコロンビア大学ワークショップ参加報告
文学研究科博士後期課程 甲斐温子
2023年3月6日から9日にかけて、ブリティッシュコロンビア大学(The University of British Columbia、以下UBC)において開催されたワークショップに参加した。本プログラムは、UBC所蔵の飛鳥井雅章自筆本「吉野記」を基軸に、UBCアジア学科(Department of Asian Studies)と早稲田大学の大学院生が、文化、歴史について様々な視点から議論を行うものである。「吉野記」とは、江戸時代前期の公家・歌人、飛鳥井雅章による歌文紀行である。自筆本が複数知られ、UBC蔵本はその一つである。報告者は7~8世紀の韻文学の視点から、「飛鳥井雅章と『万葉集』―飛鳥井雅章「吉野記」を視座に―」との題目で発表を行った。
以下、大まかなスケジュールを追う形で、滞在中の報告を行いたい。
まず、初日(到着日)は、司書の先生の案内のもと、Asian Centre内に置かれたAsian Libraryを見学させていただいた。Asian Libraryは広くアジアの文学・語学に関する多数の蔵書を有し、特に二階の東アジア文学のフロアを案内していただいた。その後、UBC大学院生と交流を行い、互いの専門分野や学問的興味関心などを話し合う機会を設けていただいた。UBC大学院生の研究内容は非常に多角的であり、比較文学的アプローチをとる研究が多いのが印象的であった。作品そのものを研究するのはもちろんのこと、文化、言語、学問領域の境界を軽々と越え、「作品を通して」考察を深めようとする海外の日本学研究の姿勢に触れたことは、日本国内で日本文学を専一に扱う報告者にとって蒙を開かれるものであった。今日、学問の細分化に対し、学際的な研究の重要性がより高まっている。一つの対象を深部まで突き詰めようとする姿勢の重要性は今後も変わらないが、今後はそれと並行し、周辺の様々な事象、異なる文化における事象を把握し、複合的に考察していくことが一層求められよう。UBCの国際的な日本学研究から、その手法等についても多くのことを学ばせていただいた。
滞在二日目は、冒頭の通り、「吉野記」について参加者が各々の興味関心に基づき発表を行った。吉野は今日でも桜の名所として名高く、雅章も吉野一帯の桜を目当てに各所を巡っている。一方で、良く知られるように吉野の地は古代から近現代まで、様々な話題を内包する特異な土地でもある。報告者は上代文学、和歌文学の立場から、主に「吉野記」の和歌にみえる『万葉集』の影響、また飛鳥井家と『万葉集』との関わりについて報告した。発表の後、貴重書室において、実際に「吉野記」を実見する機会をいただいた。大学附属図書館による精密な画像の公開やUBCの大学院生の調査報告によって、事前に大まかな様相を把握していたが、本の状態などは実見してはじめて解ることも多く、大変貴重な機会であった。
上記のほか、Christina Laffin先生、Christina Yi先生のご厚意で授業を見学させていただくなど、数多くの得難い機会をいただいた。加えて、本プログラムを通して得られた国境を越えた同世代の研究者との新たなつながりは、何よりも貴重なものであった。
本プログラムでお世話になった先生方、院生の方々に、この場を借りて心より感謝申し上げたい。