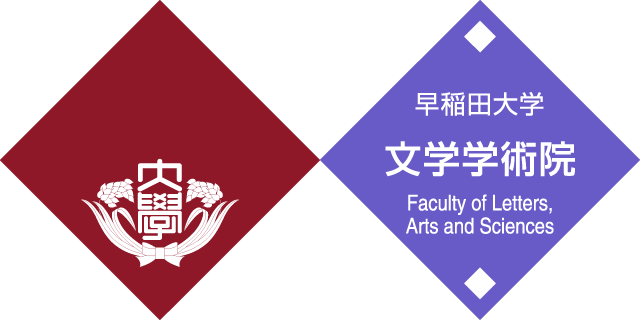- 学生報告書
- 金子聖奈 文学研究科 日本語日本文学コース
金子聖奈 文学研究科 日本語日本文学コース
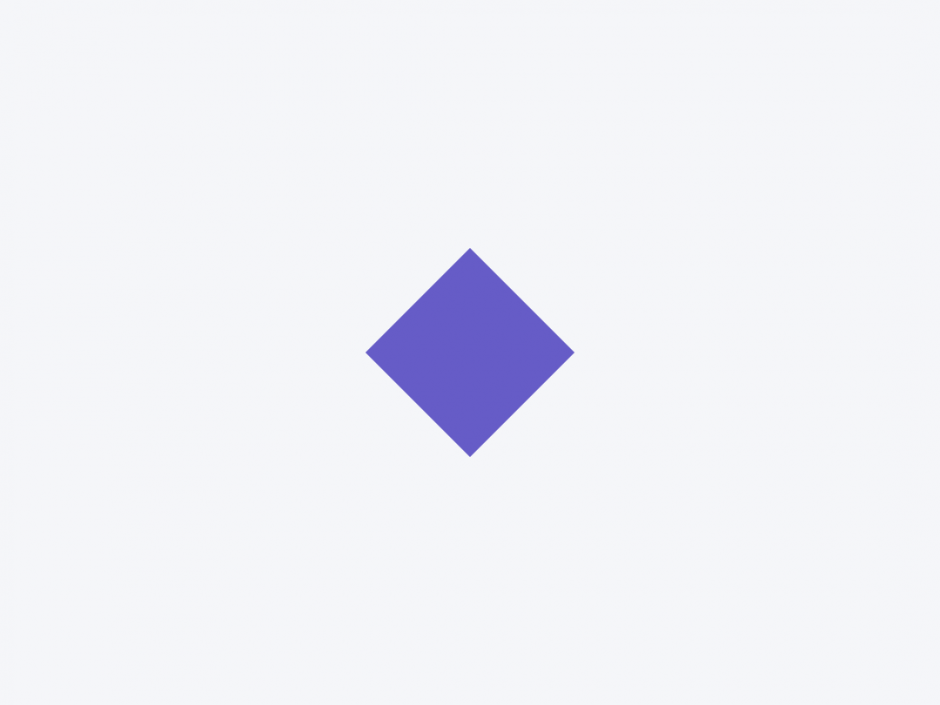
- Posted
- Wed, 11 Jan 2023
The Tadashi Yanai Initiative for Globalizing Japanese Humanities
UCLA-Wasedaリサーチ・フェローシップ・プログラム 報告書
文学研究科日本語日本文学コース博士後期課程2年 金子聖奈
今回、柳井正イニシアティブ グローバル・ジャパン・ヒューマニティーズ・プロジェクトによってUCLAのThe department of Asian Languages and Culturesに3ヶ月間(2022年9月〜12月、Fall Quarter)留学する機会を得た。日本にはない資料の閲覧、UCLAで研究を進めている大学院生との交流を通して、研究者としての立場性を根本的に考える時間ともなり、大変貴重な経験ができた。
滞在中は、主にUCLAの授業に参加しながら自分の研究に関する資料収集を行なった。授業に関しては、日本の大学にはあまり見られないModern Southeast Asian Literature(近代の東南アジア文学)のセミナーに参加できたことで、私が強い関心を寄せているフィリピンだけでなく東南アジアの作家による小説を幅広く学ぶことができた。私は日本近現代文学における〈フィリピン〉というトポスの解明を研究課題に据えている。これまでの私の研究では、日本とフィリピンの相互関係、あるいは、フィリピンの元宗主国であるスペイン、アメリカを含めた関係性を軸としてきたが、重要な文学的ネットワークが東南アジアにあることを見落としていたことに気づかされた。なお、このセミナーはJapanese Studies外のクラスであるが、Michael Emmerich先生が担当のGeorge Dutton先生を紹介してくださったことで受講がかなった。所属先に縛られずに関心のある授業を受講できたことも本プログラムの魅力の一つである。そのほかに、嶋崎聡子先生の近世文学と芸能を扱う大学院のセミナーに参加した。本セミナーは研究対象の時代を問わず、Japanese Studiesを専攻する院生が集まるものであったため、広範な視野が交差する場となっており、毎回濃厚なディスカッションができて刺激的であった。
私自身の研究・調査に関しては、司書のバイアロック・知子氏が適切な助言をくださり、日本では触れられない多くの資料に巡り会えた。例えば米国内に所蔵されている日本のフィリピン占領に関する資料や当時現地発行されていた雑誌、UCLAのスペシャルコレクションに所蔵されている19世紀末〜20世紀初頭にフィリピンで書かれたアメリカ人、フィリピン人の日記などである。今後は、こうした資料を生かしながらより研究を発展させていきたい。ほかの成果としては、UCLAの大学院生とパネルを組み、2023年7月の国際学会で研究発表を行なうことになった。国外の同世代研究者とネットワークができたことは大変うれしく、かけがえのない財産を得た気持ちである。
すでに他の派遣生のレポートでも言及されていることだが、米国における日本研究という環境に身を置いたことで、「日本人」というナショナル・アイデンティティを持ちながら日本で研究する、いわば自画像を描き直すような視点に対して、「日本」を他画像として描く視点があることを実感した。私は日本近現代文学における〈フィリピン〉に関するイメージを追究しているが、自分の研究がオリエンタリズムを再構築するかのごとく他画像を描く研究になってはいないかとの迷いがあった。しかし今回、「エリア・スタディーズ」という枠組から日本研究を見つめ直したことで、論者としていかなるパースペクティヴに立つべきかという根本的な問題への考察を深められたのは、何よりも大きな収穫であった。
最後に、今回の派遣に際して様々なサポートをしてくださったMichael Emmerich先生、早稲田大学とUCLAのスタッフの方々、UCLAの大学院生の方々に心より感謝を申し上げたい。