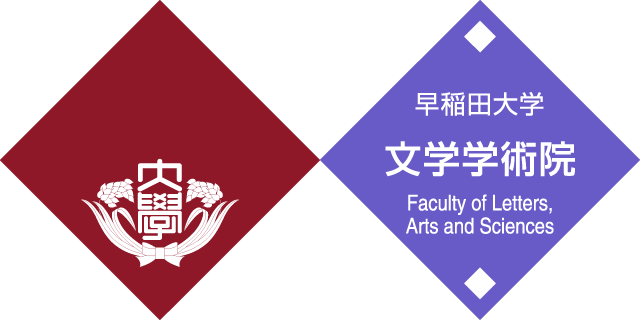- ニュース
- 開催報告 Dr. Jessica Chiba 講演会「Hamlet, Translation, and the Cultural Conditions of Thought」
開催報告 Dr. Jessica Chiba 講演会「Hamlet, Translation, and the Cultural Conditions of Thought」

- Posted
- 2021年12月6日(月)
本講演会は対面とZoomのハイブリッド形式により開催されました。当日は、学部生、大学院生(主に国際教養学部、文学研究科)、学内の教員が会場で参加し、他の学術機関、一般の方はZoomで参加されました。聴衆は少人数ではありましたが、非常に有益な講演内容であり、またその後の質疑応答も活発に行われました。

Chiba氏はまず、自身の翻訳研究が、原文と翻訳の関係に存在するヘゲモニーに疑問を呈することを目的としていることを説明されました。Chiba氏の研究は、翻訳者の不可視性に注目したローレンス・ヴェヌーティの影響を受けていることに触れた後、翻訳の核心として、ハムレットの第4独白に出てくる”be”という動詞と、これを日本語に翻訳することの難しさの考察を行いました。翻訳者の立場から”being”を考察することで、英語を母国語とする者にとっては当たり前の概念や論理の重要性が浮かび上がってくることを指摘されました。エドキンス牧師に代表される明治期の西洋と日本の日本語に対する見解は、どちらも一方的な文化進化論に基づいていましたが、Chiba氏はこのような言語決定論を否定し、ウィトゲンシュタインの思想を参考にして、言語が思考に与える影響を指摘しています。ウィトゲンシュタインは、”To be or not to be” のように、言語が広く受け入れられている構文上の文脈から切り離されたときに、哲学的な問題が生じると言っています。そうすると、このフレーズが翻訳できないのは、日本語が劣っているからではなく、この言葉を作り出している英語の使い方のためだということになってきます。続いてChiba氏は、日本における『ハムレット』の受容について考察し、英語や西洋哲学が日本に広く導入されるにつれて、『ハムレット』に対する態度がどのように変化したかを説明しました。最後に、シェイクスピアが英語の使い方を通じて、いかに存在を中心とした思考に焦点を当てているかを強調する力が翻訳にはあることを示唆して講演を終えました。
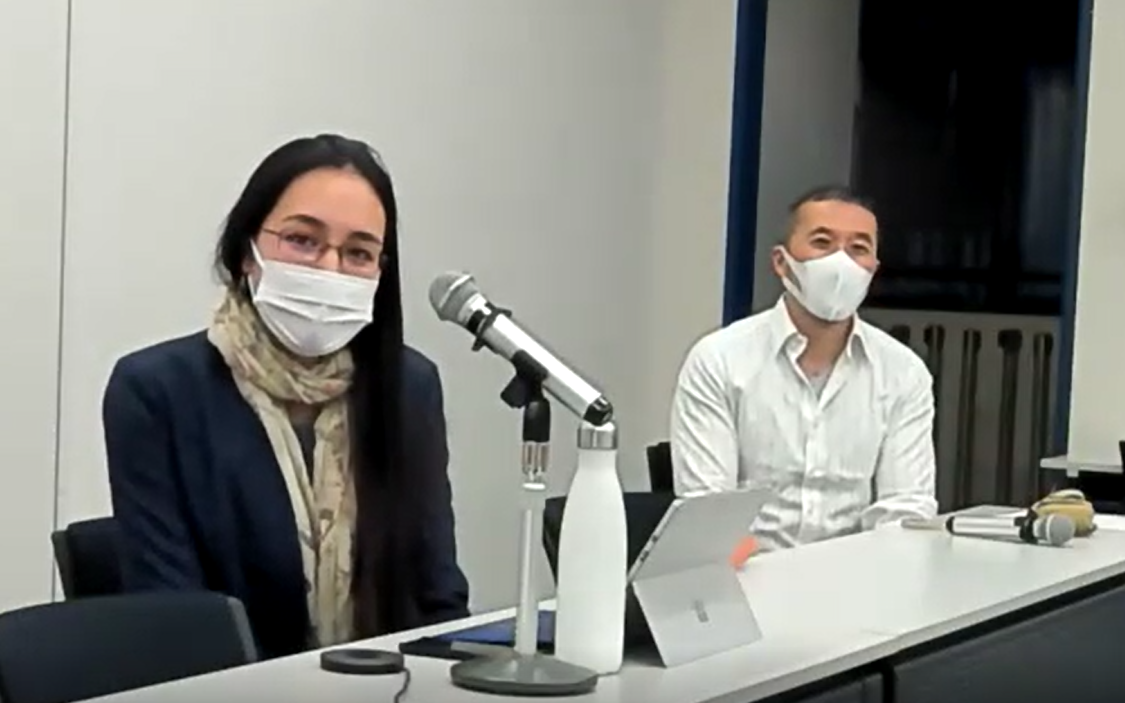 講演の後、30分ほど活発な質疑応答が行われました。Chiba氏の翻訳に関する議論 は、シェイクスピアが他のメディアに翻訳された場合、特にチャールズ・ラムのように散文に翻訳された場合にも適用されるのか、日本語の女性的、男性的な言葉がChiba氏の議論にどのような影響を与えるのか、ダジャレの翻訳がテクストの言っていることを明らかにするのにどのように役立つのか、チャールズ・ワーグマンの第4独白の翻訳についてなど、多岐にわたりました。 Chiba氏は、その後もさらに学生と個別に話し合うこともし、学生にとっても有意義な会になったと思われます。
講演の後、30分ほど活発な質疑応答が行われました。Chiba氏の翻訳に関する議論 は、シェイクスピアが他のメディアに翻訳された場合、特にチャールズ・ラムのように散文に翻訳された場合にも適用されるのか、日本語の女性的、男性的な言葉がChiba氏の議論にどのような影響を与えるのか、ダジャレの翻訳がテクストの言っていることを明らかにするのにどのように役立つのか、チャールズ・ワーグマンの第4独白の翻訳についてなど、多岐にわたりました。 Chiba氏は、その後もさらに学生と個別に話し合うこともし、学生にとっても有意義な会になったと思われます。
イベント動画の視聴は、こちらから
Dr. Jessica Chiba 講演会概要
- 日時:2021年11月11日(木) 9:00〜10:30
- 場所: 早稲田大学 8号館3階会議室
- 講演者:Dr. Jessica Chiba(The Shakespeare Institute, Leverhulme Early Career Research Fellow)
- 講演タイトル: ‘Hamlet, Translation, and the Cultural Conditions of Thought’
- ハイブリッド開催(Zoom併用)
- Tags
- イベントレポート