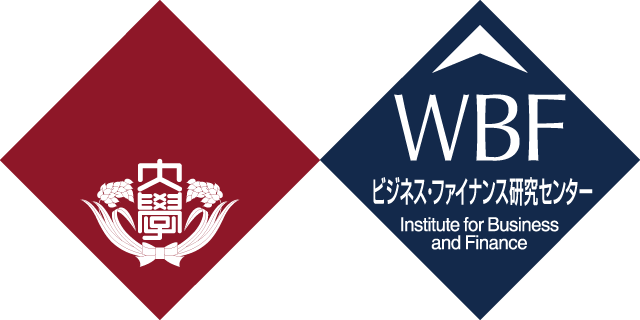- News
- 女性役員について考えることとは? 早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター主催『女性シニアリーダー育成プログラム』開催レポート
女性役員について考えることとは? 早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター主催『女性シニアリーダー育成プログラム』開催レポート

- Posted
- Tue, 20 Jun 2023

世界は転機を迎えつつあります。大きな技術革新と世界的な競争の時代です。
そうした中にある現代の企業経営に求められるのは、従来の発想に囚われずに新しい可能性に挑戦する大胆さと、グローバル化する世界の巨大なリスクに備える慎重さ、そして多様化する価値観に耐える柔軟さではないでしょうか?
その意味で、企業には社内外に説明できるガバナンスと、年齢、性別、人種、宗教、趣味嗜好などのダイバーシティを尊重することの2つが特に求められています。
また、岸田総理大臣は政府の男女共同参画会議で、最上位の上場企業の役員に占める女性の比率を2030年までに30%以上にする目標を示しています。
「女性活躍の推進を通じて多様性を確保し、イノベーションにつなげることは『新しい資本主義』や包摂的な社会の実現に向けて大変重要だ。関係閣僚が協力し、『女性版骨太の方針』のとりまとめに向け、政策の具体化を進めてほしい」と述べ、関係閣僚に具体策の検討を指示しました。
私達ビジネス・ファイナンス研究センター(WBF)は、日本、そしてアジアをリードする早稲田大学ビジネススクール(WBS)と一体になり、そうした不安定化する世界で企業を導く実践知の創造と供給の拠点となるべく、幅広い教育研修プログラムと研究プロジェクトを早稲田大学の内外に提供しています。
その一環として、この度、10年以内に会社の中核を担うシニアリーダーになりうる部長、上級課長クラスを対象とした「女性シニアリーダー育成プログラム」を企画しました。
今回は、2023年5月13日(土)に開催された本プログラム第11回目の講義(パネルディスカッション)『女性役員について考えること』を一部抜粋してお伝えします。
登壇者
-
長谷川博和
(早稲田大学ビジネススクール教授、早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター所長、専門分野:アントレプレナーシップ)

-
大山みこ
(経団連 ソーシャル・コミュニケーション本部統括主幹 /国際イメージコンサルティング・オフィス『CATCHY』 代表)

-
岡田歩
(オムロンヘルスケア株式会社 代表取締役社長、オムロン株式会社 執行役員常務)

-
金子久子
(サイネオス・ヘルス合同会社人事本部ディレクター/日本ブラインドサッカー協会副理事長)

キャリアは計画された偶発性理論
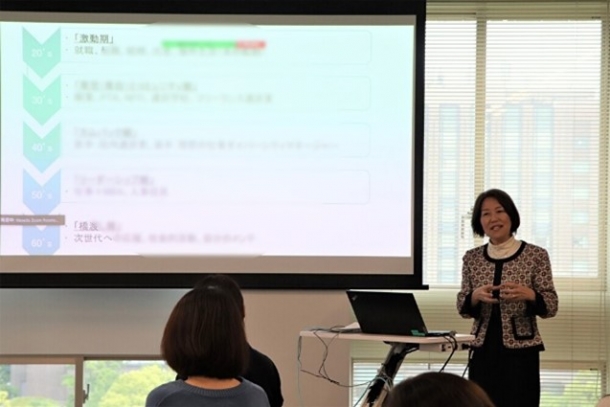
専業主婦、親業、アルバイト、自営業(フリーランス)、契約社員、正社員、管理職、執行役員、取締役、NPO理事を経験してきた金子さん。これまでのキャリアは、いわゆる王道の道ではなかったといいます。
「私の就活時代、四年制大学を卒業する女性は13%ほどで、女性を総合職に採用する日本の企業は殆どありませんでした。そこで外資系銀行に就職しました。20代は結婚と二人の子の出産、長男に障害がありキャリアは断念、30代は育児(=育自)とNPO活動、またフリーランス通訳の仕事を始めました。社内通訳者として企業でフルタイムの職に戻ることができた時にはすでに40歳になっていました。ある時経営会議でダイバーシティの推進が議題になり、私の問題意識を上司に伝えたことがきっかけで初代ダイバーシティーマネージャーに選任されました。それまで障害者のインクルージョンや女性活躍について考えてきた私にとって天職で、大変幸運でした。そして50代でMBA取得を思い立ち、早稲田大学の説明会を恐々聞きに行くと「女性の受験者が少ない」と。女性活躍を推進する自分が受験しなくてどうする(笑)と思い入学、卒業後は会社の経営陣に加わる機会も巡ってきました。60歳代に突入した今は、次世代への応援、社会的活動に軸足を移しつつあります。」

今年2023年3月にオムロン ヘルスケア株式会社 代表取締役社長に就任した岡田さん。
「大学卒業後は、すぐに社会人になるイメージがもてず、就職せずにオーストラリアへワーキングホリデーに行きました。翌年、帰国して日本で就職しましたが、女性は自動的にアシスタント(一般職)での配属でした。海外営業部に所属していましたが、営業して売上目標の達成を目指すといったことはやらせてもらえなかったことに違和感を覚えました。そこで、はじめて自分から「営業としてやらせてください」と希望を上司に伝えました。すると「数字を出したら総合職にする」と言われたので、頑張って結果を出して営業職になることができました。」
「MBAもとっていないし、金子さんもおっしゃっていたように私もキャリアとしての王道を通っていません。ただただ目の前のことを一つひとつ一生懸命にやってきたことが今につながっているのかなと思います」

経団連では、女性初の会長政策秘書として各界との調整にあたり、国際面では経団連米国代表など歴任し各国のエグゼクティブと交流をしている大山さん。イメージコンサルティング・オフィス『CATCHY』代表でもあります。

「先輩方が切り拓いてくださったおかげで、私の頃は総合職への道は確立されていました。ただ、まだ数は少なく、「交渉窓口は男性に代わってくれますか?」と言われたこともありました(苦笑)。その一方で、女性は覚えてもらいやすいという利点もありましたので、余計なことは気にせず、やるべきことをやろうと思って取り組んできました。自分なりの正義や問題意識を持って取り組んでいると、性別にかかわらず、チャンスを与えてくれたり導いてくださったり背中を押してくれる人が現れるということ。私はそういうメンターともいうべき方々との出会いによって、留学や海外駐在をはじめやりたいことを実現できてきたと思います。また、私の人生にとって、海外経験はかけがえのない財産。ここで得られた国際感覚からも、これからは個性の時代であり、日本の政財界トップや次世代リーダー達も、唯一無二の印象を残せる存在になっていく必要性を痛感し、米国発イメージコンサルティングを起業しました。これまでのキャリアは全て、自分の感性を信じてアクションに移してきたといえます。」
会社の中核を担うシニアリーダーになりうるみなさまに伝えたいこと
(金子さん)人事の立場からお伝えしたいのは、会社からチャンスを与えられたら断らないで、ということです。例えば昇格の話があったとすると、それまでに上司を含め多くの人があなたを推薦したり根回しをしています。あなたができるからこそ薦めているのです。なのに多くの女性が昇格を辞退してしまうのです。また、自らやりたいことがあったら率先して手を挙げてほしい。大山さんも岡田さんもお話しにあったように、自ら手をあげてきました。「まじめにコツコツ仕事していれば見出してもらえる」と思ったら大間違いです。キャリアは自分でつくるものです。あと、家庭との両立に関しては、コア業務以外は仕事もプライベートも手を抜く(アウトソーシング)ことが本当に大切です。
(岡田さん)私自身、悩んだり、悶々としたりした時期もあり、いろいろなリーダーシップの講義も受けてきました。リーダーにはいくつかの「型」があると思います。実際にリーダーを経験する中で、自分は仲間を信頼して任せる「イルカ型」なのかなと思いました。あまり気負わずに多様な人とコラボレーションして、いろいろな意見を受け止めて創造していくのが楽しいと思いました。今年、社長になりましたが、事業戦略を実践するときにはその実行者である「人」が特に大切だと感じています。そこで、オムロン ヘルスケアでは、多様化する人財が進むべき方向をわかりやすく言語化した指針「人財ポリシー」を作成し、その浸透に向けて様々なアクションをとっています。中でも、社員同士の対話を大切にしていて「TAKIBI」というダイアログを実施しています。実際に「たき火」をみんなで囲むととってもいい効果があるんですよね。会社の中ではたき火はできないので、ぬいぐるみを買ってきて実際にたき火を囲んでいる雰囲気を出しています(笑)。私自身も、社長室をやめて社員みんながいるフロアーにデスクを設けて社員が声をかけやすいフラットな環境をつくっています。人と人とを繋げる機会をつくること、ぜひみなさんにもやっていただきたいと思います。
(大山さん)私は、経団連でDE&I の推進も担当しているのですが、経団連という組織の中で自分自身が多様性の象徴であると認識していますし、これからもその大切さを体現していきたいと思っています。そして、次世代リーダーの皆さんには、これから必要なコンピテンスとして、1.何事も「楽しむ力」「遊び心」を忘れずに、2.変化のスピードが激しい時代に必要な「決断するチカラ」、3.「パーソナル・ブランディング」の重要性をお伝えしたいと思います。日本人は特に「人と違う」ことを気にしてしまう文化がありますが、これからは「違い」=個性を楽しみましょう!また、大企業とベンチャー企業の決定的な違いは、決断する機会です。私は、なるべく部下に決断してもらい、「なぜその決断をしたのか?」をセットに聞いています。急速に変化していく世の中、ビジネスチャンスを逃さないようにしなければなりません。そして、組織に依存せず、能力・個性を武器に唯一無二の市場価値を創っていく生き方。キャリアとライフは天秤にかけず、二兎も三兎も追って、様々なチャレンジをしていただきたいと思います。
質疑応答

(受講生)社長、役員という立場になると、常に結果や成果を出さないといけないと思っております。意識していることはどのようなことでしょうか?
(金子)重要なのは結果を可視化すること。いつも部下に言っていることは「その仕事の結果、なにか変わった?」と「変化」を聞いています。ただ仕事をしましただけではダメなんです。私自身も、数字で示せるようにしますし、なにより変化を意識しています。
(大山)結果を出し続けているだけではないのですが、失敗してからどうするかを大事にしています。どうしてその失敗が起きたのか突き詰めて考え、繰り返さないことをすごく意識しています。組織にいると、成果が目に見えないものが多いですし、経団連だと特にそうです。金子さんおっしゃったように「変化」を起こすのが大切です。どこからどこへもっていったのか示す。チームでやっているので、しっかり上に見せる。でないと埋もれてしまいます。
(岡田)経営者になると結果としての業績はもちろん大切ですし、常に達成することを求められます。実際に厳しい局面も多々あります。私自身、正直なところここまでくるのに成功ばかりではありませんでした。また、周りの役員やトップマネジメント層をみわたしてみても、どれだけ成功してきたかではなく、どれだけ挑戦したか、失敗してもその失敗をどう次に活かしたかが重要視されているように思います。会社をより良くしたいという情熱をどのように行動にうつしたかということが結果なのでは、と思います。
(金子)岡田さんも社長に就任されて人財ポリシーを作り、実際にアクションをとったように、あなたが信じていることをやってほしい。
講演後には受講者から多くの質問が飛び交い、盛況のうちにパネルディスカッションは幕を閉じ、受講生のキャリアアップに対する意欲の更なる高まりを感じました。
「ご登壇いただいた御三方は、立場でものを言うのではなく、価値観や理念といった人間性を持って言われているからこそ相手に響くのです。人に対する人間観を磨いていくことがこの時代は重要なんだと思いました。部下は見ています、人間観を磨いていきましょう。」
講義は長谷川先生のこのようなお言葉で締めくくりました。
今回、23名の二期生で熱い議論を交わしています。早稲田大学ビジネススクールの教員を中核とした講師陣によるアカデミックな講義から、トップ経営者とのディスカッション、個人アセスメントの実施を通じて、本研修を通じて向上すべき課題点を明確にした上で、カリキュラムを進めています。
ビジネス・ファイナンス研究センター(WBF)は、年間を通じ様々なノンディグリーオープンプログラムを開催しております。詳細はこちらをご覧ください。