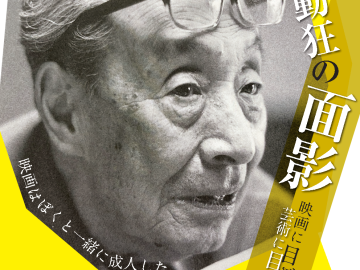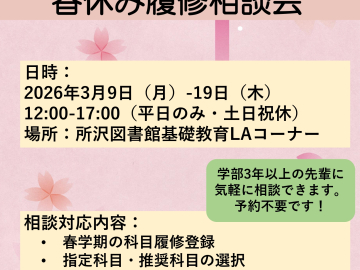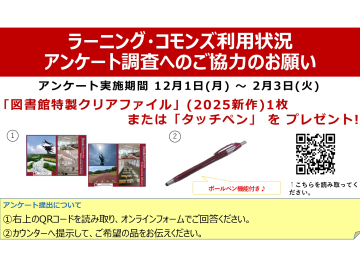人間科学学術院
| 岩崎 香 准教授 |
| べてるの家の「非」援助論 : そのままでいいと思えるための25章 / 浦河べてるの家 著 |
| 医学書院, 2002.6, (シリーズケアをひらく) |
| 「べてるの家」は1978年に北海道浦河の浦河教会の旧会堂を拠点として心に病をもつ人たちが活動をはじめました。今やその活動は精神保健福祉分野のみならず、多領域にも大きな影響を与え続けています。 これまでメンタルヘルス領域で常識とされてきたことを、ことごとく覆して成功を収めてきた「べてるの家」の理念を学ぶには最適の一冊です。私も数回訪れ、 今も交流がありますが、「弱さを絆に」「昇る人生から降りる人生へ」など逆転の発想が、いかに自分たちが援助者たろうとして、「援助」を正当化し、被援助 者を抑圧してきたかということに気づかせてくれます。合理性や効率性が追及される社会の中で、どう生きるべきかを再考したい人にもお勧めです。 べてるねっと http://bethel-net.jp/ |
 |
 |
| 扇原 淳 准教授 |
| 社会を結びなおす : 教育・仕事・家族の連携へ / 本田由紀 著 |
| 岩波書店, 2014.6, (岩波ブックレット ; No.899) |
| 本書は、若い学生諸君が自らの経験や周辺の出来事をヒントに、自らの事として思考しやすい「教育・仕事・家族」を題材としており、社会全体に通底する問 題を細分化したままにせず、複眼的、包括的に読み取る姿勢・試みの重要性を理解させてくれる。読み進めていく中で湧き出る衝動や疑問を解消するために、講 義・演習での学びを大切にすることと合わせて、キャンパスを飛び出す積極的なアウトリーチ活動で、あなた自身と社会を結びなおしていくことを試みてほし い。 |
 |
 |
| 石島 このみ 助手 |
| 森の旅人 / ジェーン・グドール,フィリップ・バーマン 著 ; 上野圭一 訳 ; 松沢哲郎 監訳 |
| 角川書店, 2000.1 |
| 本書は野生チンパンジー研究のパイオニアであり、国連平和大使でもある女性、ジェーン・グドール博士の自伝です。大好きな動物と暮らすことを夢見る少女 であった彼女が、いかにして野生チンパンジー研究の世界に入り、何を見て、何を考えながら、一人の女性・研究者・人間として、生きてきたのか。その軌跡が 描かれています。学位も持たずにほぼ単身でアフリカに渡り、ひたすらチンパンジーと向き合い続け、そのやわらかくも鋭い観察眼でそれまでの常識を覆す発見 をしていく姿がとにかく格好良く、胸を打たれます。しかし、それだけでは終わらないのが本書。進化、戦争、悪、愛、科学、神、霊性、動物の心、そしてヒト の本性とは何なのか?ヒトに希望はあるのか?そうした問いについて、深く考えるきっかけを与えてくれる一冊です。 |
 |
 |
| 岡部 杏子 助手 |
| ボヌール・デ・ダム百貨店 / エミール・ゾラ 著 ; 伊藤桂子 訳 |
| 論創社, 2002.11 |
| この小説の舞台は19世紀パリの百貨店です。主人公ドゥニーズは弟二人を養いながら、そこで売り子として孤軍奮闘します。勤勉で貞淑な彼女に店主ムーレ は惹かれてゆきます。新奇な商品を格安で提供し、街中の女性の心をわしづかみにするムーレは、果たして彼女を手に入れることができるのか? この恋模様はもちろん、人々の物欲を刺激する経営戦略や流行の創出といった百貨店の社会的・文化的機能を考察できるのも本書の魅力です。 |
 |
 |
| 米谷 雄介 助手 |
| アドラー心理学入門 : よりよい人間関係のために / 岸見一郎 著 |
| ベストセラーズ, 1999.9, (ワニのnew新書) |
| アドラーは、フロイト、ユングと並び立つ心理学3大巨頭の1人であり、本書はそのアドラーが創始した個人心理学(通称:アドラー心理学)を総括的に解説 した書です。誰もが多かれ少なかれ悩みを抱えています。これに対してアドラーは人間が持つ悩みの根源は全て対人関係によるものであると述べており、アド ラー心理学は実践の学として、よりよい対人関係を構築するための指針を示します。本書が皆さんにとって、より幸せな、かつ力強い生き方を知るための糧とな ることを期待します。 |
 |
 |
| 島崎 崇史 助手 |
| モモ / ミヒャエル・エンデ 作 ; 大島かおり 訳 |
| 岩波書店, 2005.6, (岩波少年文庫 ; 127) |
| ミヒャエル・エンデの「モモ」は、日本の小学校の図書館等でも読まれているポピュラーな児童書のひとつだと聞いています。ですが、私がこの本と出会った のは、大学院修士課程2年生、24歳の時、当時お世話になっていた大学の先生の研究室でした。学生の皆さんも、もしかしたら、タイトルだけ見たことがあ る、読んだことがある、という方も多いかもしれません。 皆さんも大学を卒業して、仕事をするようになると忙しさに追われ、「自分の人生の時間の使い方」に今よりももっと向き合うことがあるかもしれません。こ の本は、「時間とは何か」について生きていく上でのヒントをくれる作品だと思います。「時間をケチケチすることで、ほんとうはぜんぜんべつのなにかをケチ ケチしているということには、だれひとり気がついていないようでした。・・・(中略)・・・人間が時間を節約すればするほど、生活はやせほそっていくので す。」(p.106)。 私もこの言葉の意味を、働くようになってから考えさせられました。「時間がない」と言わず、興味を持った方は、ぜひ手に取っていただければ幸いです。 |
 |
 |
| 沈 睿 助手 |
| The R book [electronic resource] / Michael J. Crawley. |
| Wiley, c2007. |
| ”It may seem strange to include a new edition of a textbook in the preview, but I feel that this is one that is definitely worth highlighting. It is a classic that does not just sell to students during term time but has a much wider appeal … This edition will sell really well on publication.” (The Bookseller, 16 December 2011) “There is a tremendous amount of information in the book, and it will be very helpful … .This is a potentially very useful book.” (Journal of Applied Science, December 2008) “…if you are an R user or wannabe R user, this text is the one that should be on your shelf. The breadth of topics covered is unsurpassed when it comes to texts on data analysis in R.” (The American Statistician, Aug 2008) “The R Book; provides the first comprehensive reference manual for the R language.” (Statistica 2008) “…a 950-page comprehensive reference manual for what is perhaps becoming the most powerful and flexible statistical software environment…” (CHOICE, December 2007) ‘The High-level software language of R is setting standards in quantitative analysis. And now anybody can get to grips with it thanks to The R Book…’ (Professional Pensions, 19th July 2007) |
 |
 (こちらは冊子版です) (こちらは冊子版です) |
| 鷹田 佳典 助手 |
| At the will of the body : reflections on illness / Arthur W. Frank. |
| Houghton Mifflin, 2002., 1st Mariner Books ed. |
| からだの知恵に聴く : 人間尊重の医療を求めて / アーサー・W.フランク 著 ; 井上哲彰 訳 |
| 日本教文社, 1996.5 |
| 本書は、心臓発作とがんという、命に関わる病気に立て続けに襲われた医療社会学者のアーサー・フランクが、自身の体験を踏まえて書いた一種の闘病記で す。研究者が書いたものですが、文章は平易でとても読みやすい内容になっています。「病気」と「病い」はどう違うのか。病いの価値とは何か。ケア提供者に 求められることは。健康や病い、医療などに関心を持つ人には、是非手にとって欲しい一冊です。同著者による『傷ついた物語の語り手』(ゆみる出版)と合わ せて読むと、さらに理解が深まります(ただしこちらは少し専門的な内容になっています)。 |
| 【Reprinted】 |  |
|
| 【翻訳本】 |  |
 |
| 田代 恭子 助手 |
| ハーモニー / 伊藤計劃 著 |
| 早川書房, 2014.8, 新版, (ハヤカワ文庫 : JA ; 1166) |
| この本では、誰もが健康で天寿をまっとうでき、憎しみも怒りも存在せず、隣人と和を保って生きていく理想的な社会が描かれています。 読み進めていくうちに、その幸福の代償として払っている対価が何なのか、わかってきます。 私は、その対価を支払わなければいけないのなら、この幸福な社会を到底受け入れられないと思いました。 「本当の幸せ」とはなんなのかを考えたことがある人には、ぜひ一度読んでほしい作品です。 |
 |
 |
| 鶴田 利郎 助手 |
| 家庭や学級で語り合うスマホ時代のリスクとスキル : スマホの先の不幸をブロックするために / 竹内和雄 著 |
| 北大路書房, 2014.2 |
| 近年、大学生や高校生だけでなく、小、中学生にもスマートフォンの利用が広がってきています。インターネットは本来、人々の日常生活や学習、仕事などの 利便性を大いに高めてくれるものです。しかし一方で誤った使い方をしてしまうと、インターネットが自分や他者の心身の健康や財産、人権などを脅かす非常に 危険なものになってしまいます。この本を通して、いろいろな人とインターネット利用に関わる問題のリスクについて語り合ってみてはいかがでしょうか。 |
 |
 |
| 中村 愛 助手 |
| 失敗のメカニズム : 忘れ物から巨大事故まで / 芳賀繁 [著] |
| 角川書店, 2003.7, (角川文庫 ; 13020) |
| 人はエラーをする生き物です。忘れ物をしたり、電気を消し忘れたり、電車を乗り間違えたり。恐ろしいのはそんなちょっとしたエラーが時には大事故に繋 がってしまうことです。この本は、「安全」を脅かすヒューマンエラーのメカニズムをわかりやすく解説した一冊です。メカニズムと聞くと何だか小難しそうで すが、ユーモア溢れる文章で一気に読めます。 みなさんは日頃どれくらい「安全」を意識して生活していますか。私が大学生の頃はほとんど意識したことはありませんでした。しかし,院生の頃にeスクー ルで教育コーチを担当し社会人学生と話す機会が多くなってから、また自分が働き出してから、社会では「安全」が非常に重要視されていると知りました。事故 は財産や健康、それまで築きあげてきた信頼を一瞬で奪います。親や学校や社会に守られている学生時代は意識する機会は少ないですが、事故を防ぐことは企業 にとって利益を上げることと同じくらい重要なことで、「安全」を考えていない企業は一つもありません。それはどの業種でもそうです。 社会に出たらみなさんが「安全」を守っていく立場となります。なぜエラーをしてしまうのか、エラーをしないためにどうしたらいいのか、エラーをしたとき にどうしたら致命的な事態に陥らないで済むか、この本にはそのヒントが数多く詰まっています。社会に出る前のみなさんにこそ読んで欲しい一冊、増版が繰り 返されるベストセラーです。 |
 |
 |
| 日野 智豪 助手 |
| カチアートを追跡して. 全2巻/ ティム・オブライエン 著 ; 生井英考 訳 |
| 国書刊行会, 1992.3, (文学の冒険) |
| 本書はアメリカ史上、唯一敗戦した戦争、ベトナム戦争に光をあてる。それは、著者ティム・オブライエンが従軍した、「その」経験が強く心に刻まれている からに他ならない。物語は、ベトナムからパリへ歩いて逃亡を謀った脱走兵カチアートと彼を追跡する兵士たちの間でエキセントリックに繰り広げられる。そし て、カチアートの追跡とベトナムでの戦争体験が交互に語られる。冒頭に列挙される戦死した兵士たちはいかにして死んでいったのか?死を目の当たりにし、逃 亡したカチアートは責められるべきなのか?この追跡劇と戦死者たちにどのような関係性があるのか?そもそも、国のために自らの命を捧げることにどのような 意味があるのか?カチアートはなぜ、歩いてパリを目指したのか?何のためにたったひとりの脱走兵を追跡したのか?バカな道化を演じるカチアートこそがアメ リカの抱える闇ではなかったのか? 小説の読み方は多様である。読者それぞれの解釈で、カチアートを、追跡兵たちを、旅路で出会う人びとを、戦死者たちを、ベトナム戦争を、追体験してもら いたい。1979年全米図書賞に輝いた本書を世に送り出した、戦争という非日常体験を語るティム・オブライエンの面白さがそこにはあるだろう。 |
| 【1】 |  |
 |
| 【2】 |  |
 |
| 宮崎 球一 助手 |
| ら抜きの殺意 / 永井愛 著 |
| 而立書房, 1998.2 |
| ら抜きの殺意 [映像資料] : テアトル・エコー公演115 / 永井愛 作・演出 |
| カズモ, c2009 |
| あなたは普段「ら抜き言葉」を使っていますか?言葉は時代とともに変わっていくものなので、ら抜き言葉ももうすぐ一般的に認められるようになるでしょう。ただ、私は「ら入り言葉」が惜しまれることなくこのままなくなっていくのがイヤなので、日々悪あがきしています。 『ら抜きの殺意』は、永井愛という劇作家・演出家の戯曲です。どうしても「ら」を抜きたい男、どうしても「ら」を入れたい男、過剰敬語を操る女などな ど、作中人物たちが抱く殺意に触れながら、ら抜き言葉や敬語といった問題に限らず、あなた自身が「自分が普段使っている言葉」について観察し、考えること になるでしょう。私の専門である臨床心理学・カウンセリングでは、これはとても大切なことで、戯曲を読むことは自分の言葉について考えるきっかけになると 思います。 |
| 【図書】 |  |
 |
| 【DVD】 |  |
 |
スポーツ科学学術院
| 田口 素子 准教授 |
| 僕は絶対あきらめない : 車いすテニスに夢をかけた22歳の生と死 / 竹畠明聡,竹畠伊知郎 著 |
| 麗澤大学出版会, 2011.8 |
| 右足大腿骨骨肉腫で23歳で亡くなった青年と家族の手記。車いすテニスに夢をかけた青年は、現在私の研究室で学ぶ院生のお兄さんである。「諦めてしまう ことの怖さに比べれば、あきらめないことがどれだけ楽か」という一言は、闘い続けた彼の言葉だからこそ胸を打つ。目標を持った人間の強さ、不屈の闘志だけ でなく、その明るさと優しさに触れ、心から感動する一冊。同世代の青年の生きざまに触れることで、あなたの”いま”を見つめなおすきっかけとなるに違いな い。 |
 |
 |
| 深見 英一郎 准教授 |
| 人は誰もがリーダーである / 平尾誠二 著 |
| PHP研究所, 2006.11, (PHP新書 ; 431) |
| 平尾氏は、コーチングとは何か? と問われた際、「余りの出る割り算をあたえること」と述べている。多様な才能、個性が集うチームをまとめ上げる上で一 定の規律が求められるが、一方で組織には「曖昧さ」を残しておくことも大切だという。既存の戦術を踏襲し突き詰めるだけでは少しもおもしろくないからであ ると。もっと強くなりたい!そのためにはチームづくりが課題であると感じているあなたにお薦めの本です。 |
 |
 |
| 松岡 宏高 准教授 |
| 「社会調査」のウソ : リサーチ・リテラシーのすすめ / 谷岡一郎 著 |
| 文藝春秋, 2000.6, (文春新書 ; 110) |
| 今さら何を言っているのか思いますが、今年は研究倫理の問題が大きく取り上げられています。本書では、不適切な方法を用いた様々な社会調査の報告を批判 しています。皆さんは、論文作成において、本書の事例のような過ちを犯さないようにしてください。また、参考資料や文献の検討においても、誤った方法論を 用いている調査などに騙されないでください。ウソを見抜けなければ、あなたがウソを書くことになります。 |
 |
 |
| 吉永 武史 准教授 |
| 兎の眼 / 灰谷健次郎 [著] |
| 角川書店, 1998.3, (角川文庫 ; 10634) |
| 教職をめざすきっかけに、自らの人生に大きな影響を与えた恩師との出会いがあったことを語る教師たちは多い。様々なことに思い悩むことが多い学校生活に おいて、未来へ向かって歩んでいけるよう傍に寄り添ってくれた先生の存在は何物にも代えがたい宝である。本書に登場する小学校教師の小谷芙美先生は、まさ にそのような存在といえるだろう。 「教育」という言葉は、教師が学習者に対して一方的に知識や技術を伝達する行為と捉えられがちである。しかし、教育では、学習者の「内発を促すための外 発」であるという視点を持つことも大切である。読み書きがうまくできない臼井鉄三に学ぶことの意味に気づかせたり、クラスの子どもたちに障がいをもつ人と 共に生きていくこととは?を考えさせ、行動させたりする小谷先生の奮闘ぶりには、読み進めながら思わずエールを送りたくなる。また、教師は「教える」存在 であると同時に、子どもから「学ぶ」存在でもあるということも小谷先生の生き様は教えてくれる。 グローバル化や知識基盤社会とどのように向き合っていくかが教育の世界でも問われている。他方で、教師の多忙さやモンスターペアレンツなど学校を取り巻 く諸問題も解決の糸口が見えない。子どもたちの人間形成には教師の存在が必要であるのは言うまでもないが、その教師を支える家庭や地域の存在も必要不可欠 である。そのことを象徴する一文が、以下のように書かれている。 「…わしら教育のことはようわからんけど、自分とこの子さえよかったらええという考え方にはさんせいできまへんな。これは、もちろんエエカッコのことばで す。そんなことをいうとったら、この世の中、生きていけまへん。それをようわかっとって、あえていうてまんねん。そういう世の中やからこそ、いっそう学校 で思いやりというもんを教えてほしいと思いまんな…」(p.156) 教職をめざしている学生には是非とも読んでもらいたい一冊である。きっと教師になりたいという情熱がますます高まることだろう。 |
 |
 |
| 平山 邦明 専任講師 |
| ソロモンの指環 : 動物行動学入門 / コンラート・ローレンツ 著 ; 日高敏隆 訳 |
| 早川書房, 2006.6, (1963年刊の新装版) |
| 動物行動学の第一人者が書いた本です。動物たちと行動を共にしながら、彼らの行動を絶え間なく観察し続け、その意味するところを、名探偵のように紐解い ていきます。ユーモアに富んだ筆致で、教科書的な堅苦しさはありません。動物が苦手な人も、サイエンスとは縁遠いという人も、 騙されたと思って手にとってみてください。一気に読み進めることができるはずです。 読書の際は、様々なジャンルの本を並行して読むのも面白いかもしれません。もし、何を読むか決まっていないのであれば、『リーマンショックコンフィデン シャル(上・下)』(アンドリュー・ロス・ソーキン・著、加賀山卓朗・訳)を手にとってみてはいかがでしょうか。アメリカ発の金融危機リーマン・ショック がいかにして起きたのか、関係者200名、計500時間のインタビューをもとに検証しています。ローレンツの本とは手法もテーマも全く異なりますが、これ もまた人間という生き物の本性に迫った好著です。ぜひ、読書を通じて”答え”ではなく”問い”、言い換えれば、自分のわからないこと、知らないこと、想像 したこともなかったことに出会ってもらえればと思います。 |
 |
 |
| 小木曽 航平 助手 |
| 身ぶりと言葉 / アンドレ・ルロワ=グーラン 著 ; 荒木亨 訳 |
| 筑摩書房, 2012.1, (ちくま学芸文庫 ; ル6-1) |
| この本の作者はAndré LEROI-GOURHAN(1911-1986)である。ルロワ=グーランの研究関心は技術、先史学、人類学、社会学、美学など多岐に渡る。そんな〈分 類不能〉な稀代の研究者であった彼の、まさに面目躍如となる作品が本書、『身ぶりと言葉』であろう。 大学院生だった当時、スポーツ人類学の研究を始めたばかりの私に、〈身体〉という研究対象の奥深さ、難解さ、そして面白さを教えてくれたのが、この本 だった。豊富な学識を背景に、巨視的な視点から人類文化の発展を論じる壮大な試みとしての本書は、学門をすることの多大な魅力を我々に教えてくれる最良の 書物である。 |
 |
 |
| 中村 哲也 助手 |
| 人種とスポーツ : 黒人は本当に「速く」「強い」のか / 川島浩平 著 |
| 中央公論新社, 2012.5, (中公新書 ; 2163) |
| 「黒人やっべー!」。テレビでスポーツ中継を見ながら思ったことあるでしょ? ウサイン・ボルトやレブロン・ジェームズ、タイガー・ウッズのプレイを見 れば、誰だってそう思う。でも、彼らがすごいのは黒人だから? 実は100年前のアメリカでは、「黒人=体が弱い」ってイメージが主流だった。昔は、バス ケも100m走も、白人しかいなかった。「黒人=身体能力が高い」と素朴に考えている人には、目からウロコが落ちる一冊! |
 |
 |
| 水口 暢章 助手 |
| 進化しすぎた脳 : 中高生と語る「大脳生理学」の最前線 / 池谷裕二 著 |
| 講談社, 2007.1, (ブルーバックス ; B-1538) |
| 著者の池谷裕二先生は、44歳の若さにして東京大学薬学部教授に就任した日本屈指の神経科学者です。この本は、副題にもあるように、中高生が理解できる ようにわかりやすく神経科学トピックをまとめた本ですが、玄人が読んでも楽しめる濃い内容になっています。脳はブラックボックスと思われがちですが、すで にこんなことも解明されているのかと驚くこと間違いありません。脳の仕組みを知ることで自分自身を深く理解できるのでは。 |
 |
 |