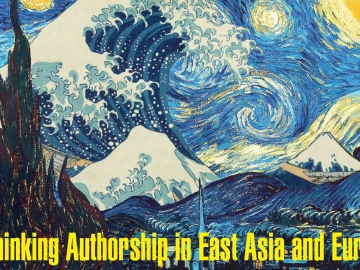2022年7月22日、ケビン・マイクル・スミス Kevin Michael Smith 氏(University of California, Berkeley) の講演会が戸山キャンパスで開催された。1920年代日本における未来派の詩に焦点を当てた本講演会は、神原泰(1899~1997)、平戸廉吉(1893~1922)、萩原恭次郎(1899~1938)らの詩を取り上げ、彼らの詩の中で都市の騒音(ノイズ)が視覚と聴覚の共感覚を通じてどのように表現されているのかを考察したものである。本講演会は鳥羽耕史教授(文学学術院)によって企画され、対面とZoomウェビナーで同時開催された。

研究員として早稲田大学を訪問したスミス氏は、植民地時代朝鮮における詩と詩学を研究してきた韓国近代文学・文化の専門家である。2019年にカリフォルニア大学デイビス校で比較文学の博士号を取得し、現在はカリフォルニア大学バークレー校東亜言語文化学科で助教授を務めている。スミス氏は、まもなく初の単著Shuddering Century: Modernist Poetry in Colonial Korea and the Poetics of Historical Difference(『戦慄する世紀:植民地朝鮮のモダニズム詩と歴史的差異の詩学』)を上梓する予定である。1920年代、30年代における植民地朝鮮の詩がヨーロッパや日本のアヴァンギャルド芸術をどのように受容したかを分析した研究書である。
20世紀初頭にイタリアで勃興した未来派は、急速な近代化と機械文明の発達がもたらした新しい視点を芸術に取り入れようとした運動であり、その表現媒体は、詩から絵画、写真、建築、そして音楽に至るまで、多岐にわたっている。スミス氏は、未来派の代表的な画家であるウンベルト・ボッチョーニの「都市は立ち上がる」(1910年)、カルロ・カッラの「サイクリスト」(1913年)などの絵画を会場のスクリーンに映しながら、未来派が表現した都市のダイナミックな風景とスピード感について紹介し、その背後にある産業資本主義の発達や、急速な機械化・都市化などの歴史的背景について説明することから講演を始めた。

1909年、イタリアの詩人フィリッポ・マリネッティがフランスの『ル・フィガロ』誌に発表した「未来派宣言」に端を発するこの思潮は、早くもその三カ月後、森鴎外が雑誌『スバル』に同記事の翻訳を掲載することで日本にもほぼ同時期に紹介された。ただし未来派運動が日本で盛んになったのは、都市文化が飛躍的な発達を遂げた大正後期、すなわち1920年代からのことである。スミス氏は、神原泰の『未来派研究』(1924年)、『新興芸術の烽火』(1926年)などの書物や、1920年に渡日したロシアの未来派画家ダヴィド・ブルリュークの日本における活動と木下秀との共同著作『未来派とは?答へる』(1923年)、そして平戸廉吉が1921年に日比谷公園前で配布したリーフレット「日本未来派運動第一回宣言」などを紹介し、日本における未来派運動の様子を概観した。スミス氏は、「日本未来派運動第一回宣言」から次の一節をも紹介した。「図書館、美術館、アカデミーは、路上を滑る一自動車の響にも値しない。試みに図書堆裡の唾棄すべき臭気を嗅いで見給へ、これに優ることガソリンの新鮮は幾倍ぞ」。路上を走る自動車のスピーディーな感覚描写にあわせ、ガソリンの臭いを「新鮮」と語るところから、1920年代に目撃するようになった新しい都市文明に対する驚きが伺える。
以上のような未来派の運動の中でも特に詩は、紙面上の言葉の配置がもたらす視覚的効果を通して、都市における強烈で真新しい近代的体験をダイナミカルに再現しようとしたといえる。その具体的な表現技法として未来派の詩人たちは、オノマトペ(擬音語・擬声語・擬態語)の多用と活字の分散的配置といった、彼らが「自由状態の言語」(“words in liberty”)と呼ぶテクニックを駆使した。スミス氏はこうした詩が都市の騒音を繰り返し描写していることに注目すべきであると指摘し、共感覚的に表現されたこの音響こそが、未来派の詩においてとりわけ重要な構成要素をなしていると述べた。

そのうえでスミス氏は、齋藤桂が『1933年を聴く:戦前日本の音風景』(2017年)の中で用いた「音風景」――風景としての「音」――という概念について言及し、従来視覚的な表現の斬新さに批評の重点が置かれてきた未来派の詩を、それが描き出してみせる都市の音風景のほうに留意して鑑賞してみることを提案した。その具体例としてスミス氏は、平戸廉吉の死後に公開された「合奏」(1931年)、萩原恭次郎の詩集『死刑宣告』(1925年)に収録された「露台より初夏街上を見る」などの詩をスミス氏自身の英訳とともに紹介した。これらの未来派の詩は、新しい都市文化と機械文明を象徴する様々な語彙とオノマトペ、そして特殊記号を紙面の随所に散りばめることによって、あたかも飛行機や高層建物の上から都市を鳥瞰するような視覚イメージを創り出している。ただしこうした詩が他の視覚媒体である写真や絵画と異なるのは、そのイメージが、音声と意味内容を同時に含む文字の組み合わせによってできているということである。この点において未来派の詩は、視覚イメージにあわせ、言葉に結び付いた音声イメージを同時に喚起させる共感覚的機能を持っているのである。

*上に引用した「露台より初夏街上を見る」の図版は、萩原恭次郎の詩集『死刑宣告』(1925、長隆舎書店)より抜粋・編集したものである。
最後に、スミス氏は、萩原恭次郎の詩「露台より初夏街上を見る」の詳細な分析を行って本講演を締め括った(上の画像を参照、詩集『死刑宣告』(長隆舎書店、1925年)より抜粋・編集したもの)。高いバルコニーから見下ろした、関東大震災後に復興を遂げつつあるモダン都市東京の全体像と、個々の単語とオノマトペが織りなす地上レベルの音風景がそこにはせめぎ合っていた。スミス氏は、1920年代日本のモダニズムとモダニティー(近代性)に関するウィリアム・O・ガードナーの研究Advertising Towerに言及し、アナーキズムに傾倒していった萩原の政治的志向がそこに垣間見えると指摘した。
講演の後は質疑応答が続いた。一つの漢字に様々な読み方が存在する日本語の特徴やカタカナの使用は、日本の未来派の詩においてどのような機能を果たしていたのか、ファシズムの擁護に走ったイタリアの未来派と日本におけるそれとの差異は何であったのか、未来派の美学におけるミソジニー(女性嫌悪)的要素についてはどのような批評が可能であるかなど、様々な観点からの質問が次々と提出された。議論はおよそ一時間半に及び、盛況のうちに終わった。

(作成:李珠姫)
開催詳細
- 日時:2022年7月22日(金)15:00 – 17:00 (JST)
- 会場:早稲田大学戸山キャンパス 32-128教室 / Zoom Meeting
- 講師:Kevin Michael Smith (University of California, Berkeley)
- 使用言語:英語
- 参加対象:学生/教員/一般
- 参加費:無料