ミュンヘン工科大学のRubén D. Costa教授の研究室で教育研究指導を受けた渡辺 清瑚さん(博士課程2年)の体験談をご紹介します。
滞在先
ミュンヘン工科大学(Straubing Campus)(ドイツ)
滞在期間
2023.3.2~2023.3.16
滞在先の印象・日本との違い
滞在したCosta研究室は学生の主体性がとても強く、週1回のミーティング以外は、研究室への滞在時間・タスクは全ての学生が自身で管理していました。朝型の学生がかなり多く、18時を回ると帰宅する学生が多い一方で、皆オンオフがはっきりしていました。その雰囲気は研究室活動にも見られ、実験するときは集中して行い、昼食は皆で研究室のキッチンで食べたり、適宜コーヒーブレイクを取ったりと、学生の自己管理能力が高い印象を受けました。学生同士の仲も非常に良く、休憩中も雑談や研究に関する議論があちこちで飛び交っていました。先生との距離感もなく、時折一緒に食事を取っていたほか、研究の進捗報告や相談をしたければいつでも先生のもとへ出向き、アドバイスをもらえる環境でした。このように、学生や先生との連携・共有がしっかりとしているため、困ったことがあっても気軽に相談できると同時に、先生・学生ともに研究をとにかく楽しんでおり、非常に刺激的な環境でした。
実験スペース・資材・設備も申し分ないほど確保されており、必要な実験・測定のほぼすべてが研究室内で完結できるほどでした。研究室にはドイツ出身の学生はほぼおらず、他のヨーロッパ・アジア・南米の国が出身の学生が大半であり、日本人がかなりの割合を占める自身の研究室と比べてかなり国際的な環境でした。出身の違いによる文化の違いも全くなく、むしろ皆が他のメンバーの出身国に興味を持ち、雑談の中でも頻繁に話題となっていた点が印象的でした。日本の学生はとても珍しかったようで、食生活・国民性・人口密度など、研究以外にも様々な文化の違いについて話しました。学生とは実験が終わった後に飲みに駆り出したり、休日には現地の寿司屋に連れて行ってもらったりしました。
 Straubing Campusの新しい実験室棟 |
 滞在先の学生と夕食 |
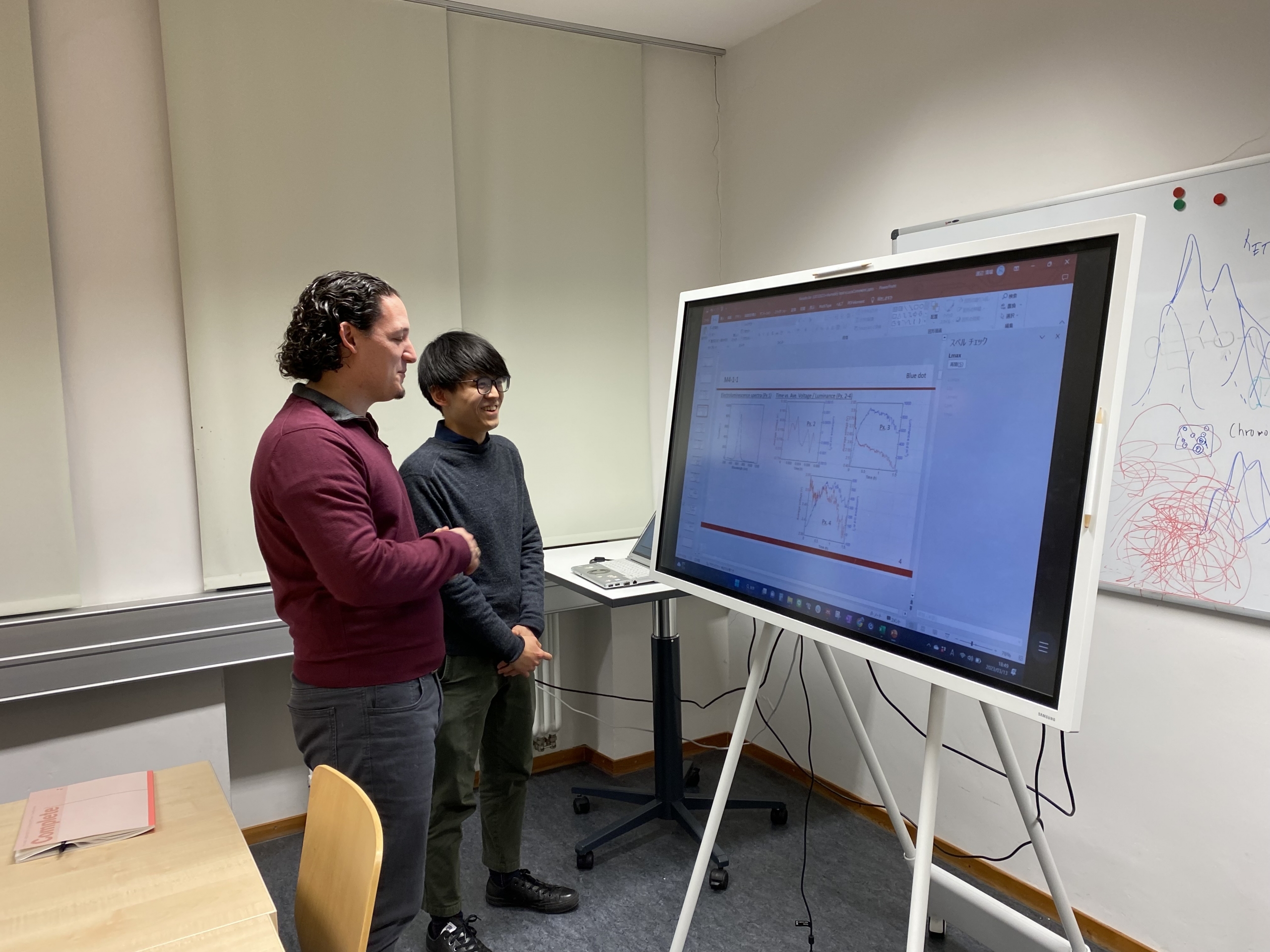
Costa教授とのディスカッションの様子
滞在先での体験談
自分は普段は高分子合成を専門としており、デバイスなどの材料応用には全く触れたことが無かったため、滞在前は現地の学生と連携して実験を進めていけるか不安でした。しかしCosta研究室の先生や学生は、新しい分野の研究者が来ることを「専門知識や技術を互いに教え、教わることのできる良い機会」と非常にポジティブに捉えており、デバイス作製から評価の仕方・解析法まで懇切丁寧に教わることができたと共に、同じ化学であっても、細かい分野の違いで重要視する実験操作・ポイントが違うことにも気づくことができ、視野を大きく広げられたと思います。英語での会話も滞在したての頃は大変でした。現地の学生同士の会話のスピードに圧倒されると共に、慣れない英語で伝えたいことを言うだけで精一杯でしたが、下手ながらもコミュニケーションを取ることを心掛けるようにしました。皆いつでも親切に話を聞いてくださり、研究以外の話題も徐々に話すようになったおかげもあって、打ち解けあうことができ、今では互いに気兼ねなく話せる、良き共同研究者になれたと思います。
滞在して良かったと思う点・今後に活かせると思う点
一番良かった点は、海外の研究室の雰囲気を生で感じ、実際に生活できたことです。国民性ゆえだと思いますが、日本人のコミュニティでは皆が遠慮しがちなので、なかなか前に出づらく萎縮しがちです。しかし、滞在先の学生は疑問に思ったことは気にせず質問・相談し、恥じらいを持つ学生などいませんでした。その雰囲気が、学生や先生との活発な議論・刺激的で居心地よい環境・良い信頼関係に繋がっていると感じました。とはいえ決して横柄というわけではなく、互いに真摯に向き合うが故の行動であり、同志として協力し助け合うスタンスを強く持っていると感じました。
また、困ったときにはとにかく動いてみよう、と確信できた点も自分にとって大きな収穫でした。様々なバックグラウンド・国籍の学生がいる中で、誰もが最初は不安な気持ちを持ちながらも、萎縮したり遠慮したりしないことが大事であり、それこそが誠意を持った行動であることを強く感じました。話したいこと・やりたいことがあれば、相手にアピールしてみる。とにかく行動に移してみる。そうすれば興味を持ち協力してくれるかもしれない。今までの自分の生活では、そういったチャンスを多く失ってきたのかもしれないと自省するとともに、より積極的に行動することの大切さを学べました。
最後に
2週間程度の短期滞在でしたが、非常に密で、貴重な経験をすることができました。慣れるまでは大変なこともありましたが、英語で連携を取りながら全く新しい分野に踏み込む経験は学びの連続でした。振り返ると、研究面・精神面ともに大きく成長できたと感じます。今までの研究経験を海外でも発揮できたこと、コミュニケーションを取りながら現地の学生と協同しプロジェクトを進められたことは大きな自信になりました。本滞在での繋がりを今後とも大事にしたいと共に、この経験を今後の研究生活にも活かしてまいります。今回の滞在を快く受け入れてくださりましたRubén D. Costa教授、指導教員の小柳津研一教授、そして手続きなどでご支援いただきましたSGUナノエネルギー拠点の皆様をはじめ、関係各位に厚く御礼申し上げます。この度は誠にありがとうございました。









