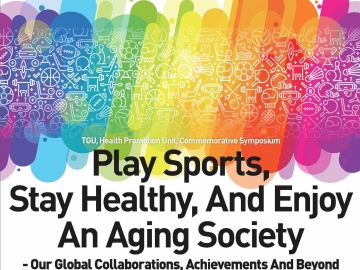運動に伴う身体的変化や生理学的メカニズムを探究する
研究成果を知的な財産として、社会に役立てていく
運動生理学を専門とする私たちの研究室では、「運動時の循環応答における神経性の調節」を大きなテーマに、人の生物的な機能や、運動によって生じる身体的変化とそのメカニズムについて研究しています。得られた結果を知的な財産、あるいは人々がおもしろいと思ってくれる知識として蓄積し、さらにはそれが社会に役立つものとなるよう発展させることを目指しています。
最近の研究例では、視力低下の原因となる眼底の血液循環について、運動中には網膜の前後で異なる血流量の変化が起きることや、楽器の演奏によって脳血流の増加・認知機能の改善が見られることなどを明らかにしてきました。また、液状の食べ物であっても、よく噛んで味わう「咀嚼」が食後のエネルギー消費量を増加させることを実証しており、今後この研究結果に基づく新たな減量方法の開発などが期待できます。
「スポーツの創造性」を科学的に解き明かす

今後に向けて、当研究室が長期的視野から取り組むのが「スポーツの創造性の研究」です。スポーツでは、見ていて鳥肌が立つほどの素晴らしいプレーが生まれる瞬間があり、その創造性に観客は心を動かされます。それがどのようなメカニズムで起きるのかを科学的な見地から解き明かしていきます。研究が進めば、将来的には創造的なプレーを実現する環境構築や、新たなトレーニング法の開発にもつながり得るでしょう。当研究室の学生の中には、すでにこうした観点から論文作成に取り組む動きもあります。
学生への指導では、学生自身の意見や考え方を尊重し、対話を重視しています。一方的に方向性を示すのではなく、対話を通して思考を整理しながら、共に良いものを生み出していくというスタンスです。また、学生が研究活動を通して、読む力、書く力、分析力など、普遍的なアカデミックスキルを高めていけるよう支援しています。修士・博士課程を修了後、研究者としてのキャリアを選ぶとしても、就職するとしても、情報を自分で得て、深く考え、発信していく力は不可欠です。
多彩な研究者が集まるスポーツ科学学術院の魅力
スポーツ科学は隣接領域が広く、医学、工学、社会学、心理学、経済学、教育学など多様な学問と深く関わり合っています。分野をまたいだ共同研究が有効なケースも多く、その意味で、自然科学・人文科学・社会科学の各研究者が在籍する早稲田大学スポーツ科学学術院の魅力は大きいと思います。
さらに、スポーツで日本一、世界一を目指す優秀な選手が多いのも早稲田大学の特長です。私自身も本学で学生時代を過ごしましたが、トップアスリートたちの活躍を目の当たりにし、大きな刺激を受けたことが、今取り組むスポーツの創造性の研究の原点になっています。
スポーツ科学学術院には海外からの留学生も多数在籍し、「これを学びたい」という強い意志で入学してくる人が多いのが素晴らしいと思います。一方で、自分の専門を超えて興味関心を広げ続けることも極めて重要です。修了時には、運動生理学の専門家であり、スポーツ科学の専門家であり、さらには科学全般の専門家を自負できるよう、幅広い視野と科学的知見を身につけてほしいと考えています。