午後1時に開始し、司会・オーガナイザーの堀内から全体のイントロダクションをおこなう。そこで読み上げられた文章から引用する。
「吉増剛造さんはみなさんよくご存じのように、1964年の第一詩集『出発』からこんにちに至るまで、常に第一線の場で、詩人として活躍されてきました。つい最近も、思潮社から詩集『VOIX』、講談社現代新書から『詩とは何か』を上梓されたばかりです。また昨年までYouTube上で週一回映像作品をアップされていらしたことも記憶に新しいところです。ご縁があって、岩手県石巻市鮎川地区に通われて、金華山を窓から望む部屋から、あたらしい創作を続けておられます。本日は、また新たなテキストを書いてきてくださいました。いつも読者を置いてけぼりにして、周囲の予測をはみ出して、誰よりも予測のつかないところで、ひょっとしたらご自身も予測できないところに自身を追い込んで、創作されている吉増剛造という詩人と同時代を生きることができる幸運を感じています。
「さて、今日のシンポジウムの主題、その一つは、世界文学の中の吉増剛造、ということになっています。吉増剛造さんの詩集はアメリカ、ブラジル、フランスなど、世界各国で翻訳されており、また吉増さんご自身も、他にもアイルランド、スコットランド、ドイツ、インド、シリアまで、世界中から招聘されています。またそのテキストには、英語のみならず、ハングル、パーリ語、フランス語その他、複数の言語が絶えず入り込んで、日本語の固定化した言語の秩序を乱し、誰も読んだことも聞いたこともない言葉の世界が実現しています。世界文学としての吉増剛造というとき、少なくとも日本という一国中心のものではない受容や創作が含意されているとは言えるでしょう。
「同時に、このいわば脱中心化の詩作の運動は、吉増剛造において脱東京という意味合いも持っています。沖縄、奄美から、青森、北海道まで、日本列島を縦横に移動する詩人の軌跡は、その詩集のいたるところに現れています。それもまた、実は「世界」ということを考えるとき、日本人の詩人が、常に日本の中で多様な複数の文化圏を横断し、日本国という一国中心主義的な視点を相対化する営みだと言えるでしょう。この点で、3・11の東日本大震災の衝撃を深く刻んで、東北に思いを致す近年の詩作はきわめてアクチュアルな意味を孕んでいます。詩人・和合亮一さんにスピーカーとしてご参加いただくのも、吉増さんの現在を深く照らし出す大切なことであると感じています。」
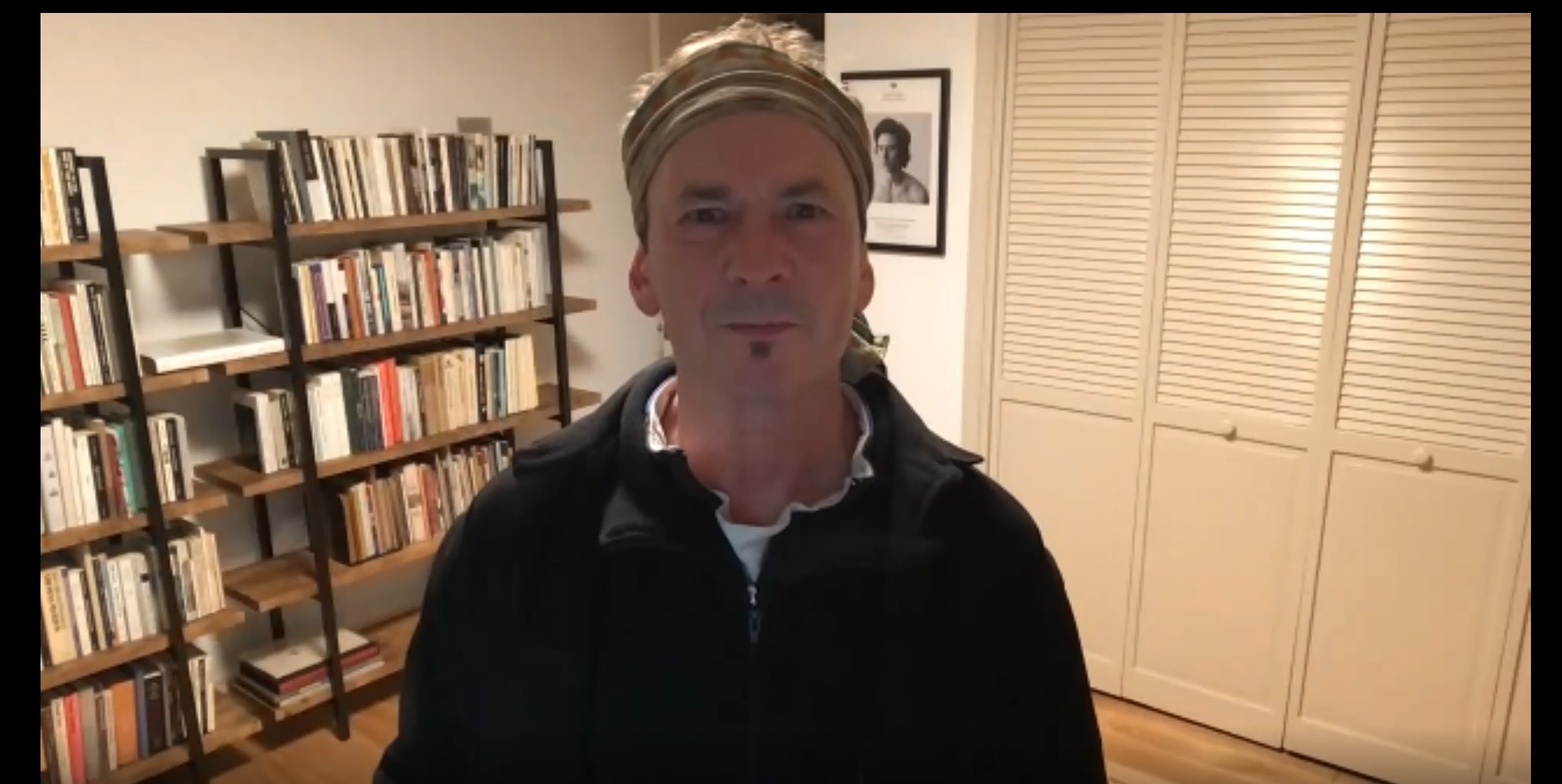
引き続き第一部、Forrest Gander氏の講演に移る。コロナウィルス感染状況のため、カリフォルニアの自宅からZoomでの参加となった。「Letter to Gozo from CA」と題し、書き上げたテキストを読み上げ、セクションの切れ目毎に、事前に翻訳していたものを堀内が交互に読み上げた。翻訳の全文は「現代詩手帖」2022年3月号に掲載される。Forrest Ganderは一九五六年生まれのアメリカの詩人、二〇一九年に詩集『ともに』Be Withによってピュリッツァー賞を詩部門で受賞した。詩集に『科学と尖塔状の花』Science and Steepleflower(一九九八)、『めざめたまま引き裂かれ』Torn Awake(二〇〇一)、『目に目を』Eye Against Eye(二〇〇五)、『世界のコア・サンプル』Core Sample from the World(二〇一一)、『Eiko & Koma』(二〇一三、邦訳版二〇一九、Awai Books)などがあり、最新詩集は『二度目の生』Twice Alive(二〇二一)。小説作品として『痕跡』The Trace(二〇一四)などがある。スペイン語の詩の翻訳の他に、他言語の協力者と合同でなされた多数の翻訳の仕事があり、吉増剛造の英訳詩集Alice Iris Red Horse: Selected Poems of Gozo Yoshimasuの編訳者である。
テキストの朗読はエネルギッシュと言えるほど力のこもったものだった。これまでにGander氏がさまざまな国で吉増剛造と一緒に過ごした経験の記憶が詩的な表現とともに描き出され、とりわけ最後では、吉増のパフォーマンスの本質が、自らにあえて拘束・不自由を課すことによって、自分のエゴや自意識のコントロールから抜け出て、限界を超えた表現になるという視点が提出されている。その後質疑応答になり、日本語から英語への通訳をJordan Yamaji Smith氏が、また英語から日本語への通訳を、このイベントの後援をしている立命館大学言語文化研究所の吉田恭子氏がつとめてくれた。このテキストがエズラ・パウンドの中国詩の翻訳詩集Cathayに収められている有名な李白Li Poの詩“Exile’s Letter”を意識して書かれたこと、また翻訳者として吉増剛造の詩をどう思うかについて、またZoomでの視聴者から「手紙」としてのテキストの性質が吉増剛造の言葉にも共通することなどが語られた。最後の吉増剛造氏にも登壇をしていただき、Ganderの講演内容についての感想を熱く語った。
引き続き第二部のシンポジウムが始まった。この模様は「現代詩手帖」2022年3月号に採録されるので参照していただきたい。4人のお話に先立ち、司会役の堀内から、大雑把なパースペクティヴの提示として短い話があった。この内容は、更に敷衍した形で「現代詩手帖」同号に掲載される予定である。
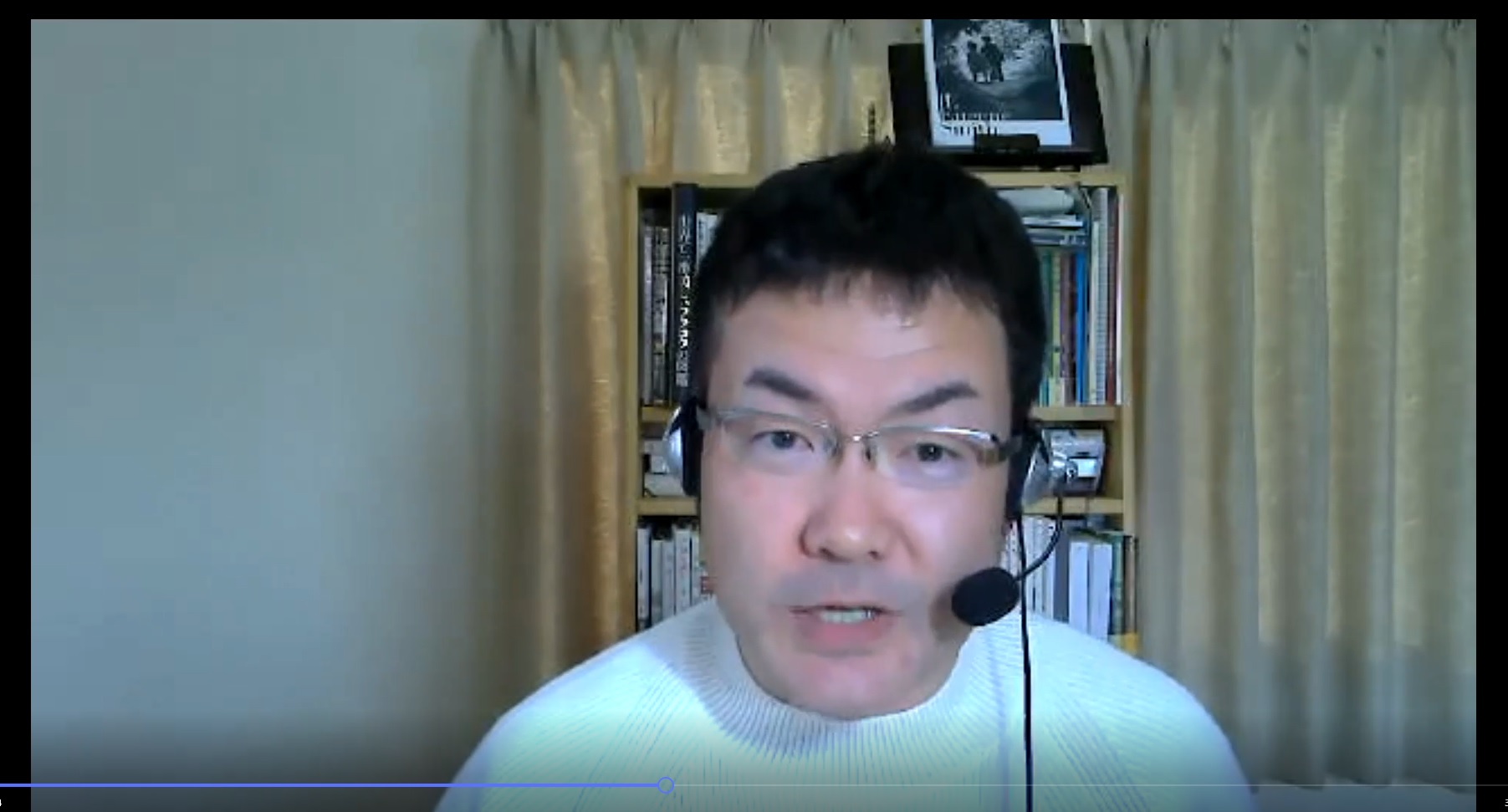 まず詩人・和合亮一氏のお話。和合氏は福島在住で、事情があり東京に来ることが叶わなかったため、Zoomでの参加となった。現在、「現代詩手帖」と「河北新報」において吉増剛造氏との連続対談をしていること、そこでの吉増氏の様子、先輩詩人としての吉増剛造をどう思っているか、吉増の「詩とは細い道」だという言葉に触れて、吉増詩には「フィボナッチ数列」に喩えることができるような増殖のあり方が見出されること、それが「異界」への入口になっていて、若い頃に観ていた唐十郎のテント公演に似ていることが語られた。東日本大震災、コロナ禍の状況を経て、「日常」の反対は「死」であるという思いをし、吉増の詩の深みが日常の反対にある「黒い色」、「宇宙の別の層」に触れていると語られた。細い道は震災の津波から逃げるための道とも重なる。詩において「細い道」ににじり寄る感覚が吉増の詩にはあり、それは夏目漱石が芥川龍之介にアドバイスをした言葉「超然として押して行く」を想起させることなどが生き生きした口調で語られた。
まず詩人・和合亮一氏のお話。和合氏は福島在住で、事情があり東京に来ることが叶わなかったため、Zoomでの参加となった。現在、「現代詩手帖」と「河北新報」において吉増剛造氏との連続対談をしていること、そこでの吉増氏の様子、先輩詩人としての吉増剛造をどう思っているか、吉増の「詩とは細い道」だという言葉に触れて、吉増詩には「フィボナッチ数列」に喩えることができるような増殖のあり方が見出されること、それが「異界」への入口になっていて、若い頃に観ていた唐十郎のテント公演に似ていることが語られた。東日本大震災、コロナ禍の状況を経て、「日常」の反対は「死」であるという思いをし、吉増の詩の深みが日常の反対にある「黒い色」、「宇宙の別の層」に触れていると語られた。細い道は震災の津波から逃げるための道とも重なる。詩において「細い道」ににじり寄る感覚が吉増の詩にはあり、それは夏目漱石が芥川龍之介にアドバイスをした言葉「超然として押して行く」を想起させることなどが生き生きした口調で語られた。
次にJordan Yamaji Smith氏が発表をした。彼もまたGanderとともに吉増の英訳詩集を翻訳した一人である。吉増の詩の翻訳行為はGanderのリードもあり、相当に自由でクリエイティヴな遊びを許されたこと、多言語的な層がいくつも重なっている彼の詩がいかに翻訳困難なものであるかなどを語ったあと、今日のために作られた自身の映像作品が投影された。吉増の詩にインスパイアされて、英語と日本語とを自在に往還するような言葉遊びを含む独特のプレゼンテーションが披露された。それは吉増剛造の詩がどのような影響や作用を及ぼすかを、自身の身をもって提示した時間であったと言える。
続いて、郷原佳以氏の発表に移った。最新詩集『VOIX』の「v」の音の発生への着目から始まり、それが多言語的にどんな連想を誘うかが語られた。日本語で書かれていても、吉増の詩はすでにそこに外国語の語源を含むような飛躍のある奥行きを持っている。日頃われわれが生活している場では、一瞬一瞬が多重化されて分裂するような「吉増剛造的なもの」は忘れてられているし、それを意識したら日常生活は立ち行かなくなるだろう。近年の詩集『怪物君』や『VOIX』を例にとりながら、現代思想を視野に収めた密度の濃い思考が展開された。後半はフロイトの「マジック・メモ」のあり方と吉増のテキスト生成のすがたとの共通性が指摘された。稠密な発表であったため、大雑把な要約は難しく、関心のある方はぜひ「現代詩手帖」2022年3月号の採録をお読みいただきたい。
次に小野正嗣氏の発表に移った。小野氏がフランス留学中、オルレアンに住んでいたクロード・ムシャール教授に出会い、その「歓待」に触れて彼の家に住むに至ったこと、そこでムシャール氏が吉増剛造の詩のフランス語訳に携わったことから、自身と吉増氏との関係が始まったこと、ムシャール宅で吉増氏とパートナーのマリリア氏と出会ったことなどが語られて、そこから吉増剛造独特のふるまい方についての見かたが示された。またムシャール氏と共同で吉増の作品「古代天文台」を翻訳した経験についての話になった。朗読を聞いて、同じ言葉の繰り返しでも、途中からいかにトーンが変わるか、パフォーマンスにおいて吉増の身体を通じて伝わるものがあり、それが翻訳に役立った。吉増は常に「誰かとともにいる」人であるような印象があり、それはあたかも「分子」状になっていつも何かをつかまえて結びつく、響いている言語やそこにある無意識までキャッチしてしまうような性質、「不思議な分子構造」を持った詩人だと思った。そこから多言語的に書くという問題にもつながるという指摘がなされた。

シンポジウムは残り30分となり、Zoom参加の聴衆からの言葉をはさんで、登壇者同士のやりとりとなった。和合氏は用意していたが時間に収まらなかった話をし、生物学的な現象である「共進化」ということが吉増剛造にある問題とつながるという指摘がなされた。共進化とは、一つの生物学的要因の変化が引き金となって別のそれに関連する生物学的要因が変化することである。たとえば花のサインを受けとるハチとハチの身振りのサインを受けとる花との関係において行動・形態の進化が生じる。そのような隣り合うものとの共進化を、詩人吉増剛造はしている。「サインの交響楽」すなわち詩人と「太陽や大地」のパートナーシップ」があり、「共進化する詩の風景」は「宇宙/日常の時空間で深く覚醒していく感覚へ」とつながっていくと言う。小野氏からはフランス語で詩の翻訳をするときには一語一語の意味を確定してあまり訳者の自由は認められないが、英語の翻訳ではなぜ訳者の創造性が働く余地があるのかという質問があり、Smith氏からは、吉増剛造のテキストならではの多層性と編者Ganderの姿勢がそれを可能にした事情を語った。ここでやはり吉増の英訳詩集の翻訳者としてGanderと共同して詩を訳した吉田恭子氏にも登壇を願い、更に翻訳作業についての補足をしてもらった。吉田氏は現在、立命館大学で海外の中堅・若手の詩人を京都に1か月程度滞在してもらう「レジデンシャル」という制度を作ろうとしており、その話も交えて、国際創作科が詩人にとって重要なものであることを、自身のアイオワ大学での経験から語った。吉増剛造は1970年、アイオワ大学の国際創作科に在籍しているが、そのときの経験がいかに彼の詩業において重要であるかについて、司会からの指摘があり、この部の終了時間になった。
第三部で吉増剛造氏が登壇した。当日のためにB4の原稿用紙一枚にびっしり手書きされたテキストが読み上げられた。吉増氏はこの日に合わせて、他に当日の真夜中に新たに詩を書き下ろし、原稿用紙3枚のその詩の原稿は、上記のテキストとともに、来場者にはカラーコピーで配布され、Zoom参加者には写真版がダウンロードされるように配信された。テキストと詩は要約不可能なものであり、かいつまんで語ることはかえって詩人の表現を貶める結果になりかねない。「現代詩手帖」2022年3月号に掲載される予定なので、参照していただきたい。手書き散文テキストの読み上げは、いつもの吉増氏の講演と同じく、一文ごとにその場で吉増自身によってコメントされ、読み上げと即興の話とが入り混じる時間となった。その後、ステージ上に置かれた原稿(デリダの書物を筆写したもの)を消す、というパフォーマンスがなされて、白いインクと緑のインクが原稿の上に零され垂らされた。その後吉増氏はできたての詩作品の朗読に入った。
「世界文学」という視点からオーガナイザーが感じた本シンポジウムの意義は、まず翻訳という視点を吉増剛造論の核心に据えた点であろう。多言語とのネットワークの中で今後さらに吉増剛造の詩が読まれていく、その希望が感じられた。アメリカの詩人Forrest Ganderは、彼自身の詩が世界各国で翻訳がなされ、各国から招聘される詩人であり、そうしたひとが吉増剛造をいかに敬愛し、尊重しているかを、具体的かつ親密な交流を通して示すことができたのも、意義深いことだった。その友情のスピリットが当日全体のトーンを決定したと言っても過言ではない。また東日本大震災後、広い範囲で読者を獲得している詩人、和合亮一氏に、東北の被災地への吉増の関わりに触れて詩人の特徴を論じてもらえたことも意義深かった。和合氏もまた世界各国で翻訳が出続けている詩人であり、Gander氏らとも交流があり、友情のネットワークとでも言うべきものが感じられた。発表者の姿勢や論点はそれぞれだったが、不思議にも(或いは当然なのかもしれないが)重なり合うところが多かったのも興味深いことだった。思潮社との共催で、企画段階から「現代詩手帖」編集長高木真史氏と相談し合って作ってきたイベントだったが、当初の企画どおり、主要な部分が「現代詩手帖」に掲載されることで、今後も研究者たちによって参照され続ける資料になるだろう。コロナ感染状況が悪化していくさなかの開催であったが、なんとか現実化できたことの幸運を感じている。
(堀内正規・記)

開催概要
- 日時:2022年1月22日(土)13:00~18:45
- 開催方式:オンライン(Zoom)と対面(早稲田大学小野記念講堂 ※早稲田大学学内関係者のみ)
- 講師:吉増剛造氏(詩人)、Forrest Gander氏(詩人)、和合亮一氏(詩人)、Jordan Smith氏(城西国際大学准教授)、郷原佳以氏(東京大学准教授)、小野正嗣氏(早稲田大学文学学術院教授)
- 司会・オーガナイザー:堀内正規氏(早稲田大学文学学術院教授)
- 使用言語:日本語・英語
- 参加:学生・教員・一般









