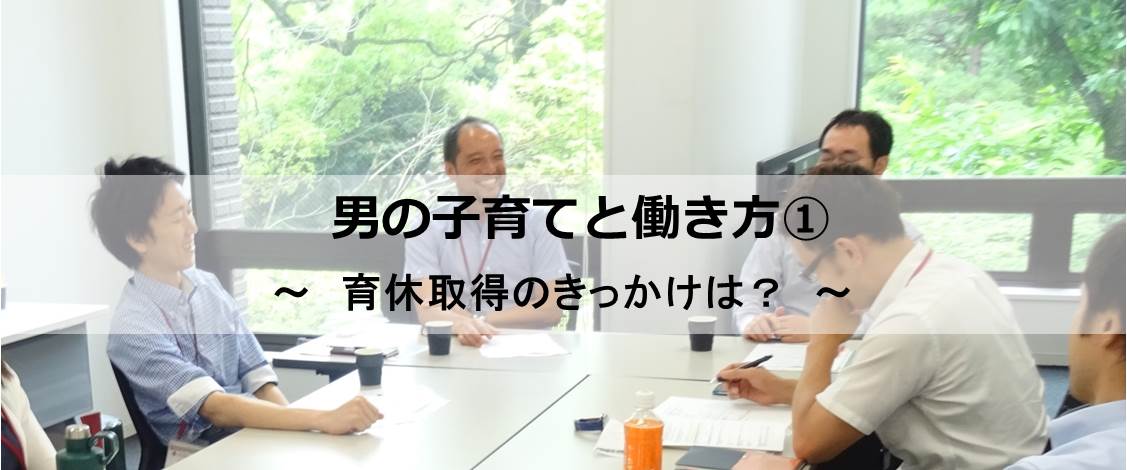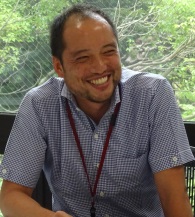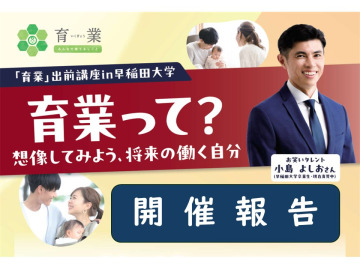座談会について
早稲田大学ダイバーシティ推進室では、男女共同参画の推進として、男女を問わず、積極的に育児休業を取得できるよう支援しています。
「産前産後休業(産休)」と「育児休業(育休)」を混同されている男性の方も少なくないと思いますが、「育休」は男性も取得できるものです。しかし、まだまだ女性と比べ、男性の育休取得者は少ないのが現状です。
そこで今回は、本学で育休取得の経験のある男性職員4名に集まってもらい、育休を取得しようと思ったきっかけや休職中のエピソードなど語っていただきました。
※全3回シリーズです。
出席者紹介
育児休業のきっかけ
T:この座談会では、育休取得の動機、育休を取得するのに大変だったこと、メリットデメリット、働き方や家事育児への変化についてお聞きしたいと思います。まずは、なぜ育休を取得しようと思ったのかについて、家庭の状況含め、お話しいただけますか。
 Y:2人目の時に取得しました。2人目となると子育ても難しいし、妻の産後の体調の不安もありました。また、両祖父母は遠方に住んでいたり働いていたりするためサポートが得られず、妻がひとりでやらざるを得ない状況が見えていました。自分自身も社会人になって1か月以上の長期休暇を取る機会は、今後定年までないだろうと考え、この機会に取得しようと思ったのが理由です。また、定期的に業務分担を変更し、担当不在時に対応ができるよう普段から調整がされている職場環境でしたので、取得しない理由はないと思いました。
Y:2人目の時に取得しました。2人目となると子育ても難しいし、妻の産後の体調の不安もありました。また、両祖父母は遠方に住んでいたり働いていたりするためサポートが得られず、妻がひとりでやらざるを得ない状況が見えていました。自分自身も社会人になって1か月以上の長期休暇を取る機会は、今後定年までないだろうと考え、この機会に取得しようと思ったのが理由です。また、定期的に業務分担を変更し、担当不在時に対応ができるよう普段から調整がされている職場環境でしたので、取得しない理由はないと思いました。
K:2人目の時に取得しました。父親と過ごす時間が少ない家庭で育ったので、子供と一緒にいる時間を取りたいと思い、1人目誕生後から、保育園の迎えのために定時の17時15分でダッシュみたいな生活をしていました。 入職5年目で多忙でしたが、仕事の優先順位の付け方もわかってきていたので。第2子の出産予定日は繁忙期(4月上旬)でしたが、第1子がまだ一歳児で4月はならし保育期間で短時間しか保育園に預けられないため手がかかるし、親に頼むこともできないのでせめて1週間だけでも、と取得しました。当時、男性の育休取得を推進していることや取得者があまりいないことを聞いていたので、少しでも大学に貢献できればという思いもありました。
入職5年目で多忙でしたが、仕事の優先順位の付け方もわかってきていたので。第2子の出産予定日は繁忙期(4月上旬)でしたが、第1子がまだ一歳児で4月はならし保育期間で短時間しか保育園に預けられないため手がかかるし、親に頼むこともできないのでせめて1週間だけでも、と取得しました。当時、男性の育休取得を推進していることや取得者があまりいないことを聞いていたので、少しでも大学に貢献できればという思いもありました。
N:2人目で取得しました。妻は専業主婦ですが育児が大変そうだったので、負担軽減になればと思いました。この先、長期で休むことはないだろうと思ったのも理由の一つです。
また、担当が自分だけである業務があったので育休取得をきっかけに、他のメンバーと共有したいという戦略もありました。
T:育休などの機会があると、自動的に引き継ぎが生じますよね。部署によっては業務が人に張り付いていることがあるようですが、こういった機会によって業務に流動性が生まれるわけですね。
N:実際に、育休取得後は、担当が自分だけである業務がほぼなくなり、担当のどちらかがいればよいという状態が実現しました。
※座談会②へ続きます。
※記事の内容は座談会当時(2017年6月)のものです。
記事一覧