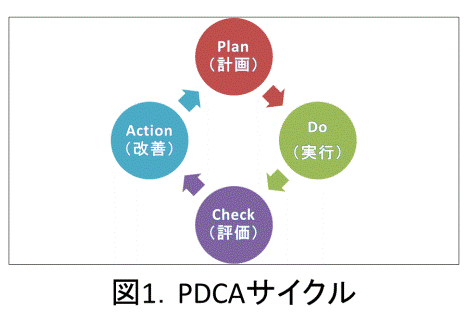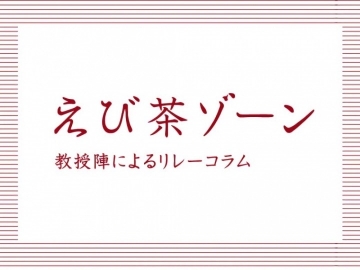アスリートの目標の設定とその達成の方策
2020年東京オリンピック・パラリンピック開催が決定し、スポーツ政策の司令塔としての機能を果たすべく「スポーツ庁」の新設を盛り込んだ改正文部科学省設置法が成立しました。国民のスポーツへの興味や期待がますます高くなり、とりわけ競技スポーツへの関心が高まる中で、世界で活躍することを夢みる、次世代を担うアスリート達が誕生してくることでしょう。競技スポーツを始めたばかりのアスリートが世界で活躍するためには、様々な課題を段階的に解決する過程が必須です。しかしながら、成熟していないアスリートには、課題を解決するための考え方が定着していないのもまた事実であることは否めません。
本稿では、クロスカントリースキー選手、コーチと研究者という立場で研究や指導を行ってきた筆者の立場から、アスリートがすべき目標の設定とその達成の方策について述べてみたいと思います。また本稿で扱うテーマは、アスリート以外の方々にも当てはまるものですので、ぜひご自身の立場でご一読いただければ幸いです。
段階的目標設定
競技スポーツのアスリートの主な目的は、競技力を向上させて各自が設定した目標を達成することにあります。そのためには、最終的な目標を掲げ、それを達成するために段階的・漸進的に下位目標をおき、それらを達成しながら最終目標に行きつくように『段階的目標設定』をする必要があります。例えば、2020年の東京オリンピックにおけるメダルの獲得を目標とするなら、オリンピック代表への選考基準をクリアすることや、オリンピック前の世界大会でのメダル獲得や世界ランキング上位に位置することが下位目標となるでしょう。さらに、これらの下位目標を達成するために必要と思われる下位目標(例:ユース、ジュニア世界大会でのメダル獲得、日本一獲得など)を設定します。そのうえで、それぞれの目標を達成するための具体的な方法(体力の向上、技術の習得、戦術・戦略の検討など)をあらゆる角度から検討することが不可欠となります。これらを総括して現在から最終目標の達成までの明確なビジョンをもつことがとても重要となります。
目標の設定と達成のための『SMART』
目標の設定のために必要な5つの条件は、その頭文字をとって『SMART』と呼ばれています。これらの条件は、分野や対象によって多少異なっているようですが、ここでは筆者が大学院の研究室で学んだ5つの条件を示しました。
- Specific ― 目標が具体的であること
- Measurable ― 目標が測定可能であること
- Achievable ― 目標が達成可能であること
- Result-based ― 結果(成果)に基づくこと
- Time-bound ― 目標達成までの期限が決まっていること
筆者は、自身がコーチングを行っているアスリートに対して、例年シーズンオフに前シーズンの目標とそれに対する達成度に対する自己評価と次シーズンの目標設定を実施させていますが、中には高すぎる目標を設定するアスリートや、トレーニング自体が目標となってしまっている(トレーニングは目標達成の一手段に過ぎません)アスリートが散見されます。また筆者の個人的な感想ですが、これらのアスリートは前シーズンの目標に対する達成度が比較的低いことが多く、前述の段階目標設定やSMARTに則った目標設定ができていないことが多いように思われます。本稿を読んでいるアスリートの皆さんには、現在の目標が上記の条件と合致しているかを冷静な目で確認してもらいたいと思います。
PDCAサイクル
段階的目標設定やSMARTに則った目標設定は、アスリートの目標達成をより現実的なものにするでしょう。しかしながら、目標を達成するための方策が間違っている場合や、その到達度が不十分な場合には、目標の達成は不可能となる確率が高くなるでしょう。それらを検討し、目標の設定と達成をするための一連のサイクルは『PDCAサイクル』と呼ばれています(図1)。これは、 Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の4つの段階を明確にして方策や到達度を検討することによって、目標達成までの過程を考察して、目標達成までの行程をよりよく循環させるものです。このPDCAサイクルにおいてDo(実行)は目標となる競技会や、その前に行われる競技会を対象とするのが一般的です。しかしながら競技会での競技成績は、選手の競技力に競技場での心理的状態や競技場の物理的環境が関与して決定される(宮下、1978)ものであり、本来の競技力をCheck(評価)するには不十分な面もあります。そこで次節では、選手の競技力をCheck(評価)するための体力や技術の測定の重要性について紹介したいと思います。
競技力の評価
体力や技術の測定によって競技力を評価するためには、その競技成績と関連の深い要素を評価する必要があります。クロスカントリースキー競技の場合には、競技成績と関連の深い体力要素として持久力の指標である最大酸素摂取量が挙げられます。先行研究では、世界大会における男子の優勝者の最大酸素摂取量は、体重あたり85.1ml/分であるとの報告(Tonnessen et al, 2014)があります(成人一般男性の最大酸素摂取量は約40 ml/分です)。一方、日本代表選手では73.5ml/分、ジュニア選手では70.5ml/分であるとの報告(藤田、2014)があります。競技成績と関連の深いこれらの値は、その選手の持久力を世界や日本代表と比較するために有効な指標となるといえるでしょう。また、ジュニア期から段階的に持久力を向上させる必要があること、世界で日本人選手が活躍するためには持久力をさらに高める必要があることを示した結果といえます。現在、公益財団法人全日本スキー連盟では、春と秋に計2回の最大酸素摂取量を含む各種体力測定を行って競技力やトレーニングの到達度を評価し、冬季に行われる競技会で競技成績を評価しています。
高い目標をもつアスリートは、自身の競技スポーツに関連する要素を測定することで、自身の能力を客観的に評価できる自己分析能力の高いアスリートとなり、競技力向上に役立ててほしいと思います。また大学や研究機関が、多くのアスリートの能力の評価をサポートする役割を担っていくことが、スポーツ立国戦略を目指す日本にとって重要となるでしょう。
参考文献
宮下、 (1978) スポーツの記録が生み出される背景。
Tonnessen, et. al. (2014) The Road to Gold: Training and Peaking Characteristics in the Year Prior to a Gold Medal Endurance Performance.
藤田、(2014)クロスカントリースキー競技の体力評価
執筆者プロフィール
 藤田善也/早稲田大学スポーツ科学学術院講師
藤田善也/早稲田大学スポーツ科学学術院講師
学歴;2007年3月早稲田大学スポーツ科学部卒業。2009年早稲田大学大学院スポーツ科学研究科修士課程修了。2012年早稲田大学大学院スポーツ科学研究科博士後期課程修了。2012年-2015年、国立スポーツ科学センタースポーツ科学研究部契約研究員として従事。2015年4月より早稲田大学スポーツ科学学術院講師。 2014年より公益財団法人全日本スキー連盟クロスカントリー部強化委員を務める