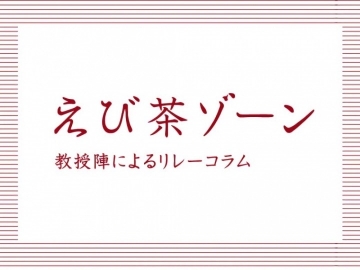障がいを有した方のスポーツの現状と課題
「65%」というこの数字は何を表しているのでしょうか。
この65%という数字は、私達の調査において、障がい者の方が行うスポーツに対する興味や関わりの程度について質問をした結果、「興味がない」「関わりがない」と回答された割合です1。このように、一般の方の障がいを有した方のスポーツに対する関心はまだまだ低い傾向にあります。一方で、障がいを有した方が運動やスポーツを行うことの必要性について尋ねた結果、約90%の方が「そう思う」とポジティブな回答をされました。しかし、文部科学省「体力・スポーツに関する世論調査」(2013)2によれば、障がいを有した方のスポーツ・レクリエーションの実施率は週3日以上が8.9%、週1-2日以上9.7%と報告されています。このように障がいを有する方のスポーツ活動の参加や実施率の低さは、障がいに対する理解面、情報環境の未整備、施設の不足、疾患や障がいを有した方向けのガイドラインが存在しない他、指導者・ボランティアの不足など様々な要因が複雑に絡み合っているといえます。
障がいを有した方への身体活動推進に向けた環境整備の取組みと期待される効果
疾患や障がいを有する方においても適切な身体活動(身体活動:生活活動、運動・スポーツを含む)を行うことの直接的な効果として、心身機能の向上、疾患憎悪の防止、廃用や生活習慣病の予防、医療・介護費の削減、自立活動の促進、社会参加の機会の創出など様々な良い効果があると考えられています。更に、私達が推進していく下記の取組みにより、共生社会の促進、地域コミュニティの活性化、誰もが住みやすい環境づくりと社会的にも価値のある形につなげていく必要があると考えています。
障がい者スポーツを通した交流
障がい者スポーツの多くは障がいの有無や世代などに関わらず取り組むことが可能です(近年では、関連した用語としてインクルーシブスポーツ、アダプテッドスポーツという言葉があります)。そのため、障がい者スポーツを通した交流(写真1,早稲田アスリートプログラムのボランティア・地域貢献活動プログラムもご参照下さい3)を図ることで、障がいの理解や共生社会の促進、地域コミュニティの活性化につながる事が期待できます。また、こうした交流をきっかけとし、ボランティアやスタッフとしての参加人口の増大を見込める他、昨年度にはスポーツ科学部の学生が所沢市内にある国立障害者リハビリテーションセンター学院の学生や中高生とチームを組み、視覚障がい者のスポーツの1つであるゴールボールの日本選手権の予選会に出場をしました4(写真2)。このように積極的に競技にも参加をしてもらうことで障がいを有しない方にとってもスポーツや健康づくりとしての幅が広がるだけでなく、競技人口の増大や競技力の向上にもつながるのではないかと考えています。
ガイドラインの作成や専門的な指導者の育成
「どれくらい体を動かしてよいのか」、「自分にあった(出来る)スポーツは何か」といったように、特に疾患や障がいを有する方にとってはリスクに配慮した形で、かつ効果のある運動やトレーニングを含めた身体活動を行う必要があります。そのためには、安全で適切な身体活動が可能なようにアセスメントやトレーニングのための基礎研究5,6など科学的根拠に基づく形で研究を推進しガイドラインを確立していく必要があります。更に、こうした専門的知識をもつ指導者やスタッフの育成を図ることも重要であると考えています。昨年度から、日本パラリンピック協会が医・科学・情報サポート推進事業として開始をした競技団体の選手のフィットネスチェックに本学部の大学院生や学部生も学生アシスタントとして参加をさせて頂くなど、こうした専門的スタッフの育成には、学問としての勉学に加え、早期からの現場との関わりの機会があることも良い経験につながっていくのではないかと考えています。
障がい者スポーツに関わるスポーツ用具や用品の開発
特に、障がいを有した方のスポーツに関わる用具や用品については、競技人口の少なさからニーズが少ないために開発が遅れ、競技者にとっては自分に適した機能や好みにあった用具や用品などが選べる環境ではなく選択幅が少ないのが現状です。1例としてアイシェード(写真3)は、私が共同研究者として携わっている国立障害者リハビリテーションセンターとの研究7で開発されたものです。アイシェードは主に視覚障がい者用のスポーツで使用され、レンズを黒く覆うことで眼からの情報を一切遮断するために使用をします。この開発に至っては機能性に加え、デザイン性も重視し、レンズの縁取りやベルトのデザインも数種類を用意することで、選手の好みに合わせて選択が出来るようにしています。こうしたスポーツに関わる用具や用品の機能性は直接的にパフォーマンスに関わるため開発は急務ではある他、見て楽しめるスポーツとしての見た目のカッコ良さ・おしゃれさも重要であると考えています。
情報環境整備やPathways Modelの確立
疾患や障がいを有した方がスポーツに興味や取り組みたい意思があっても、「いつ」「どこで」「何が出来るのか」といった情報収集が容易にできる環境ではなく、それがスポーツ参加人口の低さにつながっている1要因ともいえます。そのためには、情報の一元化を図り、障がいを有した方でも容易に情報を取得が出来るような情報環境や相談窓口の整備を促進していく必要があります。また、海外では病院・学校・スポーツ団体が連携をし、疾患や障がいを有した方のスポーツ推進のためのPathways Model(経路やシステム作り)が構築されるなど、地域にある学校やスポーツ施設などの公共機関で障がいを有した方でもスポーツが行えるような環境整備がされ(写真4)、誰でも使いやすく気軽にスポーツが楽しめるような地域に根付いた形での活動が展開をされています。私達は、日本でのこうした環境作りの重要拠点の1つとして考えている特別支援学校にもご協力を頂きながら、学校を通じた情報環境の整備、障がいを有する児童・生徒への身体活動増進に向けた教育プログラムの構築、病院内にある院内学級からの取り組み、一般校との連携(インクルーシブ教育)、学校開放を利用しての卒業生や一般の方などを対象とした運動・スポーツ指導といった形で着手をし始めました。このように、誰もが自分の地域で生涯に渡ってスポーツといった身体活動を楽しむ事ができるような環境作りの働きかけを行うことが重要であると考えています。
障がいを超えた生涯のスポーツとしての可能性とは?
疾患や障がいを有することや、年を取っていく中で出来ることや楽しみの機会が減ってしまうのではなく、このようなスポーツの在り方や環境整備により、いつまでも新たな事に挑戦をする機会ややりたい事を選べる選択の幅を作ることで生涯を通した高い身体活動を維持する環境づくりにつながると考えています。また、こうした取組みは疾患や障がいを有した方のための特別なものではなく、幅広い世代、運動・スポーツに苦手意識を感じている方や様々な身体機能のレベルの方などにも向けた身体活動増進のシステム作りとなり、ひいては地域や社会全体の活性化、2020年に行われるオリンピック・パラリンピックやまたその先の将来にもつながる環境作りが出来るのではないかと考えています。
参考・関連文献
- 塩田琴美(研究代表者):「障害者(児)の運動・スポーツ活動促進のための規定要因の解明」,2014年度早稲田大学スポーツ科学研究推進費成果報告書,2015年4月
- 文部科学省「体力・スポーツに関する世論調査」(2013):笹川スポーツ財団,「健常者と障害者のレクリエーション活動連携推進事業(地域における障害者のスポーツ・レクリエーションの活動における調査研究)」報告書,2014年3月
- 早稲田アスリートプログラム(WAP)のボランティア・地域貢献活動プログラム(http://waseda-sports.jp/news/43638/ ,http://waseda-sports.jp/news/38871/ ,http://waseda-sports.jp/news/44489/)
- 古瀬友香、徳井亜加根、梅崎多美、塩田琴美:「晴眼者がブラインドスポーツに参加する要件と効果-ゴールボール晴眼者チームを結成して-」,第35回医療体育研究会、第18回アダプテッド体育・スポーツ学会(第16回合同大会)抄録, p33, 2014年12月
- 塩田琴美(研究代表者):「ブラインドアスリートの聴覚空間認知と身体運動の解明」,ミズノスポーツ財団研究助成報告書,2015年4月
- 塩田琴美(研究代表者):「The Influence of a Physical Exercise during Hemodialysis in Improving Body Function: Effects of low and medium intensity intradialytic resistance training in elderly chronic hemodialysis patients as a preliminary report」,2011年度スポーツ科学研究推進費成果報告書,2012年6月
- 日本障がい者スポーツ協会発行,No Limit, COLOMN 01「現在、開発中! 新型アイシェードが完成間近」,2014年9月(Vol.59)
執筆者プロフィール
博士(保健科学)、理学療法士
学歴:東京都立保健科学大学保健科学部理学療法学科卒業、東京都立保健科学大学保健科学研究科修了、首都大学東京大学院保健科学研究科修了(博士号取得)。
職歴: 都内病院のリハビリテーション科に勤務、その後了徳寺大学健康科学部理学療法学科助手・助教を経て、2011年より早稲田大学スポーツ科学学術院講師として着任