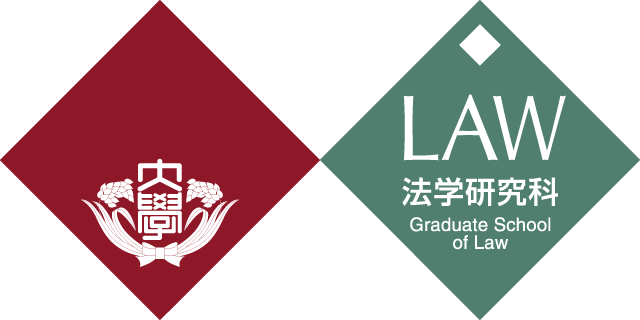- ニュース
- vol.01 新しい学び、新しいロースクール作りに挑む
vol.01 新しい学び、新しいロースクール作りに挑む

- Posted
- 2014年5月23日(金)
新しい学び、新しいロースクール作りに挑む
川岸 令和教授
(早稲田大学大学院法務研究科 担当科目:「人権論」「国家と法」「憲法総合」)
- 1986年
- 司法試験合格
- 1987年
- 早稲田大学政治経済学部を卒業後、早稲田大学大学院政治学研究科に進学
- 1989年
- 早稲田大学政治経済学部助手
- 1992年
- フルブライト奨学生としてイェール大学ロースクールに留学(93年LL.M.取得)
- 1995年
- 帰国後、早稲田大学政治経済学部専任講師
- 1997年
- 早稲田大学政治経済学部助教授
- 2002年
- 早稲田大学政治経済学部教授
- 2004年
- イェール大学ロースクールにてJ.S.D.を取得
- 同年
- 4月より早稲田大学大学院法務研究科教授を併任
3年間での修得を見据えた、重要な基本科目
日本に法科大学院が生まれたことによって、これから法律家を目指す学生の勉強への取り組み方が大きく変わってくると思います。これまでは、司法試験にいかにして合格するか、という問題がつねに前提としてあって、良くも悪くも「ここを勉強すれば合格できる」という勉強法に偏ることになり、その結果みんな同じような答案になっていました。これでは、自分の視野で独自に物事を捉え考えていく、という法律家の基本姿勢を育成することにはなりません。法律家の素晴らしい面は、強大な権力にも法をもって対等に戦うことができ、社会正義の実現に少なからず寄与できることです。たとえ最高裁の判決に対してであっても、時には批判的な視点が持てるような独自の思考力が必要です。何より「法曹資格を取った後に、その人がどのような法律家として社会に貢献していくのか」ということが大切だと思うのです。これからの法律家は、従来の法曹のフィールドを超えた様々な分野で必要とされるでしょう。早稲田大学大学院法務研究科では、法曹資格を得ることは単なる入口と捉えています。そういう意味でも、1年生からかなりハードに基本科目を修得することになりますが、ここですべてを理解できなくても落胆する必要はありません。2年生以降の専門科目や実践的なカリキュラムと関連付けることで、より深く理解できるようになっているので、3年間を通してじっくりと学修すれば自ずと将来へのイメージが明確になってくると思います。ともあれ教えてもらうという受身の態度ではなく、自ら主体的に取り組む姿勢が何より大切です。
早稲田に感じる、新しい法曹教育への挑戦
実は最初の頃、学生たちは私の授業で、しなくてはならない勉強量の多さに多少ショックを受けたようでしたね。私の担当する憲法関係の科目では、予め提示された予習課題を手引きに学生が十分に予習していることを前提に、1回の授業で3~4の主要な判例を取り上げ、さまざまな観点から検討を加えていきます。担当教員全員が定期的に打ち合わせをし、予習課題やクラスでの質問を作り、できるだけ共通認識をもって授業に取り組むようにしています。そこでは、考え方を一つの方向に導くのではなく、実際の訴訟の中で何がどのように争われているか、憲法がさまざまな法律とどう関わっているのか、憲法価値の実現の観点から何が問題なのか、を追及することが目的なのです。初めのころは、法学部で学んできた学生も、司法試験を受験したことのある学生も、100ページにも及ぶ判例をフルに読み込むといった勉強の経験がなく、予習がかなり大変だったようです。
我々、教員の方も「法務研究科の学生なのだから、これくらい平気だろう」というような意気込みがあったのですが、実際に授業を進めた反省や学生からの建設的な提案もあって、次第に改善を試みています。予習のポイントをはっきりさせ、学生はそれを知ることでさらに良い準備ができるようになり、教室ではディスカッションなどかなり突っ込んだ授業ができるようになってきています。法務研究科には、社会人体験のある学生を含めて多様なバックグラウンドを持った人が集まっているので、授業の内容と方法の双方についていろいろな角度から議論できる環境があると思います。特に学生同士で学び合うというのは早稲田の伝統でもあるのですが、法務研究科ではさらに可能性が広がっていると感じています。我々教員も日本の法科大学院での新しい教育に挑戦していきたいと思います。
「理想の光」を仰ぐ人々によって立つロースクールを目指して
すでに、それぞれのロースクールの役割が確立しているアメリカとは異なり、日本の法科大学院は、これから日本の社会で「法」の問題意識が高まり、一般の人を含めた多くの人が「法」を理解し使いこなさなければならない場面が確実に広がる、という視点に立ってスタートしています。それは、これからの時代は狭義の法曹だけではなく、企業のリーダーや地域や政治のリーダーたちも、「法」的なセンスを身につけて「法」を利用していくことが必要となることを意味しています。早稲田大学大学院法務研究科は、従来のような狭い範囲の法曹ではなく、社会のリーダーであったり、弱者の支えであったり、最先端分野のパイオニアであったり、さまざまな境界を超えたところで活躍できる法律家を養成していくべきだと考えています。
初めての法科大学院ということで、今は誰もが一所懸命です。私自身も、講義の前日には教材の準備で徹夜になることも多いのですが、学生たちも第一期生として多少の不安を抱えながら勉強に取り組んできたことでしょう。しかし、彼らは積極的に法科大学院作りに関わろうとし、その熱心な姿勢を目の当たりにするたびに、我々教員だけではなく、学生、職員と三者が一体となって早稲田大学大学院法務研究科を作っているのだ、という確かな手応えを感じています。結局、組織はそこに「集まり散じ」る人々によってその性格が決まるものですから。