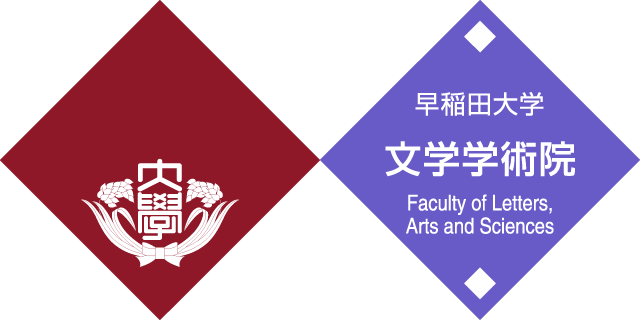- 学生報告書
- ベント 勇亮ヘンリー 文学研究科 国際日本学コース
ベント 勇亮ヘンリー 文学研究科 国際日本学コース

- Posted
- Fri, 18 Apr 2025
UCLA-Wasedaリサーチ・フェローシップ・プログラム 報告書
早稲田大学文学研究科国際日本学コース
ベント 勇亮ヘンリー
この度、柳井正イニシアティブ グローバル・ジャパン・ヒューマニティーズ・プロジェクトを通して、2024 Winter Quarter (2025年1~3月)のVisiting Graduate Researcherとしてカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)アジア言語文化学部に約3ヶ月間留学させていただきました。
周知の通り、ロサンゼルス近郊では2025年1月に大規模な山火事が発生し、広域に被害を及ぼしました。UCLAのキャンパスからそう遠くない地域まで火災が広がっていたこともあり、到着後1、2週間ほどは状況を見極めながらの生活となりました。しかし、災害対応についてのオンライン説明会の開催や詳細な被害状況の共有といったUCLAの迅速な対応と、マイケル・エメリック先生、Yanai Initiativeスタッフの皆様による個別のサポートのおかげで大きな不安を感じることなく過ごすことができました。この場をお借りして関係者の皆様へ改めてお礼申し上げます。
滞在中は、マイケル・エメリック先生による現代日本文学と翻訳についてのセミナーとトークィル・ダシー先生による日本古典文学のセミナーに参加し、ジョーダン・スミス先生による学部生を対象とした戦争と日本文学についての講義を聴講させていただきました。多様なバックグラウンドを持つ学生とのディスカッションは毎クラス刺激的な体験で、日本文学に対する広範かつ多角的な解釈に触れられただけでなく、英語での議論の実践としても貴重な機会となりました。毎週のリーディングを通して多くの英語の文献に触れられたことや、英語で日本文学を読むことで、そこに介在する翻訳の政治性を体感できたことも大きな学びとなりました。
また、日本学をテーマとした講演会もキャンパスで頻繁に開催され、日本文学はもちろんのこと、歴史学や社会学といった他の領域について学ぶ機会も多くありました。講演会への参加を通した他分野の研究者との意見交換により、日本学というより大きな枠組みの中における日本文学研究の在り方について再考でき、自身の研究の位置付けを客観的に見直すことができました。
クォーターの終盤では、私自身の研究についての発表の場を設けていただきました。参加して下さった先生方や学生の皆様に研究内容を共有できただけでなく、多角的な視点からのフィードバックをいただくことができ、大変有意義な時間となりました。
私自身、今春より大学で日本文学を英語で教えることとなり、日本文学を専攻していない、日本語が母語でない学生に対するアプローチを実際に体験できたUCLAでの滞在は、研究者としてのみならず、教育者としても大きく成長する機会となりました。
最後に、このような貴重な機会を下さったYanai Initiativeの皆様、十重田裕一先生、マイケル・エメリック先生をはじめ、早稲田大学とUCLAの関係者の皆様に改めてお礼申し上げます。