第1回「障がい者アスリート」
2020年10月3日(土) 13:00-14:30
兵藤智佳
- ゲスト・モデレータのご紹介
ゲストスピーカー:花岡伸和さん(パラリンピアン・日本パラ陸上競技連盟副理事長)
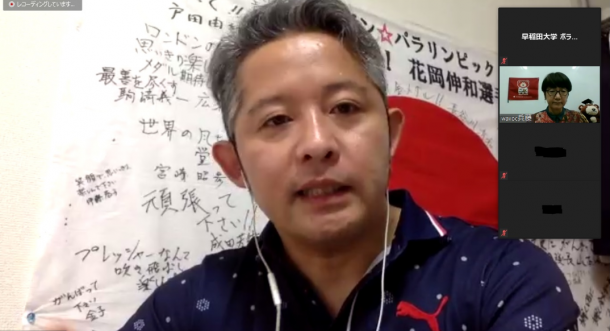 1992年、高校3年の時にバイク事故で脊髄(せきずい)を損傷し、車椅子生活となる。1994年に車いすマラソンに出会い、競技生活を開始。2004年、アテネパラリンピックの車いすマラソンで日本人最高位となる6位入賞。現在は、コーチとして若い選手の育成を行いつつ、障害者の運動にも積極的にかかわっている。
1992年、高校3年の時にバイク事故で脊髄(せきずい)を損傷し、車椅子生活となる。1994年に車いすマラソンに出会い、競技生活を開始。2004年、アテネパラリンピックの車いすマラソンで日本人最高位となる6位入賞。現在は、コーチとして若い選手の育成を行いつつ、障害者の運動にも積極的にかかわっている。
モデレーター:兵藤智佳(早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター准教授)
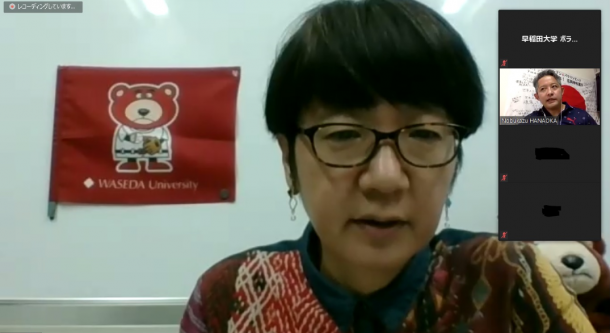 「マイノリティ支援」を専門として、これまで多くの大学生によるボランティア活動を主催してきた。大学では、ボランティア等の課外体験をした大学生を対象に「体験の言語化」による新しい教育手法の開発や実践、研究活動を行っている。近年は、「障害者アスリート」の支援ボランティアを通じて、「社会変革に与えるパラスポーツの可能性」についての発信活動にも積極的に取り組んでいる。
「マイノリティ支援」を専門として、これまで多くの大学生によるボランティア活動を主催してきた。大学では、ボランティア等の課外体験をした大学生を対象に「体験の言語化」による新しい教育手法の開発や実践、研究活動を行っている。近年は、「障害者アスリート」の支援ボランティアを通じて、「社会変革に与えるパラスポーツの可能性」についての発信活動にも積極的に取り組んでいる。
- 要旨
ゲストスピーカーの花岡さんは、車椅子に乗ったアスリートである。彼は、競技用の車椅子を時速35キロで走らせる「超人」であるが、日々の移動には常に制約がつきまとう。コロナ禍においては、多くの人が自由に移動や外出ができない状況となった。これは、一般にマジョリティと呼ばれる「健常者」が、日常では感じない不便を感じる機会であり、自分ではどうしようもない力に対して「自分のコントロールを失う」という体験ともなっている。
今回の対談では、コロナが障がい者にもたらしたポジティブな側面として、「リモートワークによって移動という障害が取り除かれた」という点が解説された。障がい者の働く能力という点では、障害は文脈に依存することが目に見えた経験であった。そして、これは、障がい者だけの問題ではなく、「移動してオフィスという場で働くことの意味を問う」という機会であり、社会の規範が変わる要因として語られた。一方で、「障がい者とスポーツの可能性」という点では、コロナが与えた負の側面も大きい。アスリートにとっては、パラリンピック延期は「目標の喪失」でもあり、彼らのメンタル面への支援は十分ではない現状がある。
花岡さんは、こうした個々のアスリートたちのおかれた困難への理解を求めつつも、コロナ禍は、パラリンピックの社会的意義を再度、確認するための時間とすべきであると主張する。商業主義や勝利至上主義に走るパラリンピックには、本質的な理念を失う危険がある。スポーツを通じて障がいを持つ人々が自分の可能性に挑戦することは勝利至上主義とは別次元の価値を持つからである。スポーツの中で失敗や負ける経験は、人間としての個人の学びや成長へとつながるからであり、パラリンピックの開催は、アスリートの姿を通じて「障害」をめぐる既存の社会的な価値観を揺さぶる可能性があるという。
また、「共生社会」の実現についても、あえて「共生」とは言うまでもないが、「障がい者と健常者」という線引きがなくなっていく重要性を指摘した。だからこそ、ボランティアや支援活動という意味では、「障がい者を理解し、助ける」という発想だけでなく、「不便を生きつつ、障がいという自分でコントロールできない状況を受容し、対応する」という当事者の生きる力に学ぶ姿勢を提示した。それは、コロナ禍を生きる多くの人々の抱える不安への処方箋となる可能性を持つからだ。
<セミナーレポート(テキスト)>
https://www.waseda.jp/inst/wavoc/assets/uploads/2021/03/c1cc33af68d91f36b2ad44ced9ac9126.pdf


