
澤田未来
SAWADA Miku
PROFILE
横浜出身。横浜雙葉高等学校卒。現在文学部美術史コース3年。「チャータースクールへの教育支援~ハワイ編~」に所属。大学1年の春から3年の夏まで4回、現地に渡航し、教育支援を行った。
参加したWAVOCの科目・プロジェクト
- ボランティア論―入門と基礎理論―
- 環境とボランティア
- チャータースクールへの教育支援~ハワイ編~
- 東日本大震災復興支援プロジェクト
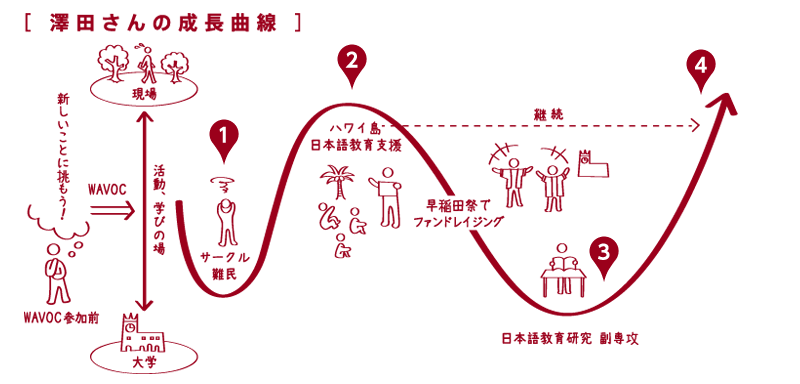
1.まさかのサークル難民、そして海外ボランティアへ
中高一貫校では演劇部の活動に励み、充実した毎日を送っていました。大学では新しいことに挑戦しようと期待に胸を膨らませて進学したのに、打ち込めるものが見つからず、気づけばサークル難民になっていました。そんな中、大学生の海外ボランティアを題材にした映画の予告編をテレビで目にして、予告編だけで泣く、という経験をしました。私も何かできるはず、とパソコンを開き、「“早稲田” “学生” “ボランティア”」と検索したのが、WAVOC公認「チャータースクールへの教育支援~ハワイ編~」プロジェクトとの出会いです。
2.出来ることは、何でもやろう
チャータースクールは、公的援助を受けて地域主体で運営される、アメリカ発祥の教育機関です。活動地のボルケーノスクールには、幼稚園生から中学2年生まで9学年、1学年に約20人の生徒が在籍しています。彼らを前に、英語を使って一人で授業。初回は緊張のあまりミスを連発し、落ち込んだ私はひと周りも離れた幼稚園児に励ましてもらう始末。最初の渡航では現地の方々に助けていただいてばかりで、とてもボランティアと言えるものではありませんでした。ただ、子ども達や先生方、ホストファミリーに会いたい、日本語教育支援を通して彼らの力になりたい、その一心で、その後3回渡航し活動を続けました。また、助成金が削減され、学校が教材の購入や施設の維持を十分にできていないという現状を知り、早稲田祭に企画を出展し、物品販売の収益をわずかながら現地に寄付しました。ハワイ島での様々な出会いからコミュニケーションを重ねるうちに、自分にできること探しをすること、それを行動に移していくことの大切さを学んでいきます。
3.のめりこんだ先に、見えてきたこと
帰国してからも毎日のように、「チャータースクールのために何が出来るだろう!?」と考えていたのですが、ふとこのプロジェクトが本当に役立っているのだろうかと不安になります。そこで、職員の方のアドバイスもあり、ハワイのみならず世界中で行われている日本語教育そのものについての学びを深め、活動に還元しようと全学共通副専攻「日本語教育研究」を履修しました。そこで国内外で日本語教育に従事する3名の方にインタビューをする機会を得ました。生徒の学習意欲や、彼らをとりまく現状を深く理解したうえで教育活動を行っている方々に比べると、私達の活動は現地のニーズに根ざしていない、独りよがりなものになっているかもしれない、と気づきました。「何のために、私は現地へ行き、子ども達の前に立つのか。」その答えは、自分で導く必要がありました。
現地学校では、日系人の子どものアイデンティティー形成に寄与するため、観光業が盛んなハワイにおいて、日本語能力があると就職に有利であるため、そして日本という外国の言語や文化を学ぶことで諸外国への興味を持ってもらうために、日本語を教えているそうです。年に2回、2週間という限られた私たちの活動期間ではありますが、現地の子ども達にとって、多感な時期に日本語や日本文化に触れることは、彼らの視野を広げ、新たな価値観をもたらすはずです。また、彼らにとって、日本人のお兄さん・お姉さんとの交流は、外国を身近に感じ、世界に目を向けるきっかけになるかもしれません。多様な日本語教育に触れ、改めて現地のニーズに耳を傾けることで、子ども達に日本語の楽しさが伝わるように、更なる工夫を重ねていきたいと強く思うようになりました。今は、子ども達の、生き生きと授業に取り組む表情や「楽しかった!」という声に、何よりものやりがいを感じています。
4.目の前の取り組みが次につながる
そんな中、今までの取り組みが、現地の人達と私達、相互の成長に、少しずつつながっているのではないか、と実感する機会がありました。Athenaという13歳の現地学校の子どもが日本に短期留学を決めたのです。私達の活動が現地学校の子供たちにとって、確実に日本や国際交流への興味を持つきっかけの一つになっているのだということが感じられて、とても嬉しく思いました。自分自身をふりかえると、メンバーや現地の方々に支えられながらリーダーを務めたり、現地学校の特色ある美術の授業に携わり、主専攻である日本美術史の学びを深めたりと教わったことは数えきれません。自分本意ではない活動を現地子ども達のために、と思っていたけれど、気がつけば“Learning by Teaching”の相互成長がありました。子どもの感性や想像力を養うことができる美術の力や、日本美術独自の面白さに気づきました。これをきっかけに、将来は美術の魅力を発信する担い手になりたい、と思うようになりました。これからも、私達の活動が、子ども達の人生を豊かにする一助になれたら、そして現地の人達と私達が、相互に学びあい成長する関係を続けていけたら、と思います。






