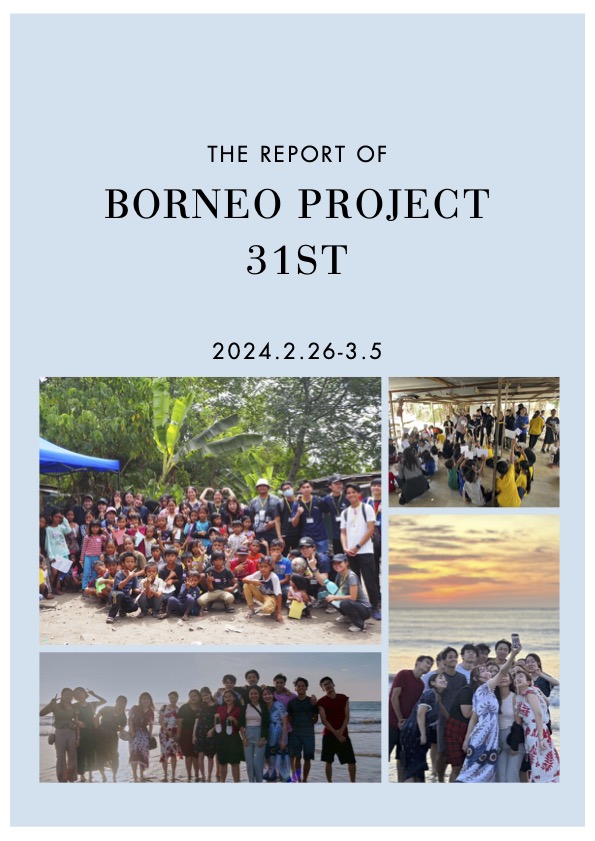コロナで途切れた絆をもやいなおす〜ボルネオ教育支援スタディツアー〜
岩井雪乃(平山郁夫記念ボランティアセンター准教授)
「ユキノせんせい〜!」マレーシア、コタキナバルの空港に降り立つと、顔なじみのマレーシア人の若者たちが、変わらぬ笑顔で出迎えてくれた。2024 年 2 月、私は「ボルネオ教育支援スタディツアー」として、学生 8 名を連れて、久しぶりにコタキナバルにやってきた。

子どもたち・日本メンバー・マレーシア学生で英語歌をうたう
本スタディツアーは、私が顧問をしている学生ボランティア団体「ボルネオプロジェクト(BP)」の活動をつなぐために開催したものである。BP は、マレーシアに数百万人いるとされる「無国籍の子どもたち」に教育支援を続けてきた。マレーシアの無国籍の子どもは、親が正規移民ではないため国籍がなく、公教育を受けることができない。そんな子どもたちに、少しでも知識と愛を提供する活動をしてきた。
それが、コロナ禍の 4 年間、現地渡航ができなかったため、マレーシア渡航経験のある学生がみんな卒業してしまい、後輩を育てることもできなかった。私は、2006 年に学生と一緒に BP を立ち上げて以来、ずっと活動を見守り、答えのない問いに挑戦しながら成長していく学生を支えてきた。「ここで BP を途絶えさせてはもったいない」との思いから、今回のスタディツアーを企画したのである。

子どもたちによりよい教育活動を届けるために、マレーシア学生と話し合う
そして、いつも現地活動で協力してくれるマレーシア学生も、私たちを待ってくれていた。マレーシア側でも、卒業生が呼びかけて、現役学生を集めてくれていたのである。
今回スタディツアーに参加した学生たちは、日本での準備ミーティングの段階から、全力投球でスタートし、可能な限りの時間を教育活動の準備に割いた。そして、もちろん現地でも、子どもたちともマレーシア学生とも全力で関わって、これまでの BP と同じかそれ以上に、現地との強い絆を育んだ。
その参加者たちが、報告書を作成した。一人一人の参加者が考えたことが伝わる内容になっている。ぜひご覧ください!
一部抜粋して掲載します。
教育の本質を追い求めて〜ボルネオ島で見た無国籍の子どもたちの現実と未来への挑戦〜
中村紡希(社会科学部二年)

私は大学2年間の中で、東南アジアの教育格差問題について興味をもって意欲的に勉強していた。しかしながら、実際に現地の状況を自分の目で見ることもなく、ただ机上で勉強することが本当に価値あることなのか疑問に思っていた。そんな中、実際に現地に渡航して学校に行けない無国籍の子どもたちに教育支援を行うWAVOC主催のボルネオスタディツアーの募集を見つけ、自分の学びをより深めたいと思い、参加することを決めた。
参加する前は、無国籍の人々がとても貧しい暮らしをしており、いちはやく助けなければならない危機的状況の中で日々怯えながら暮らしているのだと考えていた。何の罪のない子どもたちが正当な理由なく勉強の機会を奪われ、勉強をしたくてもすることができないことで、将来進む道の選択肢を狭められているという事実に悲しみや憤りすら感じていた。
しかし、実際に渡航して無国籍の人々が住む村を訪れ、自分の目でその現実を見て、自分の手で子どもたちに触れて、その考え方が大きく変化した。
 無国籍の人々の暮らしは、私たちの目から見ると確かに衛生的ではなく、危険と隣合わせの日々かもしれないが、そこに暮らす人々はとても生き生きとした、明るい笑顔に満ち溢れていた。子どもたちの無邪気に遊ぶ姿は日本にいる子どもたちと何も変わらなかった。
無国籍の人々の暮らしは、私たちの目から見ると確かに衛生的ではなく、危険と隣合わせの日々かもしれないが、そこに暮らす人々はとても生き生きとした、明るい笑顔に満ち溢れていた。子どもたちの無邪気に遊ぶ姿は日本にいる子どもたちと何も変わらなかった。
 それと同時に、村にいた多くの子どもたちがスマートフォンを持ち、InstagramやYouTube等のSNSやネットゲームを使いこなしていた。私はこのことに大きな衝撃を受けた。無国籍の人々だからといって、本当に危機的に貧しい状況にある人々はひと握りで、多くの家庭では子どもにスマートフォン等の娯楽を与える金銭的余裕があるのである。
それと同時に、村にいた多くの子どもたちがスマートフォンを持ち、InstagramやYouTube等のSNSやネットゲームを使いこなしていた。私はこのことに大きな衝撃を受けた。無国籍の人々だからといって、本当に危機的に貧しい状況にある人々はひと握りで、多くの家庭では子どもにスマートフォン等の娯楽を与える金銭的余裕があるのである。
今の時代、どこにいても、オンラインサービスを利用すれば自分の学びたい教育に関して容易にアプローチすることができる。村に学校がなければ、そして、村にある学校での教育よりももっと高度で専門的な勉強がしたいのならば、インターネットを介してオンラインで勉強すれば良いのである。
しかし、そんなことをしている子どもを私は誰ひとり見つけられなかった。基本的にはゲームをしたりYouTubeを見るなど、娯楽の範囲内でしかスマートフォンを使っていなかった。
そもそも一定の年齢になったら働きに出るか、婚約するかの人々に勉強するモチベーションなど、ほとんどないに等しいのである。
そこから、私は今後の課題として、子どもたちが主体的に学びにアプローチしたいと思える環境づくりが必要不可欠であると感じた。学ぶことで得られる楽しさを子どもたちに伝えていきたい。
学生ボランティアとして感じた限界、そこから見出した可能性
赤嶺友香( 文学部一年)

「大学生によるボランティア活動の限界と可能性に挑戦する」ボルネオプロジェクトの募集要項に書かれていたこの文章は最初あまりピンと来なかった。そんなことよりボランティアをする、それ自体に漠然と憧れを抱いていた当時の私は「限界」というマイナスな言葉を気にも留めなかった。そんな当時の私にいいたいのは、最初はこの気にも留めなかったこの文言こそが 2024 年春渡航を通して感じ た こ とを 端 的に 表 してい る 、 ということだ。これから、どういったところで学生ボランティアの限界を感じ、そこから絶望し、それでも自分の中で納得できる解決策を考え、希望や可能性を見出したかについて述べる。
渡航2日目に、実際に無国籍の人たちが住む村に行き、子どもたちに「将来は何になりたいか」というインタビューを行った。彼らは「医者になりたい」「教師になりたい」とキラキラした目で答えた。そのとき私は、このような将来に希望を抱いている彼らのためならどんなことでもしてあげたいと強く感じた。私は国籍を彼らに取らせて、夢を叶えてあげたいと思うようになった。しかし、国籍は取るのが複雑で困難だということや、そもそも国籍をとりたいと思っている人が少ないという現実を、その後、先輩から教えてもらって知った。

限界を感じたのは、まず一つ目に、こちら側が良かれと思って国籍取得に奮闘したとしても、それは現地の人にとっては望ましくない場合もあるという点だ。二つ目に、仮にもし取りたい人がいて、国籍を取らせてあげようとなっても、学生の短期のボランティアではできない、ということで限界を感じた。
そこから、国籍を取得しないという選択を大半の人はするため、医者になりたいと言っていた子どもたちの夢は叶えてあげられず、将来は工事現場で働く運命にあると知った。それでは将来の可能性を広げるための勉強を教える私たちの存在意義はないのではないか、と絶望した。勉強は将来の可能性を広げるために有効な手段だと思っていた私は、将来、工事現場で働くことが決まっている彼らに勉強を教えても無駄ではないかと悲観的になった。
しかし、勉強をする、学ぶ、という行為は将来の可能性を広げるためだけのものではなのだと凝り固まった考えを柔らかくし、思い直した。勉強することで、それ自体の楽しさを感じたり、達成感を得られたりする。また目標を立て、その目標を達成するためには何をすべきか逆算し把握する計画力や、目標に向かってコツコツと学ぶことで継続力が身に付く。 さらに思考力も得られる。勉強することでこれらのメリットを得られることを子どもたちに伝えていきたいと思うようになり、私たちが彼らにできることの可能性を見出すことができた。
さらに思考力も得られる。勉強することでこれらのメリットを得られることを子どもたちに伝えていきたいと思うようになり、私たちが彼らにできることの可能性を見出すことができた。
これらの経験を踏まえ、次回の渡航では子どもたちに勉強することでたくさんのメリットがあるということが伝わるような授業を展開したい。
ボルネオプロジェクト Instagram: https://www.instagram.com/borneoproject.kk/