【開催レポート】西川町スタディツアー「地域とかかわる」
学生リーダー 南部 耀之介
2024年2月4日(日)~7日(水)にかけて、西川町スタディツアー「地域とかかわる」を開催しました。西川町の活動でさまざまに学んだこと・感じたことをお伝えします。
きっかけ
「地方創生」—母方の実家が地方にある僕にとっては聞き慣れた言葉ではあったものの、実際地方では何がなされているのか、地方創生について僕に何ができるのかは全く知りませんでした。そんな僕が地方創生に強い関心を持ったきっかけは、学生寮の講演で登壇していた、山形県西川町の町長である菅野大志さんです。「関係人口を増やし、移住してくれる人を増やさなければならない」と熱く語ってくださった話に感化されて、地域に何か貢献したい、地域とかかわっていきたいと感じました。
それから半年後。西川町で何かボランティア活動ができないか、と相談しましたところ、快く受け入れてくださりました。日本有数の豪雪地帯として知られる西川町。その雪に関連した地域課題も多く、雪を生かしたイベントも開催されているため、冬の間に活動させていただくことになりました。
1日目 2月4日(日)
東京から新幹線に乗って山形駅に向かい、そこから左沢線に乗り換えて羽前高松に到着。駅で町の職員さんに車に乗せていただき、そこからさらに山の方へと進んでいきました。町の職員さんから今年は例年よりとても雪が少ないと聞きましたが、西川町に近づいていくにつれて周りに残る雪の量もだんだんと増えていき、都内の感覚でいえば大雪と思えるほどの雪の量が見られるようになっていきました。遠くに見える山々も一面雪化粧をしていて美しい景色が広がっていました。私たちが今回滞在した志津という地域は、西川町の中でも特に雪が多いことで知られており、雪のないところが見当たらないほどでした。
今回主に活動した「雪旅籠の灯り」というイベントまで時間があったので、西川町が力を入れているサウナの体験をさせていただきました。本格的なサウナに加え、水風呂の代わりに雪の中に飛び込めるということで、雪の多い地域ならではの体験ができたなと思います。
 その後、夕方5時ごろから「雪旅籠の灯り」のお手伝いをしました。このイベントは、雪を押し固めて作った建物をロウソクで飾るもので、夜になるととてもきれいな景色になります。建物に二階建てのものがあったり、入り口から中に入れるようになっているものもあったりと規模も大きく、建物の外壁の装飾も竜のレリーフがある等、色々な工夫がなされていて驚きました。今回はそのロウソクを設置し火をつけるところを手伝いました。イベントを開催している場所が広いことと、ロウソクの数が多かったことで、想像以上に作業は大変でした。日が出ているうちは寒さも気にならず活動できていたのですが、日が沈むと一気に寒くなり、手の悴む気温の中での活動となりました。
その後、夕方5時ごろから「雪旅籠の灯り」のお手伝いをしました。このイベントは、雪を押し固めて作った建物をロウソクで飾るもので、夜になるととてもきれいな景色になります。建物に二階建てのものがあったり、入り口から中に入れるようになっているものもあったりと規模も大きく、建物の外壁の装飾も竜のレリーフがある等、色々な工夫がなされていて驚きました。今回はそのロウソクを設置し火をつけるところを手伝いました。イベントを開催している場所が広いことと、ロウソクの数が多かったことで、想像以上に作業は大変でした。日が出ているうちは寒さも気にならず活動できていたのですが、日が沈むと一気に寒くなり、手の悴む気温の中での活動となりました。

一緒に活動していた地元の旅館の方に聞いたところ、雪旅籠の灯りのイベント以外でもこの地域では人手が足りないということをおっしゃっていました。私たちは今回六人で参加したのですが、それでも火をつけるのは時間がかかったため普段はもっと時間がかかって大変なのだろうと感じました。
 その後、旅館でおいしいご飯をいただき、活動の振り返りミーティングを行い、1日目は終了しました。
その後、旅館でおいしいご飯をいただき、活動の振り返りミーティングを行い、1日目は終了しました。
2日目 2月5日(月)
2日目は西川町の菅野大志 町長と対話する時間を取っていただきました。お話の中で今後の町で取り組んでいくことについて質問したところ、西川町を組織として横のつながりを強化していくことや、それによって補助金の獲得を目指し、町を活性化していきたいといったお話をしていただけました。財務省での勤務の経験もあるということで、その時のことも交えながら話していただき、学びの多い時間となりました。町長が精力的に活動していることや、それで町が変化しつつあるというのがよくわかりました。
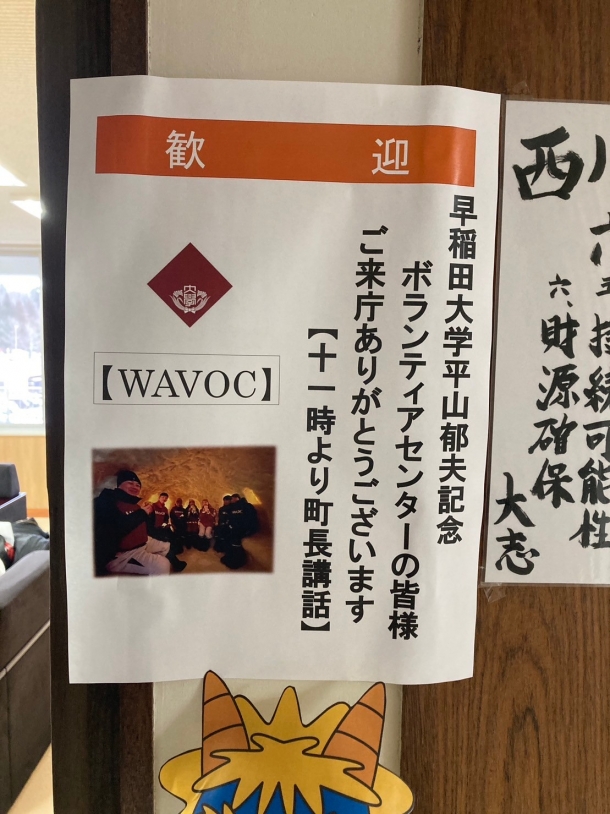 対話後、町長や町の職員さんたちと一緒に、地域でよく食べられているひっぱりうどん(この地域では「ひきずり」と呼ぶそうです)をいただきました。ひっぱりうどんというのはうどんを卵・納豆・鯖缶・出汁などを混ぜたつゆにつけて食べる料理です。実は僕は卵や納豆が苦手なのですが、具材を混ぜてうどんと食べてみるととてもおいしくいただくことができました(お土産に乾麺を買うほどおいしかったです)。
対話後、町長や町の職員さんたちと一緒に、地域でよく食べられているひっぱりうどん(この地域では「ひきずり」と呼ぶそうです)をいただきました。ひっぱりうどんというのはうどんを卵・納豆・鯖缶・出汁などを混ぜたつゆにつけて食べる料理です。実は僕は卵や納豆が苦手なのですが、具材を混ぜてうどんと食べてみるととてもおいしくいただくことができました(お土産に乾麺を買うほどおいしかったです)。
食後は「雪旅籠の灯り」で開くお店の仕入れのお手伝いをしました。地元の歴史ある商店やワイナリーの方々とお話をするなかで、町の人が我々のような町を訪れる人に対してフレンドリーで、人柄も温かいことが分かりました。二日目も一日目と同じように灯りを付ける活動を行いました。5時ごろから台湾からの団体の観光客が来るということで急いで行いました。観光に来た人たちが楽しそうに見て回ったり写真を撮ったりしているのを見て、とてもうれしく思いました。また、地元の方がイベントの写真を撮りに訪れていて、「今年もきれいだね」とおっしゃっていたのでやりがいを感じられました。
 振り返りミーティングの中で、「地域の方々は、このように大学生が訪れて活動していることをどのように思っているのだろう」という疑問が浮かびました。どこかで地域の人に質問してみたいなと思いつつ、二日目は終了しました。
振り返りミーティングの中で、「地域の方々は、このように大学生が訪れて活動していることをどのように思っているのだろう」という疑問が浮かびました。どこかで地域の人に質問してみたいなと思いつつ、二日目は終了しました。
3日目 2月6日(火)
3日目は当初雪掃きをする予定だったのですが、稀にみる雪の少なさということで、西川町で全戸配付しているタブレット端末の操作講習会のお手伝いをすることになりました。想定よりも多くの人に来ていただけたようで、たくさんの人に教えることができました。タブレットでの防災無線の聞き方や基本的な操作などを、高齢の方々にもわかりやすいように工夫しながらお伝えしました。最初はタブレット端末を見たことが無い方も多く、新しいものに対しての嫌悪感などを示されて、「ちょっと面倒くさいしわからない」とおっしゃる方もいました。
しかし、説明を通して最後には、「便利なものをもらったんだから、頑張って使えるようにならなきゃね。操作も忘れちゃうかもしれないけど教えてもらいながら頑張るわ」と言っていただけて、お役に立てたんだなという安心感と、自分が教えることで新しいものを受け入れていただけたという達成感・やりがいを感じました。
講習会を通してたくさんお話した方に、前日に感じた「大学生の活動を地域の方々はどう思っているのか」というのを質問しました。すると、「大学生が活動しているのは今日初めて知った。何をしているのか全然知らない」との返答があり、まだまだ地域の人たちとは深くかかわれていないのだなと反省すると同時に、これからかかわっていける余地はたくさんあるなと感じました。
講習会の後に、西川町歴史文化資料館を見学しました。金山としての発展の歴史や鎌倉時代のお話や、江戸時代の三山信仰に関してのお話など興味深いものが多かったです。
 夜に大井沢地区で行われる町長と町民の対話会に行きました。町が変化の過程にあるというのは様々なところで感じていましたが、ここでも感じることができました。農家の方が農業方針を町長に直接話していたり、河川のキャッチアンドリリースの方針に対する意見などを述べていて、町政に町の方が積極的にかかわろうとしていることが感じられました。
夜に大井沢地区で行われる町長と町民の対話会に行きました。町が変化の過程にあるというのは様々なところで感じていましたが、ここでも感じることができました。農家の方が農業方針を町長に直接話していたり、河川のキャッチアンドリリースの方針に対する意見などを述べていて、町政に町の方が積極的にかかわろうとしていることが感じられました。
4日目 2月7日(水)
最終日の4日目には道の駅に隣接する天然水の工場、ビール造りの場所を見学しました。どちらも西川町の魅力を外に発信する重要な役割を果たしているなと感じました。ビール造りを担当している方に詳しくお話を聞くことができたのですが、「2年後を目標に、様々な発泡酒の試作を続けている。さくらんぼをつかったお酒を造りたいがなかなかうまくいかず、試行錯誤している」とおっしゃっていました。
 また、道の駅に併設されているサウナで勤務されている熱波師の方にお話を伺いました。西川町に住む際に快く受け入れてくださったことや、熱波師として働くことについてのお話、サウナについての話をたくさんしていただきました。
また、道の駅に併設されているサウナで勤務されている熱波師の方にお話を伺いました。西川町に住む際に快く受け入れてくださったことや、熱波師として働くことについてのお話、サウナについての話をたくさんしていただきました。
どちらの方のお話からも、新しいことに挑戦する人を受け入れる姿勢が広がっていることが伝わってきました。受け入れる姿勢が広がっていることが伝わってきました。
スタディツアーを終えて
まずこのスタディツアーを通して、人の役に立つこと・喜んでもらえることの楽しさを様々な場面で学びました。灯り付けを通して、観光客の人たちに限らず地元の方々にまで喜んでいただけたこと、それを参加した学生の中で共有できたことはなかなか得られない経験でした。ほかにもタブレット端末操作講習会で私が担当した人たち全員に操作方法などを理解してもらうことができて、役に立つことによるやりがいを感じることができました。特に講習会を通して、前向きに「少しずつ覚えていこうかな」と思っていただけて良かったです。
もう一つ学んだこととして、人とかかわることの楽しさがあります。西川町の人がとても暖かく歓迎してくれたこともあって、何かボランティアを通してお返ししたいと感じました。今回の経験からボランティアで活動することの根本には、人とかかわることの楽しさがあるのではないかなと思いました。
最後に、ボランティアとして地域とかかわっていくことは十分可能だと感じました。お伝えしてきたように西川町はいま新しいことを取り入れたり変化をし始めている段階です。西川町のように新しいことを始めている地域はほかにもたくさんあるはずです。そこに学生のボランティアがかかわり、できることはたくさんあると、今回の活動の中で思いました。
また、地域とのかかわりは一瞬だけではなく、継続していかなければならないことだと感じています。なぜならボランティアで取り組む地域課題は一回だけの取り組みで終わるものではなく、毎年起こることであったり、長期的に取り組まなければ解決できないものも多いからです。スタディツアーを通して、そこをいかに続けられるかが今後の課題なのではないかと考えました。







