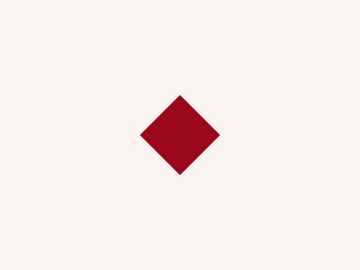2025年7月19日(土)にスマートエスイーコンソーシアム主催 DX交流フォーラムを早稲田大学リサーチイノベーションセンター・コマツ100周年記念ホールにて開催しました。オンライン配信も含め、多くの方にご参加いただき、誠にありがとうございました。
本ページにて、招待講演およびパネルディスカッションの動画をアーカイブ配信中です。是非ご覧ください。
※同時開催したDXコース募集説明会のアーカイブ配信はこちら
DX交流フォーラム
招待講演
- 及川 信太郎 氏
株式会社サイバーエージェント
株式会社AI Shift - テーマ
「人とAIの協働による生産性革命とは」AIエージェントと働く、サイバーエージェントの実践事例

「今年はAIエージェント元年」と語る及川氏より、ご自身の経験から生成AIとAIエージェントを活用したDX推進の具体的な取り組みをご紹介いただきました。サイバーエージェントグループでは、「日本一生成AIを徹底活用する会社」を目指す、という代表からの強いメッセージを契機に、全社的なリスキリングやAIオペレーション室の設置を推進し、広告事業で2026年までに既存業務の完全自律化を目指す営業AIエージェントを開発。これにより商社での営業マルチAIエージェント導入事例や、コールセンターの自動化事例を挙げ、トップダウンとボトムアップを融合した支援体制で85%以上という高いPoC突破率を実現しています。AIエージェントの概念として、ワークフロー型と自律型の違いやその仕組みにも触れ、AIを通じて人類の生産性向上に貢献していくビジョンが語られました。
修了生による講演 1
- 大塚 大 氏(IoT/AIコース6期生)
株式会社クレスコ - テーマ
IoT/AIコースでの学びと修了制作の成果

社会人5年目当時、エンジニアリングの応用力不足とビジネス視点の欠如に課題を感じ、受講を決意。IoTコースでビジネス、アプリケーション、情報処理、通信物理の4領域における原理原則や実務に直結する技術を深く習得しました。多様な受講生との交流で視座を高め、修了後は社内業務のデジタルソリューション創出や生成AI人材育成に貢献。受講目標であった「技術の本質理解と応用力」「ビジネスアイデアを形にするプロセス」を達成し、業務における成果物の品質向上と顧客価値追求の姿勢を身につけられたと報告しました。
修了生による講演 2
- 山田 大介 氏(IoT/AIコース7期生)
Hella Japan inc. - テーマ
修了制作の取り組みと成果

ご自身のキャリアがハードウェアからソフトウェア・システム開発へとシフトしたことへの危機感と、ハード・ソフト知識の分断克服、AI・機械学習の実装力習得を動機にスマートエスイーを受講。受講を通じて、アイデアを具現化する能力、ハード・ソフトの一貫した知識、そしてビジネス観点(価値検証の重要性)を強く習得したと実感され、修了後には、公共案件コンサルティングでの生成AI活用による効率化、ペットの健康モニタリングシステム開発、ビジネスコンテストへの挑戦、個人の課題解決向けアプリ開発など、多岐にわたる新規事業を創出しています。自身の積極的な行動が本業や周囲の技術活動を活性化させ、メンバーの能力向上にも繋がる良い波及効果を生んでいると報告しました。
修了生による講演 3
- 中谷 浩二 氏(DXコース3期生)
アッヴィ合同会社 - テーマ
修了制作の取り組みと成果

製薬・医療機器業界での営業からバックオフィスへのキャリアチェンジを経て、データ分析の専門性習得と社内DX推進の必要性を強く感じ、DXコースを受講。DXコースではPower BIやRPAなどの技術面と、DX推進に必要なマインドセット、ビジネスモデルの仮説検証、経営者の視点といった施工面の両方を深く学びました。特に、年齢や役職の異なる社外の仲間との活発な議論を通じて視野を広げ、忍耐力とコミュニケーションの重要性を再認識したと語りました。修了後、社内DX化プロジェクトを推進し、勉強会を主導。社内ダッシュボード化の功績で表彰を受けるなど、具体的な成果を上げていることが報告されました。
パネルディスカッション
- 登壇者
及川 信太郎 氏(招待講演者)
大塚 大 氏(スマートエスイー修了生)
山田 大介 氏(スマートエスイー修了生)
中谷 浩二 氏(スマートエスイー修了生)
ファシリテータ:鷲崎 弘宜(早稲田大学教授・スマートエスイー事業責任者) - テーマ
DXの課題、進展、人材育成 ~スマートエスイーでの学び・成果を交えて~ - 質問1
企業が大学のリカレント教育に期待する学習効果と評価
~企業が期待する大学リカレント教育の「実践性」とは?~ - 質問2
生成AI時代における人材ニーズの変化とリカレント教育の役割
~生成AI時代に求められる人材と、リカレント教育の役割とは?~ - 質問3
企業による大学リカレント教育活用の促進策
~企業がリカレント教育を「活用しやすい仕組み」とは?~
「技術との向き合い方が変化し、以前は場当たり的だった実装に対して仕組みや設計意図の理解が深まった」
「汎用的な知識・技術を習得し、特定のツールに依存せずアーキテクチャの本質を理解できる力がついた」
「技術面に加え、DX推進に必要な全体像を把握し、それを分解して思考する「思考面」を学べた。」
という修了生による学習後の評価を受け、及川氏は「大学のリカレント教育は、大人になってから学術的観点を体系的に学べる貴重な機会、研究に裏付けられた教育が社会実装に活きる」という期待を示しました。
「大学の教育は基礎が重要だが、社会のニーズに合わせて価値創造に繋がる部分との連携が更に求められており、スマートエスイーはその点で有効である。大学も企業もオープンイノベーションを取り込んでいくことが重要」と鷲崎教授は述べました。
スマートエスイーとしても生成AIをどう取り込んでいくかが課題であり、この生成AI時代、企業においてもスキルやマインドを変えていかなければ、という鷲崎教授の意見を発端に活発な意見交換が行われました。
そんな中で及川氏は「企業に求められるのは新技術に対する「食わず嫌いしない」姿勢であり、新技術を当たり前として積極的に活用することが求められる」と述べました。また、リカレント教育には生成AIの仕組み、リスク、ガバナンスといった基礎知識の習得を期待するとしました。
中谷氏は、時代に応じたスキルや知見を取り入れていくことが重要で、効率化が進む中でも、最終的な意思決定は人が行うべきであり「人の魂を込める」意思決定の重要性は変わらない、と指摘しました。
また山田氏は、学びへのハードルが下がったため、様々な分野で「食わず嫌いしない」学びの姿勢が必要だと述べました。自動運転や医療など安全性が求められる分野では、AI活用と並行してその仕組みを理解し、説明責任や倫理観、サイバーセキュリティといった基礎的な要素がより重要になるとしました。
大塚氏は企業派遣で受講した経験から、上司や現場マネージャーの理解と業務調整などの配慮が非常にありがたかったと述べ、今後も同様の配慮が効果的であると示唆しました。
山田氏は個人参加であり、時間的な配慮は得られたものの金銭的なフォローはなかったため、企業が大学のリカレント教育を活用するには、成果を会社に還元できることを具体的に示す努力や、大学との共同開発の実績、プログラムが人材の底上げに貢献できるという認知を広めることが重要と指摘しました。
中谷氏も個人での受講であるものの、会社の制度や教育訓練給付金を利用したと述べました。また、個人的な感想として、自分でお金を出したことで「貪欲に学ぼうとする」姿勢が強まったため、業務をおろそかにせず、学習と業務を両立させたと述べました。
及川氏は今回、スマートエスイーのようなプログラムの存在を初めて知ったとのことで、キャリアの節目におけるインプットは非常に重要だと認識。大学のリカレント教育を社員のキャリアアップ・チェンジの機会として、企業が活用を検討すべきだと推奨しました。
当日の様子




入会のご案内
スマートエスイーコンソーシアムでは、今回のDX交流フォーラムをはじめ、スマートエスイーが対象とするIoT、AI、DXといった各分野に関連するセミナーやイベントを開催しています。入会は無料です。これを機に是非ご参加ください。
https://www.waseda.jp/inst/smartse/consortium
DXコース募集説明会
同時開催したDXコース募集説明会のアーカイブ配信は以下のページをご覧ください。
https://www.waseda.jp/inst/smartse/news/7110