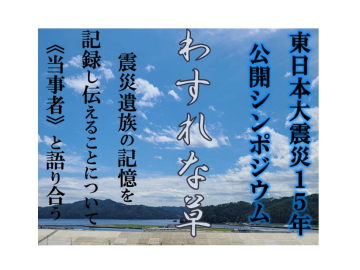語が持つ綴りと意味の対応関係が読みの速度に影響する
~ 速く正確に読むには、形態素が重要! ~
発表のポイント
- 文字列に対する「語−非語判断」を求める語彙判断課題(提示された文字の並びが、本当の言葉かどうかを見分けるテスト)※1に、語の綴りと意味の対応関係の一貫性効果(綴りが似ていて、意味も似ている言葉の存在が読みを促進し、綴りが似ているが意味が異なる言葉の存在は読みを抑制するという効果)が報告されています。
- データ分析の結果、この一貫性効果は、文字追加隣接語※2をもとに一貫性を操作した際には観察されるものの、文字置換隣接語(や文字削除隣接語)※3をもとに一貫性を操作した場合には観察されないことが明らかとなりました。
- また、文字追加隣接語による一貫性効果は、ターゲット語と形態素※4を共有する文字追加隣接語による形態素ファミリーの促進効果※5に加えて、形態素を共有しない文字追加隣接語による抑制効果も生じるため、一貫性効果を観察し易いことが明らかとなりました。
- 今後の研究を通して、語を読む際、その語が持つ形態隣接語や形態素が果たす役割がさらに明らかになり、そうした知見をもとに、より速く正確に言葉を読む方法やより適切な言葉の学習方法が開発されることが期待されます。

概要
早稲田大学文学学術院の日野 泰志教授、ウェスタンオンタリオ大学(University of Western Ontario)のDebra Jared教授およびStephen J. Lupker教授らの研究グループは、英単語を対象に、ターゲット語に文字を追加した形態類似語(文字追加隣接語)、文字を置換した形態類似語(文字置換隣接語)、文字を削除した形態類似語(文字削除隣接語)をもとに、別々に一貫性効果の有無を確認し、一貫性効果の生起には文字追加隣接語が大きな役割を果たしていることを突き止めました。
では、なぜ一貫性効果には文字追加隣接語が重要なのでしょうか。この問題をさらに検討したところ、ターゲット語と似た意味を持つ文字追加隣接語は、形態素を共有するターゲット語の派生語を多く含むため(e.g., SAVES, SAVED, SAVER for SAVE)、形態素ファミリーの存在による促進効果が生じる可能性が高いことが明らかとなりました。さらに、ターゲット語と意味が異なり、形態素を共有しない文字追加隣接語は、ターゲット語の処理を抑制することも明らかとなりました(e.g. SCREAM for CREAM)。しかし、文字置換隣接語や文字削除隣接語は、ターゲット語と形態素を共有する・しないに関わらず、ターゲット語に対する処理を促進する傾向のみが観察されました。このように、一貫性効果の背景には、形態素を共有する文字追加隣接語による促進効果と形態素を共有しない文字追加隣接語による抑制効果の両方が関与していることが明らかになりました。
本研究成果は、『Journal of Memory and Language』(論文名:Orthographic-semantic consistency effects in lexical decision: What types of neighbors are responsible for the effects?)にて、2025年5月5日(月)にオンラインで掲載されました。
これまでの研究で分かっていたこと
最近の英語の研究では、与えられた文字列に対する語−非語判断を行う語彙判断課題の“語”判断の反応は、類似の綴りを持つ語同士が似た意味を持つ場合の方が、類似の綴りを持つ語が異なる意味を持つ場合よりも速く正確であると報告されています(e.g., Marelli & Amenta, 2018; Siegelman, Rueckl, Lo, Kearns, Morris & Compton, 2022)。この効果を語の形態−意味対応の一貫性効果と呼びます。一方、過去に、日野研究室で行った日本語を使った研究では、行動データに有意な一貫性効果を観察することができませんでした(Tachibana, Kida & Hino, 2020, November)。そこで、これらの研究の違いを確認したところ、類似の綴りを持つ形態隣接語に対する定義が研究間で異なっていました。Marelli & Amentaの研究では、ターゲット語の綴りを含む別の語を形態隣接語として使用していたのに対して、Siegelman et al.は、Levenshtein距離1の形態隣接語を使用していました。これは、ターゲット語に1文字を追加するか、置換するか、削除するかして作成される別の語のことです。さらに、Tachibana et al.は文字置換隣接語のみを使用していました。そこで、英単語を対象に、文字追加隣接語、文字置換隣接語、文字削除隣接語から別々に形態−意味対応の一貫性を計算し、その効果の有無を確認することで、形態隣接語の種類の違いが一貫性効果にどのようなインパクトを持つのかについて再検討してみようと考えるに至りました。
今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと
本研究では、英単語を対象に、ターゲット語に文字を追加した形態隣接語(文字追加隣接語)、文字を置換した形態隣接語(文字置換隣接語)、文字を削除した形態隣接語(文字削除隣接語)に対して、別々に一貫性効果の有無を確認しました。その結果、一貫性効果の生起には文字追加隣接語が大きな役割を果たしていることが明らかになりました。では、なぜ文字追加隣接語が重要なのかという問題についてさらに検討したところ、ターゲット語と類似の意味を持つ文字追加隣接語の多くは形態素を共有する派生語であるため(e.g., SAVES, SAVED, SAVER for SAVE)、形態素ファミリーの存在による促進効果が生じることが確認されました。この効果は過去の複数の研究でも報告されています(e.g., de Jong, Schreuder & Baayen, 2000; Ford, Davis & Marslen-Wilson, 2010; Kuperman, Schreuder, Bertram & Baayen, 2009)。さらに、ターゲット語と意味が異なる文字追加隣接語は、ターゲット語と形態素を共有しない形態隣接語であり、これらの存在は、ターゲット語の処理を抑制することも確認されました(e.g. SCREAM for CREAM)。この抑制効果は文字追加隣接語に対してのみ認められ、文字置換隣接語や文字削除隣接語は、ターゲット語と形態素を共有する場合も共有しない場合も、ターゲット語に対する処理を促進する傾向が認められました。このように、一貫性効果の背景には、形態素を共有する文字追加隣接語による促進効果と形態素を共有しない文字追加隣接語による抑制効果が大きく関与していることが明らかになりました。同じ綴りを共有する語が似た意味を共有する場合には、形態素ファミリーの存在によって語の読みが促進されるのに対して、同じ綴りを共有する語が異なる意味を持つ場合には、別の語彙・形態素レベルの表象の活性化により、ターゲット語に対する処理が抑制されるというメカニズムが介在する可能性が示唆されました。
研究の波及効果や社会的影響
語の綴りから音韻情報への対応関係の性質が、語を読み上げる成績に大きな効果を持つことが知られています。また、語の音韻情報から綴りへの対応関係の性質が、語の聞き取り成績に大きな効果をもつことも知られています。本研究で扱った綴りと意味の対応関係の性質に関する効果は、語を読む際の成績が語の綴りと意味との間の対応関係の性質に依存することを示しています。本研究の成果をもとに、語を読む際の形態素の役割がさらに明確化されることが期待されます。類似の綴りを共有する語同士が類似の意味を持つことで、これらの語に共通の“形態素”が形成され、これらの語が読みやすくなるものと思われます。一方、類似の綴りを共有する語同士が異なる意味を持つ場合、一方の語を読む際に誤って他方の語の意味で読まれることがないように、抑制のメカニズムが発達し、機能しているものと思われます。こうした語を読む際に機能するメカニズムが、今後の研究でさらに明らかになっていくことで、言葉をより速く、正確に読む方法や、子供や第二言語学習者に言葉を教える際の適切な方法の開発にも貢献することができるものと思われます。
今後の課題
本研究では、語彙判断課題のデータのみを対象にデータ分析を進め、語を読む際、文字追加隣接語が重要な役割を果たしていることが明らかとなりました。その一方で、カテゴリー判断課題や関連性判断課題など、語の意味に関する判断を求める意味課題を使った多くの研究では、ターゲット語を読む際に、その文字置換隣接語の意味も活性化され、ターゲット語に対する意味判断に効果を持つことが報告されています(e.g., Forster & Hector, 2002; Hino, Lupker & Taylor, 2012; Rodd, 2004)。このように、意味課題を使った場合には、文字追加隣接語による意味活性化ばかりでなく、文字置換隣接語による意味活性化も機能することが知られています。そこで、今後は、意味課題に観察される効果にも注目することで、意味課題の処理において形態素や形態隣接語が果たす役割を再検討し、語彙判断課題に観察される形態素を介した処理との間の性質の違いなどについて検討を進めて行きたいと考えています。
研究者コメント
本研究は、2022年度9月から1年間、特別研究期間の際に、カナダのUniversity of Western OntarioのJared教授とLupker教授と共に進めた研究です。この研究は、日本語を使ったTachibana et al. (2020, November)の研究で英語と同様の結果を確認できなかったのはなぜかという問題意識が背景にありました。この問題意識を持って、カナダで1年間英語の読みに関する研究を行うことができたことが今回の成果に繋がりました。私たちの言葉の知識はどのような形で学習され、記憶されているのか、私達が言葉を読む際に、どのような作業を行っているのかという問題は、私たちが持つ情報処理システムはどのような仕組みでどのように機能しているのかという問題とも関連した重要な問題です。本研究の成果を踏まえ、さらに研究に取り組んでいくことで、こうした問題が解明され、言葉を速く正確に伝えるコミュニケーションの方法や適切な言葉の学習方法などが開発されていくことが望まれます。
用語解説
※1 語彙判断課題
実験参加者の前にあるスクリーンに刺激文字列を提示し、それが実在する語であるかどうかの判断を求める課題。実験参加者は迅速かつ正確に判断に応じて“語”ボタンか”非語”ボタンを押すよう求められる。刺激提示からボタン押し反応までの反応時間をミリ秒単位で計測し、反応の正誤も記録される。
※2 文字追加隣接語
類似の綴りを持つ語を一般に形態隣接語(orthographic neighbors)と呼ぶ。形態隣接語の中で、”SAVE”に対する“SAVES”や”CREAM”に対する”SCREAM”のように、ターゲット語の綴りに文字を追加して作成される形態隣接語を文字追加隣接語と呼ぶ。
※3 文字置換隣接語と文字削除隣接語
形態隣接語の中で、”SEAT”に対して“MEAT”や”SENT”のように文字の置換によって作成される語を文字置換隣接語、”SEAT”に対して”SEA”や”SET”のように文字の削除によって作成される語を文字削除隣接語と呼ぶ。
※4 形態素
これ以上文字を削除すると意味が損なわれてしまう語を構成する最小単位。
※5 形態素ファミリーの促進効果
同じ形態素を共有する語グループを形態素ファミリーと呼ぶ。形態素ファミリーの数が多い語ほど、語彙判断課題の反応が速く正確であることが報告されている(e.g., de Jong et al., 2000; Ford et al., 2010; Kuperman et al., 2009)。
論文情報
雑誌名:Journal of Memory and Language
論文名:Orthographic-semantic consistency effects in lexical decision: What types of neighbors are responsible for the effects?
執筆者名(所属機関名):日野 泰志(早稲田大学文学学術院)*, Debra Jared(University of Western Ontario), Stephen J. Lupker (University of Western Ontario)
掲載日時(現地時間):2025年5月5日
掲載日時(日本時間):2025年5月4日
掲載URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749596X25000397
DOI: 10.1016/j.jml.2025.104646
研究助成
なし