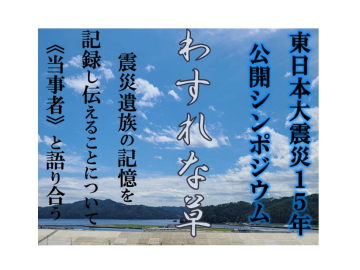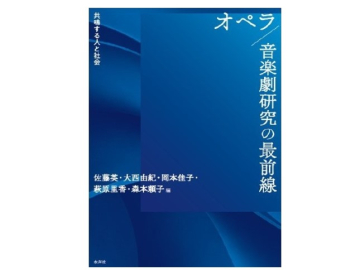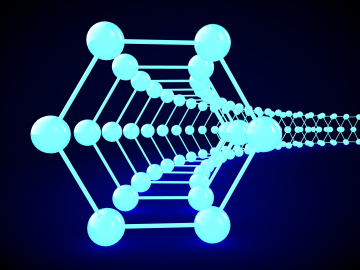早稲田大学は、シンポジウム「私立大学の戦略的コアファシリティ2024」~私立大学が整備する多様なコアファシリティの役割りと意味、産官との連携~を2024年1月24日(水)に開催し、85機関282名の方にご参加いただきました。
このシンポジウムは、少子化や人口減が進行、産業競争力や研究力が相対的に低下する日本において、多くの学生の高等教育を担う私立大学の研究環境、とりわけ全学的なコアファシリティの戦略的なシステム整備をメインテーマとして取り上げました。その特徴ある取組みや工夫の数々を紹介するとともに、私立大学ならではの課題等についても議論することで、あらためて、様々なステークホルダーにもたらす役割りや意味を考えたいということです。
その初回となる今年度は、文部科学省科学技術・学術政策局長の柿田恭良様、同研究環境課長の稲田剛毅様、一般社団法人日本分析機器工業会技術委員会委員長の杉沢寿志様などからご挨拶、ご講評をいただくなど、以下のプログラムに沿ってオンライン形式で開催しました。
https://www.waseda.jp/inst/research/news/75795
主催:早稲田大学
共催:東京理科大学、東海大学、一般社団法人日本分析機器工業会JAIMA、一般社団法人研究基盤協議会CORE
東京理科大学、東海大学、早稲田大学という、3つの私立大学からの事例が紹介されるとともに、大きく2つの視点について、その工夫や課題などについての掘り下げた議論が繰り広げられました。学生ファーストかつ公的補助が少ない私立大学では、研究力を向上させるための研究インフラの整備をどのように工夫すべきか、そして、学生への機器使用の技術研修にはどのような課題があるのか、などです。

文部科学省科学技術・学術政策局長の柿田恭良氏(上段、右から1人目)、一般社団法人日本分析機器工業会技術委員会委員長の杉沢寿志氏(二段目、左から1人目)、東京理科大学研究推進機構研究機器センター長の酒井秀樹氏(二段目、左から2人目)、本学理工学術院統合事務・技術センター技術部長の細井肇(二段目、右から2人目)、本学研究推進部長の天野嘉春(二段目、右から1人目)、文部科学省科学技術・学術政策局研究環境課長の稲田剛毅氏(三段目、左から1人目)、東海大学学長室(研究推進担当)部長の岩森暁氏(三段目、左から2人目)、本学理事(研究推進部門総括・産学連携担当)の若尾真治(三段目右から2人目)、東海大学マイクロ・ナノ研究開発センター講師(URA)の荒砂茜氏(四段目、右から2人目)
本シンポジウムを通じて、より高度な研究インフラが整備されている公的研究機関など、外部との連携、相互利用などは欠かせない点、そして、企業における日本独自の雇用形態が時代遅れとなる中、学生への基本的な素養や経験をいかに積ませるかという点など、私立大学の今後の取組みへの期待が示されました。さらに視聴者から、私立大学ならではのもっと自由かつ積極的に社会変革・未来創造する案を出していくべきとのコメントなども寄せられました。
次年度以降も、全国の私立大学における戦略的なコアファシリティについて、ともに議論する仲間を増やしていくとともに、私立大学への期待に応えるソリューションについて、探求を深めて参ります。