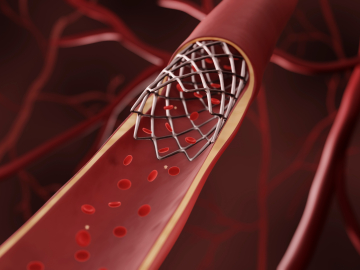2019年6月13日、本学にて、5人の中核研究者から2018年度の研究成果報告がおこなわれました。はじめに、理工学術院の合田亘人 研究推進部長から開会の挨拶がありました。合田教授はこの会の趣旨と「次代の中核研究者育成プログラム」の制度について説明をし、中核研究者への期待を述べました。
2019年6月13日、本学にて、5人の中核研究者から2018年度の研究成果報告がおこなわれました。はじめに、理工学術院の合田亘人 研究推進部長から開会の挨拶がありました。合田教授はこの会の趣旨と「次代の中核研究者育成プログラム」の制度について説明をし、中核研究者への期待を述べました。
 次代の中核研究者育成プログラムとは、「Waseda Vision 150」の核心戦略7『独創的研究の推進と国際発信力の強化』において標榜した≪若手研究者プロモーションの推進PJ≫の一環として、次代の早稲田の研究力の担い手となる中核研究者を育成するもので、若手・中堅研究者を中心としたチーム型研究の促進を図ります。一定の研究水準を満たした若手・中堅研究者を選定し、より大型のプロジェクトを獲得できるよう支援を集中させることで、研究者プロモーションを介した新たな研究分野の開拓、国際共同研究を通じた国際研究プレゼンス向上を狙う本学の独自の研究戦略のひとつです。
次代の中核研究者育成プログラムとは、「Waseda Vision 150」の核心戦略7『独創的研究の推進と国際発信力の強化』において標榜した≪若手研究者プロモーションの推進PJ≫の一環として、次代の早稲田の研究力の担い手となる中核研究者を育成するもので、若手・中堅研究者を中心としたチーム型研究の促進を図ります。一定の研究水準を満たした若手・中堅研究者を選定し、より大型のプロジェクトを獲得できるよう支援を集中させることで、研究者プロモーションを介した新たな研究分野の開拓、国際共同研究を通じた国際研究プレゼンス向上を狙う本学の独自の研究戦略のひとつです。
発表者は以下のようです。
関根泰教授(理工学術院)2016年度採択者
 関根教授は、「関根イオニクス触媒プロジェクト」について説明をしました。研究テーマは「低温での表面イオニクス・スピントロニクスが誘起する触媒反応」です。
関根教授は、「関根イオニクス触媒プロジェクト」について説明をしました。研究テーマは「低温での表面イオニクス・スピントロニクスが誘起する触媒反応」です。
有村俊秀教授(政治経済学術院)2017年度採択者
 有村教授は「有村・環境エネルギー政策プロジェクト」について説明をしました。研究テーマは「環境・エネルギー政策の実証研究:価格vs非価格アプローチ」です。
有村教授は「有村・環境エネルギー政策プロジェクト」について説明をしました。研究テーマは「環境・エネルギー政策の実証研究:価格vs非価格アプローチ」です。
ファーラー・グラシア教授(国際学術院)2016年度採択者
 ファーラー教授は、「ファーラー国際労働移動プロジェクト」について説明をしました。研究テーマは「異なるスキル・レベルの労働者の国際移動と外国人労働者のスキルについての考察」です。
ファーラー教授は、「ファーラー国際労働移動プロジェクト」について説明をしました。研究テーマは「異なるスキル・レベルの労働者の国際移動と外国人労働者のスキルについての考察」です。
岩田浩康教授(理工学術院)2015年度採択者
 岩田教授は「岩田心身覚醒RTプロジェクト」について説明をしました。研究テーマは「ライフ・サポート・ロボティクスの新展開」です。
岩田教授は「岩田心身覚醒RTプロジェクト」について説明をしました。研究テーマは「ライフ・サポート・ロボティクスの新展開」です。
十重田裕一教授(文学学術院)2014年度採択者
 十重田教授は「トエダ日本文学・文化再想像プロジェクト」について説明をしました。研究テーマは「世界の中で日本文学・文化を再想像する」です。
十重田教授は「トエダ日本文学・文化再想像プロジェクト」について説明をしました。研究テーマは「世界の中で日本文学・文化を再想像する」です。
最後に、理工学術院の笠原博徳 副総長から閉会の挨拶が述べられ、会は盛況に終わりました。