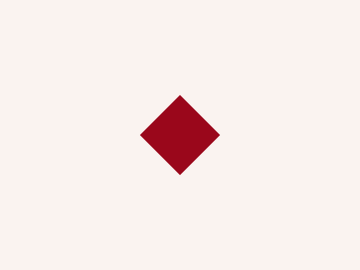2023年10月に始まったパレスチナ(ハマス・ガザ地区)とイスラエルの軍事紛争。
イスラエル側から一方的に破棄された人質交換交渉のあと、11月から現在まで、ひたすら「イスラエル自衛権」の名のもと軍事攻撃が苛烈に続けられています。
停戦に対し、国際社会が駆け引きをしている間、無防備な人の命が、東京と全く同じ気温の寒空に投げ出され、ガザ地区の住民220万人のうち、すでに9割の飢餓が言われています。水も食料も封鎖された状態で、空爆下に三か月。
なぜ一方がこんな風に空爆し続けることが「自衛」なのか、そもそもこの紛争は他の国際紛争と同じなのか?違うとすれば何が違うのか。民衆の声はいったいどうなっているのか。不思議すぎる状況が我々の理解と支援を阻みます。
今回のシンポジウムでは、植民地主義と民族虐殺だとかの大文字の国際政治ではなく、民衆目線で、現場で何が起きているのかを知り、聞き取り、それによってこの紛争を「民衆にとっての意味」から再解釈しようとする挑戦です。それは、現地の住民が奪われた意思決定と同じように、国際社会の我々が奪われている意思決定を取り戻すための、一つのアクションでもあります。こんなことは起きてはならないと確信する私たちの声もまた、まとめなければなりません。
事前申し込み不要です。
後半の対談時間では、フロアからの意見徴収も織り込み、現地に届けたいメッセージの書き込みボードも設置します。パレスチナって何?イスラエルってどうして? 小さな疑問を持ち寄って、私たちが今ここから彼らとつながる道について考える機会にしたいと思います。お気軽にご参加ください。
〈開催概要〉
●会場:早稲田大学 早稲田キャンパス14号館 102号室
●プログラム
10:00-14:00 第一部 絵画展[夢見る権利]
14:00-17:00 第二部 シンポジウム[ともに・いきる](討論言語:日本語)
①趣旨説明
◆野中章弘(早稲田大学教授/アジアプレス・インターナショナル代表)
②ガザ2023の総括と分析、共存・和解への展望
◆鈴木啓之 (東京大学 特任准教授・中東研究)
③お話と対談
◆土井敏邦(パレスチナに34年間通い取材を続けたジャーナリスト・映画監督。作品に映画『ガザに生きる』(5部作)、『沈黙を破る』など)
×
◆ダニー・ネフセタイ (平和と人権を考える元イスラエル空軍 ユダヤ人の家具職人・ 東京新聞記事2023年10月18日 )
絵画解説
◆佐々木陽子(南山大学准教授・ 科研費20K20686)
●主催:ジャーナリズムとメディア表現(早稲田大学グローバル・エデュケーションセンター)
共催:科研費(挑戦的研究・萌芽)20K20686「芸術との対話を経た公共圏の形成過程に関する実証研究」
●お問合せ:[email protected]
●チラシ