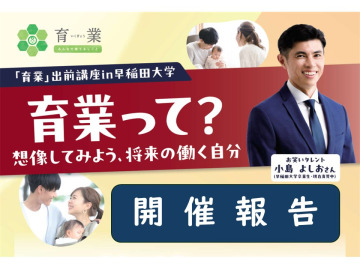~障がい者・パラスポーツの支援を通じ共生社会を知る~
 2025年10月14日(火)早稲田キャンパス18号館国際会議場(井深大記念ホール)で「早稲田大学ボランティア・アカデミー ~ 障がい者・パラスポーツの支援を通じ共生社会を知る ~」を開催し、96名の学生・教職員にご参加いただきました。
2025年10月14日(火)早稲田キャンパス18号館国際会議場(井深大記念ホール)で「早稲田大学ボランティア・アカデミー ~ 障がい者・パラスポーツの支援を通じ共生社会を知る ~」を開催し、96名の学生・教職員にご参加いただきました。
このアカデミーは、障がい者やパラスポーツを支援するボランティアについての関心と理解を深めるとともに、障がい者支援に必要な実技体験を通じて共生社会の実現に貢献することを目的として開催いたしました。開催にあたっては、清水建設株式会社様が、2015年より障がい者やパラスポーツに関する知識を深め、ボランティアの養成に寄与することを目的として全国各地で大学生や地方自治体を対象に定期的に開催してきたアカデミーをベースに、NPO法人STAND様に企画・運営のご協力をいただきました。
基調講演 伊藤数子氏
 冒頭のご挨拶に続いて、まずは日本のパラスポーツ支援の第一人者である伊藤数子氏(NPO法人STAND代表理事/スポーツ庁 U-SPORTS PROJECTアドバイザリー委員)より、パラスポーツとボランティアに関する基本的な知識や心構えに関する基調講演をいただきました。
冒頭のご挨拶に続いて、まずは日本のパラスポーツ支援の第一人者である伊藤数子氏(NPO法人STAND代表理事/スポーツ庁 U-SPORTS PROJECTアドバイザリー委員)より、パラスポーツとボランティアに関する基本的な知識や心構えに関する基調講演をいただきました。
伊藤氏からは「ボランティア=自発的な、進んで、というのが本来の意味。日本ではボランティア活動というと重たく堅苦しいイメージをもたれることもあるが、まずは自発的に、という意思を大事に取り組んで欲しい」という趣旨のお話がありました。
続いて参加者を「視覚障がい編」「車いす編」の2班に分けて、講義と実技体験を行いました。70分ずつで班を入れ替え、両編を全てご参加いただきました。
基調講演 初瀬勇輔氏

「視覚障がい編」ではまず初瀬勇輔氏(2008年北京パラリンピック 視覚障害者柔道 日本代表/一般社団法人 日本パラリンピアンズ協会副会長)より講演をいただきました。
初瀬氏からは、緑内障により視覚障害となり失意の底にあったが、高校時代に打ち込んだ柔道を再開し2008年北京パラリンピックに出場を果たしたことで、障がいを受容するきっかけとなった、という実体験を語っていただきました。
実技体験 ~視覚障がい編~
その後、社会福祉法人日本盲人社会福祉協議会東京視覚障害者生活支援センター職員2名より、二人一組でアイマスクを着用しながら、視覚障がい者の歩行誘導の実技指導をいただきました。段差を乗り越える、椅子に安全に座る、障害物の間を通行する、といった実技を通じ、特に視覚障がい者が歩行時に感じる不安と恐怖を実感いただき、この不安と恐怖を取り除くために必要なサポート方法を学びました。
基調講演 花岡伸和氏

「車いす編」ではまず花岡伸和氏(2012年ロンドンパラリンピック マラソン5位入賞/NPO法人関東パラ陸上競技協会理事長)より講演をいただきました。
高校3年時にバイク事故で脊髄を損傷し車椅子生活となったこと、そこから車椅子陸上を始め2度のパラリンピックに出場したこと、現在はパラ陸上選手の支援と後進の指導に尽力していること、などの実体験を語っていただきました。
実技体験 ~車いす編~
その後、理学療法士4名より4班に分かれ、車椅子に乗車して段差を乗り越える実技指導をいただきました。5cmの段差を乗り越えることが如何に難しいかを実際に体験し、社会には障がい者にとって多くのバリアが存在することを実感することができました。車椅子の構造やどのような改良ができるか、という視点で理学療法士に質問する参加者もいらっしゃり、非常に高い意識をもって取り組んでいただけたことがうかがわされました。
パラスポーツ支援の第一人者やパラアスリートから直接お話をうかがい、また、きめ細かな実技を実際に体験してみることで、初めて身に付いた知識や技術があり、非常に有意義な時間になりました。
本アカデミーでの経験が、参加いただいた皆様の障がい者に対する意識を変え、視野を広げ、共生社会のあり方を考えるきっかけとなることを願っています。
【参加者から寄せられた感想】(一部抜粋)
- 「困っている方がいたら声をかける」という最低限のことすら今までの自分はできなかったと思いますが、声をかけ、その後どうすればいいのかということがこのイベントのおかげで学ぶことができました。困っている方によってニーズは異なると思いますが、イベント前の自分よりもできることが確実に増えたと思います。機会があれば必ず実践します。
- 話と体験がどちらもできるところが良かった。実際誘導をしたことがありましたが、よりよい方法を知ることができて良かったです。声掛け1つでもかえられることがある、バリアはいたるところにあるということを改めて自分で気づけました。
- 視覚障がい者の誘導方法を学べたことで、今まで声をかける勇気が無かったけど、これから声をかけることができる大きなきっかけとなったと思います。正しく誘導することで障がい者の方の不安を取り除くことができたらいいです。
- 今まで経験したことのなかった経験で貴重な体験だった。体験は一時的だが、当事者はその状況がずっと続くわけなので、そこのところを忘れないようにしていきたい
- 車椅子の実物を扱うことが初めてだったので、扱い方から乗った間隔まで体験することができたことがよかったです。視覚障がいの方の誘導に入り色んなパターンがあることが少しですがわかりました。実践の経験を積みたいと思います。
- 目が見えないことがどれだけ怖いのかを身をもって理解しました。今後の生活でそのような人に気を配っていきます。
- 視覚障がい編の実技で段差がありますと言われてそれが上りか下りかわからないと不安であると知ってハッとしました。まだまだ自分自身の目線でしか考えられていないと実感しました。
- 障がい者側の視点を体験しつつ、介助者として必要なことを丁寧に教えていただけたのが良かった。講演されたパラスポーツ選手の方のお話がおもしろく、実技の指導をしてくださった方の綿密な対応がよかった。