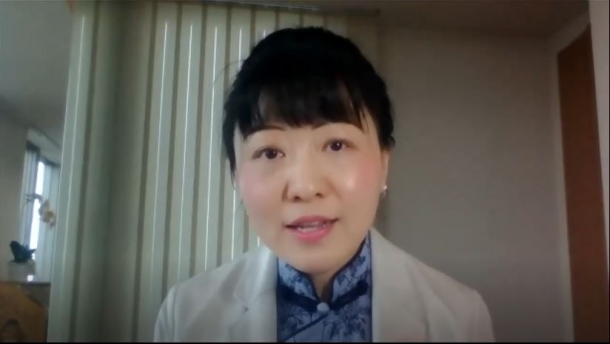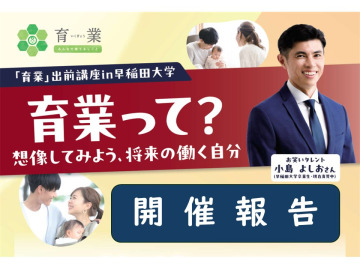2021年2月17日、「ワーク・ライフバランスデザインワークショップin 商学学術院」がオンライン開催されました。講師に東京国際大学商学部教授の平木いくみ氏、味の素(株)グローバルコーポレート本部コーポレート戦略部マネージャーの湯春慧氏をお招きし、嶋村和恵商学学術院教授の司会進行のもと、第一部講演会、第二部グループセッションの二部構成で行われました。大学院生をはじめ、学部生、附属校や系属校の生徒(高校生)も含め22名の参加がありました。
冒頭、司会の嶋村先生より「第一部の講演会では、商学研究科での大学院生活で得たものがその後のキャリア形成にどのような影響を及ぼしているか、修了後のキャリア形成の過程でさまざまなライフイベントに対してワークライフバランスをどのようにキープしていったか、自分らしいワークスタイルをどのように見出していったか、など具体的な体験談をうかがいます。その後、Q&Aセッションや第二部のグループワークの中で、参加者の皆さんの疑問や不安に対するアドバイスをいただきます。全体を通して、皆さんが今後のご自身の目指すべきキャリアを模索するうえで参考になるようなヒントを得ていただければ嬉しく思います」とのご挨拶がありました。
講演概要:平木 いくみ氏

講師:平木 いくみ氏
学部卒業後に就職した企業が経営破綻するという事態に見舞われ、「大学院で専門性を身に付けてから再就職先を考えよう」という気持ちで修士課程に入学した。学びを深めるうちに、その先に博士後期課程、さらに研究者・大学教員への道があることに気づいた。
商学・ビジネス分野における女性研究者の割合は低く、その中で母親として子育てをしながら仕事を続けているロールモデルは極めて少ない。自分としては「母親になること」と「自分のキャリア形成」の両立を目指したうえでできることをするしかなく、そのための環境を整える工夫と努力を重ねてきた。
第一子は早稲田大学で助手をしていた頃、第二子は他大学で3年間の任期付き教員となった最初の年に出産した。第二子の産前産後の一時期は、授業を休講とし、校務に従事できない時期があった。雇用を維持していただきながら、働けない時期には一時的に処遇が下がるというのは当然で、精神的には楽になったが、その事実が周囲の同僚には理解されていない状況の中で居心地の悪さを感じたこともあった。ダイバーシティについて深い理解のある先輩の女性教員から励ましていただいたことが唯一の心の支えだった。
このような経験から、社会的責任からいったん解放された環境で「第三子を産みたい」という思いを優先し、専任教員として次の就職先を探すことをせず、週に一度の非常勤講師をしながら子育てと研究を両立させる生活を選んだ。子育てと並行して細々とではあるが、着実に研究を続けた結果、3年後に東京国際大学で専任教員としての職を得ることができた。
信条として「女性だから」、「子どもがいるから」ということに甘えず、自分に課せられた仕事は責任をもってこなすことで、周囲のメンバーから認められる状況を生み出すことを心がけてきた。また、同世代の研究者と自分を比較したりせず、「自分の生活と研究のバランスを取るために、自分の目標の中でどのような研究プロセスを描いていくか」を意識するようにしている。
振り返ってみると、大学院へ進学したことが自分にとっての大きな転機だった。大学教員になる道を拓き、専門家として社会で活躍する場を与えていただくベースを築くことのできた商学研究科には感謝している。
講演概要:湯 春慧氏
「ワークライフバランス」は目的ではない。あなたにとって何が大事か、何をしたいか、そのためのワークライフバランスであり、自分の「ありたい姿」をまず明確にする必要がある。私の場合、社会人になった当初は、ビジネスパーソンとしての基盤を確立したいと思い、そのためにワークライフバランスをデザインしていた。仕事においては未経験の仕事にどんどんチャレンジし、上司や同僚からコミュニケーションの仕方を学び、周囲から信頼されるよう努力した。生活の面では収入支出の計画、余暇の過ごし方、自己研鑽などのプライベートの基盤を確立していた。現在は仕事においても生活においても責任が大きくなっているので、両方の責任をきちんと果たしたいというのが、今の私の「ありたい姿」だ。
一方、「キャリア」とは何か。私が勤める味の素では「キャリアとは仕事人生。過去~現在~未来へ続く、仕事を通じて自己成長するプロセスのこと」と定義している。そのような視点から、私のこれまでのキャリアと生活を振り返ってみたい。
2000年、外国人新卒採用第1号として入社した私は知的財産部に配属された。商学研究科で学んだマイケル・ポーターの「3つの基本戦略」(①コストリーダーシップ戦略、②差別化戦略、③集中戦略)を思い出した。差別化戦略とは競合他社製品よりも高い付加価値を提供すること。つまり、知的財産の仕事は味の素の差別化戦略、競争優位性の構築につながる仕事だと理解していたので、味の素の事業に寄り添って知的財産の仕事をスタートすることができた。6年間、業務遂行はもちろん、ビジネスパーソンとしての基本を確立するとともに、社内のネットワークを構築できた。生活の面では都内に自宅を購入し、夫と二人での日本での拠点ができた。
その後、自分の実力を磨きたいと思い、事業本部への異動希望を出した。当時、事業部に異動できるのは営業を経験した人のみだったが、私の場合は商学研究科で消費者の行動について研究し、ある程度理解していると認めてもらい、営業を経ずに事業本部に配属されることとなった。事業本部では10年間、主に製品開発を担当した。大学院で勉強した知識をフルに活かし、さらに理解を深めた。この間、中国の父が手術をすることになったが、新商品の開発に関わっている大事な時期と重なり、帰国できないという事態に直面した。葛藤もあったが、これを機に家族や親戚と相談し、両親には環境が整った老人ホームへ移り住んでもらうこととなり、安心を得ることができた。
2013年に管理職になり、2016年に知財部に異動し、4年間、契約チーム長としてマネジメントの能力を鍛える機会を得た。この間、夫が単身で海外に赴任することも経験した。
2020年、人事部から「さらに広いマネジメントの視点を鍛えないか」との提案を受け、グローバルコーポレート本部で新しい業務に取り組んでいる。ここでも大学院で得た知識と先生方とのコミュニケーションの経験が大いに活かされていると思う。社外コンサルタントと仕事をする機会も多いが、専門家の学歴や巧みなトークに惑わされることなく、妥当な方向でサービスを提供してもらえている。現在、味の素には夜間に大学院で勉強をしている社員がたくさんおり、大学院、特に商学研究科で学ぶ知識は、事業会社にとってとても役に立つと思う。
これまでのキャリアを重ねる間、生活の面では各種ライフイベント、両親の健康状態、夫の海外勤務単身赴任など、自分が選択できるものと選択できないものの両方があったが、その都度、自分の納得のいく方策、望む生活になるように判断し、行動してきた。今後も生活と仕事のバランスを図りながら、自分や家族の幸せはもとより、お客様の健康と幸せのために貢献していきたい。
皆さんは「Π型人材」という言葉をご存じだろうか。広い知識を持ったうえで二つの専門分野を持つ人材、つまり二本の脚は自分のポジションや世の中の変化に応じて変化していき、時代や自分のポジションに合った脚で前進できる人材のことだ。パラダイムシフトが加速している現代においても、マインドシフトで対応していけば、社会に必要とされる人財で居続けられるのではないか。そのような人材を目指していくことの重要性を感じている。

ファシリテーター:谷口 真美先生
第二部のグループセッションでは、アカデミックのフィールドに関心のある方、ビジネスのフィールドに関心のある方、二つのグループに分かれ、それぞれ活発な議論が交わされました。最後にファシリテーター役を務められた谷口真美教授から「“ありたい自分の姿”を描く。つまりどんなフィールドで誰から評価されたいかという自らのソーシャルアイデンティティについて考えていくこと、そこでの自分の居場所をみつけていくことが大切です」とのアドバイスがありました。
参加者からは以下の感想が寄せられ、とりわけ高校生(附属校、系属校の生徒)に将来の進路を描くきっかけを与えるという面で、意義深いシンポジウムとなりました。
参加者感想
「今回の講演は今まで曖昧だった自分の将来像を深く考えるヒントとなりました。まだ高校生で社会人までの道のりは長いですが、御二方の先生のように自分の生活と仕事を両立させることができるよう、努力していきたいと思いました。ありがとうございました」
「今回はこのような貴重な体験をさせていただきありがとうございました.早稲田大学の商学部の大学院に進んだという同じ経験をしていても,大学院に進もうと決めるまでの過程やその後の人生の歩み方は今回お話してくれた二人とも全く一緒のものではなく,自分が将来どのような進路を歩んでいきたいのか今一度考えるきっかけになりました.今後もこれからの自分の人生について考えることができるようなワークショップがあればぜひ参加したいです」