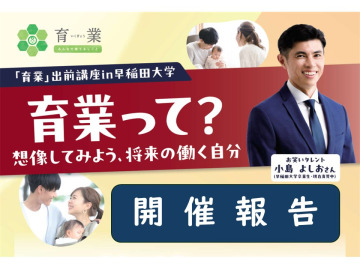男女共同参画・ダイバーシティの推進プロジェクト講演会
2017年11月10日、早稲田大学小野記念講堂にて、スウェーデン大使館の協力のもと、男女共同参画・ダイバーシティの推進プロジェクト講演会を開催しました。本学学生・教職員を中心に、参加者数は201名となりました。
 冒頭、ダイバーシティ推進室長 矢口徹也教授より、「日本では、何事にも組織優先で、仕事のために生きている感も否めません、この講演で、自分らしきられる社会についてヒントをいただけると思う」と、開会の挨拶がありました。
冒頭、ダイバーシティ推進室長 矢口徹也教授より、「日本では、何事にも組織優先で、仕事のために生きている感も否めません、この講演で、自分らしきられる社会についてヒントをいただけると思う」と、開会の挨拶がありました。
お一人目の講演者であるスウェーデン大使館 政治経済担当官 アップルヤード和美氏より、まず、スウェーデンは国政における女性閣僚の割合が50%であり、世界で初めて「フェミニスト政府」と呼ばれていること。ジェンダー別に統計がとられており、その中でも注目すべきは雇用率で、男性と女性がほぼ同じ75%を超えており、年々、女性が外で働く時間は長くなり男性が外で働く時間が短くなってきおり、男性が家事をする時間が世界で一番長いと言われている。男性10人中9人は育児休暇を取得し、男性が家事をすることが当たり前である男女平等社会の存在を紹介されました。
 政府は1921年から男女平等を推進するための改革をおこない、女性が働き続けられる環境づくりが進み、現在に至っています。加えてジェンダー平等については、高等教育、学会、研究者において取り組んでおり、1980年代からジェンダー別に統計をとり、政策の立案にも役立て、
政府は1921年から男女平等を推進するための改革をおこない、女性が働き続けられる環境づくりが進み、現在に至っています。加えてジェンダー平等については、高等教育、学会、研究者において取り組んでおり、1980年代からジェンダー別に統計をとり、政策の立案にも役立て、 学校の授業や学生生活の中で社会の問題を考えるということをおこなっていると紹介され、「これらが、スウェーデンのエンパワメントだと感じている」という言葉で締めくくました。
学校の授業や学生生活の中で社会の問題を考えるということをおこなっていると紹介され、「これらが、スウェーデンのエンパワメントだと感じている」という言葉で締めくくました。
続いて、スウェーデン大使館広報部補佐のエラノア・セザー氏から、スウェーデンのジェンダーマイノリティについて講演がありました。スウェーデンでは、LGBTQA,LGBTQAIという言葉もあるが政府を含めて「LGBTQ」を使っていること、 その背景として、国家以外にもLGBTQをサポートする組織や団体が数多くあること、その理解と環境整備をおこなった企業へは認定書が発行され、全国で500近くの認定企業が存在している反面に、問題点の一つとして性的志向での差別が存在し暴力を受けるなどの被害が出ているということも明らかとなりました。これらの問題を解決し、社会を改善するためには、「教育」と「オープンマインドでいること」が大切であると、会場へのメッセージが投げかけられました。
その背景として、国家以外にもLGBTQをサポートする組織や団体が数多くあること、その理解と環境整備をおこなった企業へは認定書が発行され、全国で500近くの認定企業が存在している反面に、問題点の一つとして性的志向での差別が存在し暴力を受けるなどの被害が出ているということも明らかとなりました。これらの問題を解決し、社会を改善するためには、「教育」と「オープンマインドでいること」が大切であると、会場へのメッセージが投げかけられました。
後半は、ダイバーシティ推進委員会教育研修部会長 弓削尚子教授による進行で質疑応答がおこなわれ、スウェーデン大使館から、アップルヤード氏、エラノア氏とともに、広報部の佐々木文夫氏、科学イノベーションのLisa Yuen氏、Petter Erlandsson氏の5名が登壇され、パネルディスカッションの時間となりました。会場からはスウェーデンの教育についてやLGBTQの宗教としての対応についてなどの質問が途切れることなく続き、事前の質問を含めそれぞれの意見や具体的な例が紹介されるなど、閉会までひとつひとつ丁寧に回答される時間となりました。

参加者からは「スウェーデンではLGBTQ差別が違法であること、同時に、民間への意識浸透はゆっくりであること、精神的な負担感などは拭えないこともわかった」「高い税金で手厚い福祉を実現されているというイメージがあったが、LGBT平等が社会でどのように実現されているか未知数だったので、興味を持つきっかけとなった」等、理解が深まったという意見が届きました。
以 上