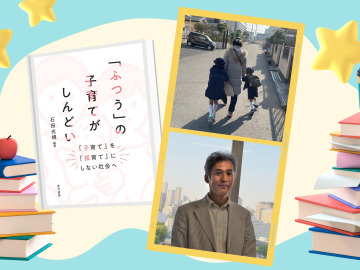育休取得を経験して、変わったこと
T:育休取得 をきっかけに、働き方や組織に対する貢献意識・意欲などに変化はありましたか?きれいごとに聞こえるかもしれませんが、私は、限られた時間の中でもよい仕事をしたいと思うようになりましたし、休職中にサポートしてくれた他の職員のサポートをより積極的に行いたいと思うようになりました。
をきっかけに、働き方や組織に対する貢献意識・意欲などに変化はありましたか?きれいごとに聞こえるかもしれませんが、私は、限られた時間の中でもよい仕事をしたいと思うようになりましたし、休職中にサポートしてくれた他の職員のサポートをより積極的に行いたいと思うようになりました。
Y:育休をとったから、ということではないかもしれませんが、妻の育児負担を減らしたいと思い、なるべく早く帰れるように努力するようになりました。
K:妻は現在は専業主婦ですが、今も私は18時までには毎日職場を出ています。朝は集中できるので早めに出勤し、自分で終わりを決めて働くなど、効率的に仕事を進めるようになりました。かつては長時間にわたって働いていたこともありましたが、働いても働いてもキリがないですし、現在の短時間で集中する働き方の方が、体には合っていると思います。
N:やはり、なるべく早く帰って妻の負担を軽くしたいと思いますので、限られた時間で仕事をこなすため、仕事の優先順位をつけて働くようになったと思います。
T:保育園の迎えなど時間の制約があって、そこに間に合わせるために頑張れるということはありますよね。子育てによる時間制約は、一般的にマイナスと捉われがちですが、これからの職場では、生産性やモチベーションという意味でプラスであると私は思います。
メッセージ
T:最後に締めのメッセージを頂きたいと思います。
 Y:当時私がいた職場のように、その世代の職員が多いと、産休・育休が発生する可能性は高いですよね。この点を考慮して、管理職が業務分担のローテーションを積極的に回していたことで、育休を取りやすかったですし、引き継ぐ側も安心できたと思います。実際、以前の職場では産休・育休の取得する人が次々に現れましたが、事前に対策を講じていたので業務が滞ることなく円滑に引継ぎができました。職場と職種によって事情は違うかもしれませんが、このような職場環境は今後増えていくと思いますので、育休を取ることに不安を感じないでほしいと思います。
Y:当時私がいた職場のように、その世代の職員が多いと、産休・育休が発生する可能性は高いですよね。この点を考慮して、管理職が業務分担のローテーションを積極的に回していたことで、育休を取りやすかったですし、引き継ぐ側も安心できたと思います。実際、以前の職場では産休・育休の取得する人が次々に現れましたが、事前に対策を講じていたので業務が滞ることなく円滑に引継ぎができました。職場と職種によって事情は違うかもしれませんが、このような職場環境は今後増えていくと思いますので、育休を取ることに不安を感じないでほしいと思います。
K:育休をとるタイミングは、働き方を変えられるチャンスです。周りも自分も、半年以上準備する時間がありますし、当たり前だと思っていた働き方を考えるきっかけにもなります。だまされたと思って、取って欲しいなと思います。みんなが取得する制度になれば、普通のことになると思うので、みんなでとりましょう。
N:気楽にとって欲しいですね。取得するかしないかについては選択の自由だと思いますが、早稲田は取得しやすい組織だと思います。取得に際して生じる業務の見直しなど、大変なことがなくはないのですが、取得によるデメリットは、ほとんどありません。育休取得は、選択肢の一つとしてポジティブにとらえてほしいなと思います。
 T:メッセージありがとうございました。さて、育休を取得した方を対象とした調査では、取得後に早く帰るために業務効率化を意識するようになったり、同僚の家庭事情などに配慮する気持ちを持てるようになったりといった変化があったそうです。今後、育児や介護で時間的な制限を抱える職員が増加すると言われており、それに対応できる組織作りやマネジメントの重要性が着目されていますので、育休取得経験者が出ることは職場の意識改革の良いきっかけなのかもしれませんね。
T:メッセージありがとうございました。さて、育休を取得した方を対象とした調査では、取得後に早く帰るために業務効率化を意識するようになったり、同僚の家庭事情などに配慮する気持ちを持てるようになったりといった変化があったそうです。今後、育児や介護で時間的な制限を抱える職員が増加すると言われており、それに対応できる組織作りやマネジメントの重要性が着目されていますので、育休取得経験者が出ることは職場の意識改革の良いきっかけなのかもしれませんね。
今回の皆さんのお話から、育休を取ることが、自身にとっても、家庭にとっても、また職場にとってもメリットの多い結果となっているということがよくわかりました。当然、このことは大学にとっても良いことですので、今後男性の育休取得者がますます増えてほしいと思います。本日は、大変良いお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。
【座談会を終えて】
育休取得のきっかけは、「妻の負担を軽減するため」と答えた方が多く、4名全員が第二子以降の出産を機に、育休取得に踏み切っています。祖父母など親族に頼れる状況になかったということも共通していました。一人目の時の経験が、育休取得へ踏み切るきっかけになったのかもしれません。
職場が多忙で責任感の強い人ほど、「自分がいなければ職場の業務が回らない、迷惑をかけられない」という思いが強く、育休なんて取得できるわけがないと思いがちですが、育休を取得することで、職場の業務効率が向上したり、業務の優先順位が明確になったり、また担当業務を他メンバーと共有する機会にもなるようです。男性でも育休が取得しやすい職場環境としては、日頃から柔軟な体制を整えておくことが重要ですが、逆に育休を取得することで、そのような環境がつくられる面もあります。
この座談会が男性の育休取得について、当事者だけでなく職場全体で考えるきっかけになれば幸いです。
※記事の内容は座談会当時(2017年6月)のものです。
記事一覧