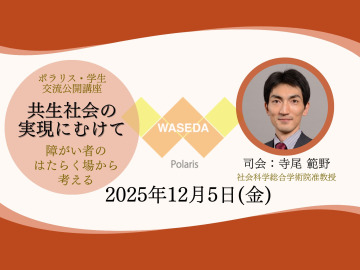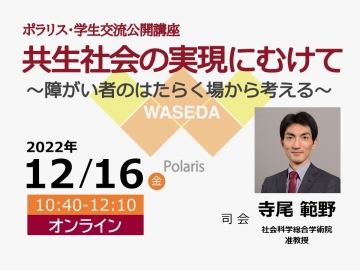介護のスペシャリストとして現場をよく知る、NPO法人パオッコ理事長の太田差惠子氏をお招きし、男性介護の特徴や傾向と、離職せずに介護を乗り切る考え方を学びました。
 冒頭、畑惠子早稲田大学男女共同参画担当理事より「Waseda Vision150における男女共同参画」について、女性の生き方・働き方の変革は男性に無関係だと考えるのではなく、共に変化していく姿勢が必要という話があり、「男女共同参画は女性だけの問題ではないように、男性介護も男性だけの話ではない。介護は、社会全体の課題であるから男女共に考えてほしい」と述べました。
冒頭、畑惠子早稲田大学男女共同参画担当理事より「Waseda Vision150における男女共同参画」について、女性の生き方・働き方の変革は男性に無関係だと考えるのではなく、共に変化していく姿勢が必要という話があり、「男女共同参画は女性だけの問題ではないように、男性介護も男性だけの話ではない。介護は、社会全体の課題であるから男女共に考えてほしい」と述べました。
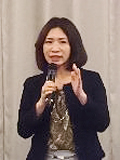 太田講師が、参加動機について挙手を求めて尋ねると「介護が差し迫っているため」「介護をテーマとした勉強・研究目的」がおよそ半数ずつに分かれていました。
太田講師が、参加動機について挙手を求めて尋ねると「介護が差し迫っているため」「介護をテーマとした勉強・研究目的」がおよそ半数ずつに分かれていました。
10年前までは女性が主な聴講者だったが、最近は、企業で講演をすると50代男性正社員の聴講者が多く、行政でも男性の姿を見かけるようになったことに時代の変化を感じているというお話から始まりました。
次に、男性が介護に直面した際の事例紹介があり、男性介護の特徴として「独身男性は、身軽だからと離職して実家に戻ってしまう」「男性は周囲に支援を求めず一人で抱え込む」傾向があると述べました。介護は2~3年で終わるものではなく10年以上にも渡る長期戦なので、離職したり抱え込んだりしないように、重要なのは情報と戦略、仕事の感覚でやるとうまくいくと要諦が示されました。
(1)チームを組む (2)ビジョンを練る (3)情報収集 (4)介護資金プラン (5)時間調整をポイントに挙げ、それぞれについて具体的な説明がありました。また、「93日間(法定日数)の介護休業の利用法を介護するための休業だと誤解している人が多いが、介護との両立の準備を行うための期間である」「介護資金は年金額によって負担感が異なる」「介護資金は親のお金でプランニングすべき。プランニングにあたって必要な親の資産状況について話をするためには普段の対話が大事である。その情報は兄弟間で共有しておくべき」等、ペアワークによる事例検討を交えながら、本格的な介護が始まる前に必要な準備についても語られました。
参加した感想として、「介護費用を親のお金で賄うことは相続でもらうよりずっと生きたお金の使い方であることや、様々な手立て、心構えをご紹介していただき大変有益だった。今度帰省した際に、まだ元気な親と話し合ってみようと思う」「多くの人々は介護に直面する立場になって初めて介護について考えることになるが、事前に様々な情報収集や戦略を立てることが重要だと改めて感じた」「事例を通して、介護する側が抱えている問題が分かった。両立支援制度や介護休業マイホーム借り上げ制度など、介護が必要となるときに重要な情報を知りとてもためになった」と声が寄せられました。