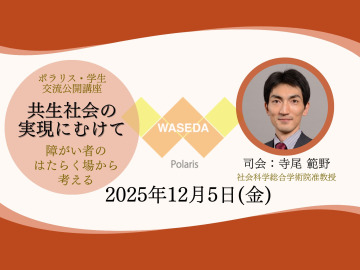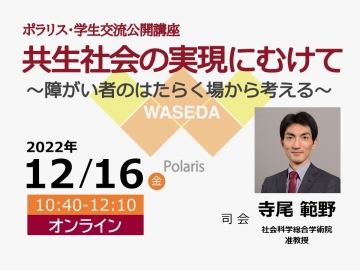「ストレスフルな出来事とのかかわり方を、マインドフルネス・ヨーガの実践を通して変えてみましょう」 講義と体験の実感をメンタルヘルスの向上に役立てていただこうと、本学文学学術院で教鞭を執られる相馬花恵講師をお迎えして、学生・教職員と幅広い年代層、男女36名が自らの身体をとおして心をほぐす、午後の2時間を過ごしました。
 齋藤美穂男女共同参画担当理事より、大隈重信侯の「男女複本位論」に拠り女性への教育機会を開放した本学の歴史、そして Waseda Vision 150に掲げられる男女共同参画の推進の重要性が説かれました。男女共同参画推進の拠点である推進室は、学業と子育て・介護等との両立支援、女性にとっても男性にとっても生きやすく力が発揮できるキャリア形成のための交流事業・セミナー等の開催を行っており、本講座をストレス対処のヒントにと意義を紹介されました。
齋藤美穂男女共同参画担当理事より、大隈重信侯の「男女複本位論」に拠り女性への教育機会を開放した本学の歴史、そして Waseda Vision 150に掲げられる男女共同参画の推進の重要性が説かれました。男女共同参画推進の拠点である推進室は、学業と子育て・介護等との両立支援、女性にとっても男性にとっても生きやすく力が発揮できるキャリア形成のための交流事業・セミナー等の開催を行っており、本講座をストレス対処のヒントにと意義を紹介されました。
I マインドフルネスの解説
 ストレスフルな出来事に直面すると、自動的にスイッチが入り、出来事についてぐるぐる考える「反すう」や、出来事から目をそむける「回避」といった「対処」をして、その結果、問題をさらに長期化・重篤化させやすくなることが指摘されています。そこで、よりよい対処法として、ストレスを普通に起こる大切な経験のひとつに扱い、ものごとをありのままで見る「マインドフルネス」について学び実践してみましょう、と相馬講師のお話が始まりました。
ストレスフルな出来事に直面すると、自動的にスイッチが入り、出来事についてぐるぐる考える「反すう」や、出来事から目をそむける「回避」といった「対処」をして、その結果、問題をさらに長期化・重篤化させやすくなることが指摘されています。そこで、よりよい対処法として、ストレスを普通に起こる大切な経験のひとつに扱い、ものごとをありのままで見る「マインドフルネス」について学び実践してみましょう、と相馬講師のお話が始まりました。
2つのキーワード「意図的に注意を払う」と「判断しない」が挙げられ、これが揃うと、ストレスとの関わり方が変わり、現実的・機能的・柔軟な反応の選択が可能になると解説された後、「マインドフルネス・ヨーガ」の体験に入ります。
マインドフルネスの効果について、「これまで、ストレスに対してぐるぐる思考で対処し、問題が未解決なまま長期化した結果、肩こりや頭痛等の身体症状が生じやすくなっていた。それが、不調の前触れとなる心身のささいな変化(緊張等)をはじめとする、『今ここ』での経験がより豊かになることで、症状が重篤化する前に、対処することができるようになる。今、自分ができることへの情報量が増える」と紹介がありました。また、主たる目的は、今の自分の心や身体の状態に気づき、自分に対する情報を増やすことですが、リラックスというおまけがつくこともありますと紹介され、期待も高まります。
II マインドフルネス・ヨーガの実践
 バスタオルを敷いてヨーガに移り、【呼吸】【山のポーズ】【ヤシの木のポーズ】【リンゴ取りのポーズ】【三日月のポーズ】、【観察】心と身体の状態を静かに観察する時間、そして【目覚めの体操】と45分の間、相馬講師の穏やかな教示と、「マリン缶」という揺すって水の音を醸すBGMにリードされ、外の暑さを忘れるゆったりとした時間が流れました。
バスタオルを敷いてヨーガに移り、【呼吸】【山のポーズ】【ヤシの木のポーズ】【リンゴ取りのポーズ】【三日月のポーズ】、【観察】心と身体の状態を静かに観察する時間、そして【目覚めの体操】と45分の間、相馬講師の穏やかな教示と、「マリン缶」という揺すって水の音を醸すBGMにリードされ、外の暑さを忘れるゆったりとした時間が流れました。
III マインドフルネス・ヨーガ実践後、気づきを促すアンケートと参加者間でのシェアリング
体験後、アンケートに答えることで、自身のふり返りと参加者間での活発なシェアリングがなされ、挙がった声に相馬講師が1つ1つフィードバックをされ、参加者間で共有していきました。アンケートには、自身の心の変化と身体の変化の、体験後の多くの気づきが記述され、心が解き放たれリラックスした感覚や、身体がほぐれたという体感が実感されていました。
「ぐるぐる思考がヨーガの間にも出てきたのだが」という質問には、「思考が飛んだということに気づいたら、『今ここ』に気づきを戻すチャンスが来たと思ってください。思考が飛んでいきやすい人ほどマインドフルネスを体験する機会が多く訪れます」という答えが出され、体験をして感ずる問いも多く出されました。
最後に、相馬講師から、参加された方と共有する時間の流れのなかで、教示する自分の声の様子も変わっていくのが解り貴重な経験だった、こうした心と身体の変化の感覚を大切にして、日常のストレス対処に取り入れてもらえると嬉しいと結ばれました。
参加した感想として、「ヨーガがゆっくりと心とからだに効く内容だった」、「シンプルなことで、思った以上に大きな落ち着きが得られた」、「講義と実践の両方がありよかった」、「講義の中にも“気づき”が多く日常生活に取り込みたいと思えた」、「身体と頭の対話ができた」、「身体感覚の変化に導かれるように、心の状態が変化していった」、「疲れがとれて食欲が出てきた」等多くの声が寄せられました。