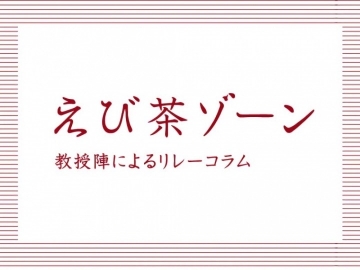スポーツとジェンダー:スポーツから社会が変わる?
2020年東京大会決定に際して
2013年9月7日、私は、国際スポーツ哲学会に参加するため、カリフォルニア大学フラトン校にいました。海外の研究仲間に突然“Congratulation!”と言われ、困惑したことを思い出します。実はちょうど、第125次IOC総会にて、2020年のオリンピック夏季大会に東京が選出されていたのでした。このエッセイでは、2020年東京大会がどのようなオリンピック・パラリンピックになるだろうかと思いをめぐらしつつ、スポーツとジェンダーの問題について考えてみたいと思います。
女性とスポーツ
近代オリンピックの幕開けは、1896年アテネ大会まで遡ります。第一回アテネ大会は、わずかに14カ国、しかも、男性選手しか参加していませんでした。翻って2012年のロンドン大会に目を向けてみましょう。参加国は204カ国にのぼり、大会に参加した女性選手は4,676名でした。また、五輪史上初めて全ての国、地域から女性選手が参加した大会にもなりました。このように、近代オリンピックの歴史を「女性スポーツ」という視点から捉えてみると、非常に大きな変化が見て取れます。
第一回アテネ大会において女性選手が一人もいなかったその理由は、何だったのでしょうか。この素朴な問いについては、さまざまな研究者がすでに指摘してくれています。たとえば、J.ルーカスら(1980)は、「クーベルタンは、大衆の面前で女性の競技を見せることは品位を下げると述べた」(p.92)と指摘しています。このように、近代オリンピックの第一回大会で女性選手が参加できなかった背景には、「スポーツという活動は女性らしさに合致しない」という見方があったことが読み取れます。
スポーツを哲学する:スポーツは女性らしくない?
ここで、少し立ち止まって考えてみたいことがあります。一つは、クーベルタンがスポーツから女性を遠ざけようとした理由に関する、「女性らしさ」とは何か?ということについてです。
その前に、まず、「~らしさ」とは何だろうか、という疑問が出てくるでしょう。「Aらしい」と述べる場合の「らしい」とは、辞書的に言えば助動詞になります。どのような働きをしているかと言えば、Aという体言につけて「ぴったりした状態」を示す機能を持っています。すなわち、あるものAの様態を示す言葉であり、Aの「性質」や「偶有性」とも言えるわけです。それは、あるものAの「本質」とは異なるものと理解できます。
それでは「本質」と「性質」の違いについて見てみましょう。アリストテレスという哲学者は、「本質(形相)」を、「AをAたらしめるもの」として、「性質」から区別しました。この区別に従えば、本質には普遍的な判断が求められますが、性質とは、あるものAの形容であるため、普遍的な判断とは限りません。多くのAに共通する特徴を経験的に観察し、抽出し、平均化されたものが「Aらしさ」として形づくられていくわけです。
そうであるならば、「女性らしさ」のその内実も、たまたま、いま、ここにいる女性たちに共通する特徴が集められ、平均化されたものが「女性らしさ」として作られていくわけです。ここで重要なことは、当然、この平均にはばらつきがあるということです。それでは、平均からずれた女性としての性質を、「女性らしさ」とは言わないのでしょうか。
確実に言えることは、本質ではなく性質を表す「女性らしさ」とは、相対的で可変的な概念であるということです。このように考えると、クーベルタンが考えていた当時の「女性らしさ」がスポーツにそぐわないという判断は、「女性らしさ」という確固たる何かがあって、それに基づいて判断されたというわけではなく、むしろ、彼が有していたその時代の「女性らしさ」という概念が、スポーツにそぐわないものとして主観的に認識されていたから、というのが実情でしょう。
近代オリンピックの歴史を振り返ってみるとわかるように、スポーツ世界においては女性の活躍の場が広がってきています。先のように考えてみると、「女性らしさ」をめぐる概念の変化が理由の一つとしてありえます。もちろん、別の理由もあるでしょう。「正義、公正、平等」ということが、社会における重要な理念となってきたことも関わっているでしょう。これらの問題については、また機会があればどこかで述べたいと思っています。
2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けて
2020年オリンピック・パラリンピック東京大会では、女性が初めて参加した第二回パリ五輪大会とは比べ物にならないくらい、女性選手の活躍が期待できるでしょう。そこでの活躍とは、単にメダルの獲得数を意味するものではありません。どのような立場の、どのような状況にある女性(選手、指導者、役員、サポーター)も、自分の意志に基づき自分の能力を発揮できるという意味です。たとえば、母親である女性選手などへのサポート等は、力を入れて取り組むべき問題ではないでしょうか(たんに母親らしさを理由に競技参画は難しいと判断されるならば、それは先にみたように、論理的に判断の誤謬である)。
2020年東京大会においては、メダルの有無だけが関心事となるのではなく、スポーツ文化の豊かな発展のためには、上記のような視点も忘れてはならないでしょう。そして、その取り組みが無形のレガシーとして構築されていき、よりよいスポーツ世界の創出につながるだけではなく、スポーツから社会を変えていく契機となることを願うばかりです。
参考文献
J.A.ルーカス、R.A.スミス著, 片岡暁夫編訳(1980)現代アメリカスポーツ史. 不昧堂出版.
執筆者プロフィール
 竹村瑞穂/早稲田大学助教
竹村瑞穂/早稲田大学助教
学歴;2011年筑波大学大学院人間総合科学研究科満期退学、2012年博士号(体育科学)取得。スポーツ倫理・哲学、スポーツ教育が主な研究分野。最近の論文は、竹村瑞穂(2014)競技スポーツにおける身体的エンハンスメントに関する倫理学的研究:より「よい」身体をめぐって. 体育学研究,59(1):53-66.
Mizuho Takemura(2013)Prolegomena to philosophical considerations on the issues of sports and gender: a critical consideration on sports and gender researches in Japan. The journal of the Philosophy of Sport,41(1):97-111. など。