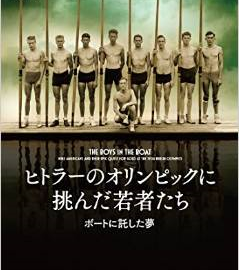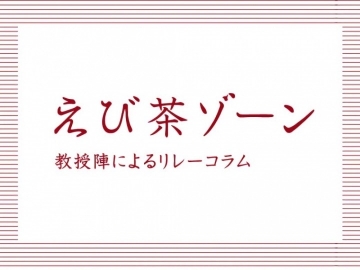“ボートに託した夢”
“ローイング(ボート漕ぎ)”は私のライフワークである。
私は高校、大学とボート部に所属していたが、十年ほど前から、大学時代の仲間とマスターズの大会を目指して週末、ボートの練習に励んでおり、国内はもちろん、海外の大会にも毎年参加してボートライフを楽しんでいる。ボート競技は大きな心肺体力と筋量が競技パフォーマンスに不可欠であり、体格の小さい日本人は欧米人に比べて圧倒的に不利である。世界マスターズ大会でも60歳代くらいまでは欧米クルーにほとんど歯が立たない。
しかし、70歳代、さらに80歳代になると互角に勝負でき、勝利する可能性も高くなる。それが日本人の健康長寿の証であるように思われる。
昨年は1956年にオリンピックが開催されたオーストラリアのメルボルン郊外のボートコースでの世界マスターズ・ボート大会に参加した。1956年といえば、ほぼ60年も前のことであるが、小学生であった私は、ラジオでメルボルン・オリンピックの水泳の実況放送を聞いた記憶がある。当時、金メダルが大いに期待された早稲田大学OBの山中毅選手が、オーストラリアの選手に敗れて銀メダルに終わったときの放送である。
1936年ベルリンオリンピック
その大会を遡ること20年、1936年にはヒトラーによるナチスが支配するドイツ・ベルリンで第11回オリンピックが開催されている。1936年のベルリンオリンピックでは聖火リレーが初めて行われ、映画「オリンピア」が世界中で上映され、大いに人気を集めたことでもよく知られている歴史に残る大会であった。この大会では、陸上競技では短距離のオーエンス選手(米国)の活躍が世界的に話題になったが、日本人選手の活躍もあった。“前畑ガンバレ!”のNHKラジオ実況放送で有名な平泳ぎの前畑秀子選手の金メダル獲得は当時の日本人を興奮の渦に巻き込んでいった。そのなかで、早稲田大学関係の選手としては、“友情のメダル”として知られている棒高跳びの西田修平選手が銀メダルを獲得している。
1930年代においては、世界的に最も人気があったスポーツは陸上競技であり、次に人気があったスポーツがボート競技である。とくに、エイト(8人の漕ぎ手と、舵をとるコックスの9人乗り)のレースは最も注目される種目であった。昨年、翻訳が出版された「ヒトラーのオリンピックに挑んだ若者たちーボートに託した夢」(早川書房)(原題:THE BOYS IN THE BOAT)は米国では2014年のノンフィクション部門でベストセラーになっており、映画化も決定されているとのことである。このエイトクルーの漕手とその家族、そしてコックス(舵手)を含む他のクルーメンバー、コーチ、ボートビルダーなどが生き生きと描かれている。近代オリンピックの創設者であるクーベルタン男爵がボート愛好者であったこと、またボート競技は英国や米国でもエリート階層のスポーツとして発展してきたことは多くの人々が知っている。しかし、1936年のベルリンオリンピックで金メダルを獲得した米国・ワシントン大学のエイトメンバーはいずれも労働階級の出身であり、学費の捻出にも苦労して学業を修めながら、すばらしいチームワークにより、全米のエリート校を撃破して、米国代表としてオリンピックに出場、そしてドイツ、イタリアなどの強豪をゴール直前で差して、金メダルを獲得したことはあまり知られていなかった。とくに、本書の決勝レースの描写は、まさに“手に汗握る”圧倒的な迫力があり、感動的である。本書は早稲田大学のボート部員のみならず、他の競技スポーツに取り組んでいる学生諸君にもぜひ読んでいただきたい作品である。本書から激動の20世紀を生き抜いた若者の姿を知ることにより、21世紀に生きる若いアスリート諸君が、これからの人生をどのように生きていくべきかを考える手掛かりが得られることだろう。
東京とオリンピック
ベルリンで開催された“ヒトラーのオリンピック”の次には東京でオリンピック開催が予定されており、当時の日本国内ではその開催と日本人選手の活躍が大いに期待されていた。しかし、1940年の東京オリンピックは世界大戦の影響で実施されなかった。東京でオリンピックが開催されたのは終戦からおよそ20年を経た1964年である。今年は戦後70年に当たるが、世界が平和であってこそ、スポーツを楽しむことができるということを私たちは決して忘れてはならないと思う。2020年の東京オリンピック・パラリンピックまであと5年であるが、そのときに、世界が平和であり、現在、早稲田大学で学びながら競技スポーツに励んでいる学生諸君が、日本の代表選手として活躍することを大いに楽しみにしている。
私は2020年にはすでに大学を退職しているので、ボート競技を中心に東京オリンピック・パラリンピック三昧できることを楽しみにしている。そして、いつの日にか世界マスターズで勝利することを夢見て、これからもボートを愛し、楽しんでいきたいと思う。
執筆者プロフィール
早稲田大学アクティヴ・エイジング研究所所長。専門は運動生理・生化学、スポーツ栄養学。所属学会は、日本体育学会、日本体力医学会、アメリカスポーツ医学会など。