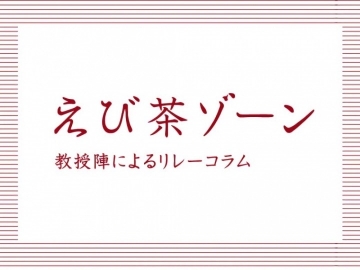大学の体育各部でスポーツをしている選手は恵まれていると思うことがよくあります。理由は、大学がスポーツを良いものだと思い、支援しているから。
体育各部の選手は、ほとんどが中学高校で運動部に所属していたと思いますが、中学高校も大学と同じようにスポーツを支援しているので、支援に違和感がないというか、それが当たり前のことだと思っている。しかし、すべての、とまでは言わなくても、多くのスポーツが学校のスポーツと同じように経済的、精神的に支援されているわけではありません。同好会は練習場所の確保に苦労し、地域スポーツクラブの運営費は「自腹」です。日本は企業スポーツが盛んな国で、オリンピックや世界選手権の代表が企業スポーツから多く輩出されていますが、その企業スポーツも、1990年代のいわゆるバブル崩壊、あるいは2008年のリーマンショックによって、すくなからぬ数のチームが廃部しています。
このような環境変化を背景として、企業スポーツに係わる人たちは、自分たちが企業でスポーツをしていることの価値を、真剣に考えるようになりました。その過程では、CSR(企業の社会的責任)という新しい言葉に飛びついてみたりという、少し笑える展開もあったのですが、現在は企業スポーツの価値というと
- ブランディング(広告宣伝価値)
- 社員や取引先の一体感や士気高揚
- 地域社会への貢献(工場など事業所のある地域でのスポーツ教室の開催など)
が基本的なものだと考えられています。
とはいえ、もし企業スポーツが普遍的に、つまりどの企業にとっても価値のあるものだと認識されているなら、スポーツを保有しようとする企業はもっと多いはずです。しかし実際にはそうなっていません。この理由としては、第一に、上に掲げたような価値を、必ずしも必要としない企業もあるからなのでしょう。たとえば、自社としてのブランドを持たない会社、企業イメージの向上を必要だと感じない会社、社員の一体感形成のための手段を他に持っている会社、工場のない会社などがこれに該当します。
そして第二の理由は、スポーツには価値がある、スポーツは企業にとっての価値を持ち得るということを知らない会社があるということだと思います。これはスポーツに限らず、一般的な製品やサービスでも同じです。買ってみたり、使ってみたりしないとその良さがわからない。当たり前と言えば当たり前なのでしょう。楽天はプロサッカーに次いでプロ野球のオーナーになりました。DeNAは、プロ野球のつぎがランニングです。これらの企業は、一つめのオーナーシップでスポーツの価値を理解したから、つぎのスポーツを求めたということができるように思います。
さて、では、大学の体育各部生は、このような恵まれた環境の下で、WAP(早稲田アスリート・プログラム)が唱えるところの「スポーツと修学の両立」を追及し、実現していけばそれでいいのかというと、私はちょっと違う、甘いんじゃないかと思っています。「スポーツと修学の両立」なら、中高生の目標にもなり得る。それができたらよかったねというのは、中高生レベルの話だということであり、大学生はオトナなので、加えて、何かすべきことがあるんじゃないかと考えるのが当然でしょう。
では、何を加えればよいのか。私は、スポーツの価値という、世の中では必ずしも了解されていないものを伝えるということではないかと思っています。冒頭に述べたように、大学はスポーツに価値があると考えている。だから体育各部と部員が支援されている。そうであるなら、スポーツに価値があると考える人、学校、企業などが増えていくことは、間違いなく好ましいはずなので、そうなるために何かできないか、何ができるだろうかと考えてみて欲しいと思うのです。
参考までに、スタンフォード大学名誉教授の青木昌彦先生(一応解説すると、経済学の世界的権威です。)が、日本経済新聞2014年1月6日の「経済教室」に寄稿された文章の一部を紹介してみたいと思います。ロンドンオリンピックについてです。
- 英国の成功は、資金を施設のみに投資するのではなく、エリート選手を発掘し、育て、支える「チームのあいだの競争」を刺激する戦略をとったこと、そして「チーム力」とは、「コーチ、スポーツ医学・科学、競技・競演に現れるライフスタイル」など多様な要素からなり、それは産業政策、経営戦略にとっても示唆に富む。
- 日本が「予想外」(?)の成績をあげえたのも、水泳、体操、サッカーなど、若いうちから選手を発掘し、裏方の人々を含めたチーム力の競争のあった種目だった。逆に、権威的な管理組織としごきによって根性をたたき込むという伝統的な選手育成法にこだわった種目は、期待された成績を残せなかった。
- こうしたことは果たして、スポーツに限られる話だろうか。そうではなく、より広い含意が、経営にも、教育、研究界にもあると思う。潜在的なエリートの足を引っ張り、変わり種をのけ者にするのでなく、彼らをサポートし、競争させ、認め合うシステムと雰囲気、そうしたことが、活動人口が縮小する日本を活性化することになる。
重要なのは、スポーツの価値が、スポーツの中にとどまるものではないというところでしょう。青木先生はスポーツ関係者ではないので、より広い視野から、スポーツの価値を見出してくれている、そんな気がします。体育各部生の多くは、大学を卒業するとスポーツから離れるのだろうと思います。そうなって欲しくはないのですが、それが現実でしょう。とはいえ、ではスポーツから離れたらスポーツの価値を伝えられなくなるのか。そうではない。スポーツは、社会や産業に対して、伝える意味のあるものを多く含んでいる。それを伝え、実践していくのが、大学でスポーツをしていた人々の使命なのではないかと思うのです。
執筆者プロフィール
1955年生まれ。東京大学大学院修士課程修了。三菱総合研究所主席研究員を経て現在早稲田大学スポーツ科学学術院教授。専門はマネジメント、スポーツマネジメント