- ニュース
- 東アジア国際関係研究
東アジア国際関係研究
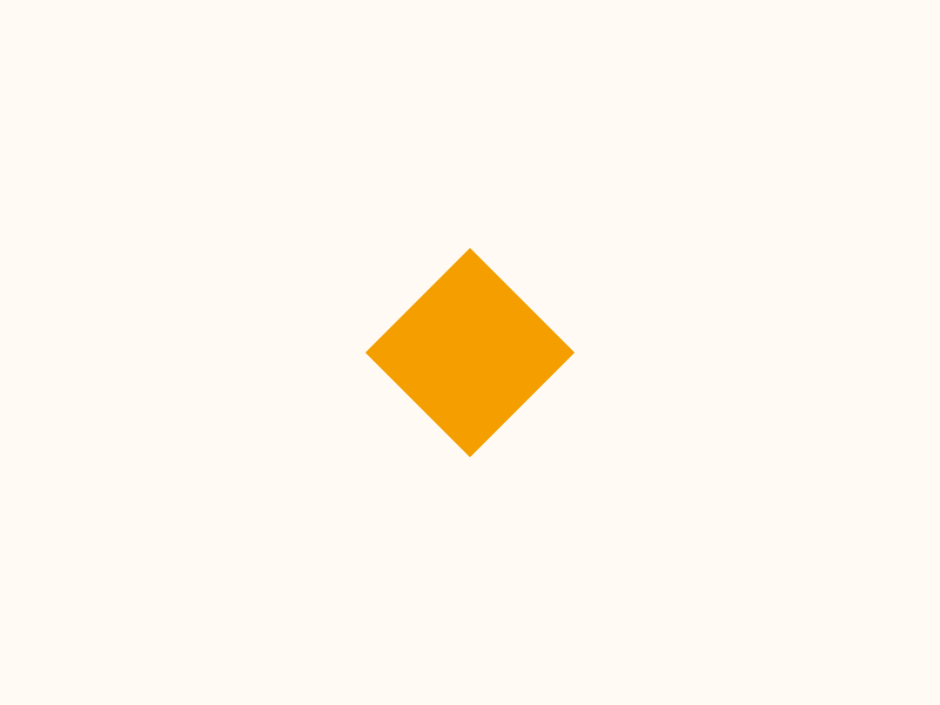
- Posted
- Tue, 17 Jun 2025
概要
地域・地域間研究機構の傘下にあった本研究所は、2017年度以降、「和解に向けた歴史家共同研究ネットワークの検証」(基盤研究A、劉傑代表)「東アジア知のプラットフォームの現状に関する研究」(基盤研究A、平野健一郎代表)を展開し、一連の研究成果を公開してきた。歴史家ネットワークに関する研究は、日本、中国、台湾、韓国の歴史学者に対するインタビューを実施し、彼らが研究活動と交流活動のなかで構築した研究者ネットワークの実態、とそのネットワークが国家間の和解に果たした役割を検証した。また、歴史の研究法、歴史と政治の分離法、歴史家共同体の構築法の三つの方法論を提起し、「和解学」に貢献する歴史学のあり方を提案した。
一方、「知のプラットフォーム」に関する研究は、二つの問題を考察した。第一に、東アジアにおいて①国境を超え、②学問領域を超え、③世代を超え、④研究者と実務者の境界を超えるような、知識人の「越境的ネットワーク」がどのように形成されたのか、第二に、そうしたネットワークがどのような知(「越境知」)を生み出したのか、である。また、国境に沿って亀裂が走る東アジアに平和と安定をもたらす可能性を、こうした知のネットワークと知のプラットフォームに見出そうとした。
これまでの研究成果を踏まえて、本研究所は、「越境知」が東アジアの国際関係に果たす役割についてさらに研究を深めていくことを目的とする。 例えば、権威主義の政治体制下の研究者のネットワークが生み出す「越境知」の中味とその影響力は未だに解明されていない。また、「国際派」としての彼らの基礎的なデータがなく、その活躍は明らかにされていない。これらのことを解明すると共に、「アジア大学リーグ」という先端社会科学研究所を中核とするプラットフォームを発展させ、人文科学と社会科学を融合させた「現代アジア学」「現代日本学」の研究拠点を目指す。
これまで、アジアの10以上の大学の研究者が参加する「東アジア人文社会科学フォーラム」を2回主催し、文化の交流と共生について議論を深めた。 また、中国、台湾、韓国の大学、研究機関と毎年定期的に共同シンポジウムを開催し、東アジアにおける知のネットワークのハブとしての機能を果たしてきた。 今後もこのような共同研究の活動を継続し、社会科学総合学術院と早稲田大学のアジア研究の発展と知的交流に貢献する。
構成メンバー
代表者:劉傑
兼任研究所員:山田満、早田宰、堀芳枝、奥迫元、チンロ、浅野豊美
招聘研究員
- 羽場久美子(神奈川大学教授)
- 加藤恵美(帝京大学外国語学部准教授)
- 鄭成(兵庫県立大学環境人間学部教授)
- 駱豊(二松学舎大学、多摩大学非常勤講師)
- 野口真広(大妻中学高等学校常勤講師)
設置期間
2025年4月1日~2030年3月31日
IASS研究プロジェクト一覧
| 研究費種目 | 代表者名 | 課題名 | 年度 |
| 科研費基盤B | 羽場 久美子 | 欧州とアジアの境界線をめぐる紛争緩和と格差是正———和解と共同発展 | 2022-2026 |
| 国際共同研究加速基金(国際先導研究) | 浅野 豊美 | 普遍的価値と集合的記憶を踏まえた国際和解学の探究 | 2023-2029 |
| 科研費基盤C | 加藤 恵美 | 川崎市「ヘイトスピーチ禁止条例」の成立過程の研究」 | 2023-2025 |
| 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化B) | 山田 満 | 資源管理のための伝統的制度の役割と持続可能性 との関係 | 2022-2025 |
| 科研費基盤C | 早田 宰 | 自助による住宅政策の理論と展開〜グループセルフビルド住宅の国際比較 | 2022-2024 |
