- ニュース
- 【開催報告】2022年度第1回スタディセミナーが開催されました
【開催報告】2022年度第1回スタディセミナーが開催されました

- Posted
- 2022年6月15日(水)
スタディセミナー「ドイツとスイスの事例から考える先端科学技術の問題圏」
主 催: 早稲田大学比較法研究所
日 時: 2022年6月2日(木) 16:30~18:00
場 所: オンラインによる開催
講 師: 高岡佑介教授(早稲田大学法学学術院)
参加者: 50名(うち学生27名)
2022年6月2日、第1回比研スタディセミナーが開催されました。講師は高岡佑介・法学学術院教授、講義タイトルは「ドイツとスイスの事例から考える先端科学技術の問題圏」でした。司会は大橋麻也・比較法研究所幹事が務め、高岡教授のレクチャーの後、質疑応答がなされました。
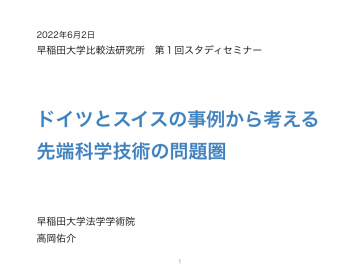
高岡教授はまずエンゲルスの文章を参照し、新たなテクノロジーの登場は、周りの世界を変えるのみならず、人間の思考そのものを書き換えるものでもあると議論されました。つまり、これまでは変えられないと考えられてきた身体や精神の状態を、新たなテクノロジーによって変えることができるということは、私たちの考え方をも変えられてしまう(変更不可能性でなく、変更可能性が、私たちの思考の新たな出発点や基盤となってしまう)ということです。
高岡教授は、テクノロジーに関するこうした考え方を出発点としつつ、ドイツやスイスにおける合成生物学とこれに関連する法規制について、研究報告をされました。
そもそも合成生物学とはどのようなものなのでしょうか。何かを理解する際、我々は、それを部品に分解し調べることで理解しようとすることもあれば、その部品を集めてきてそれを組み立てることで理解しようとすることもあります。合成生物学とは後者のアプローチをとることで、生物・生命とは何かなどの問題に取り組むものです。
合成生物学の知見を活かし、「ゼノボット」、いわば「生きている機械」が作り出されています。これは、様々な動物細胞を組み合わせつつ、それをコンピューター・アルゴリズムによって制御することで組み立てられた存在です。法はこれをどのように取り扱うべきでしょうか。また、この開発にまつわる「特許」などをどのように考えるべきでしょうか。これらの問題について高岡教授は、ドイツやスイスの取り組みを参照しつつ、動物保護法の蓄積を延長する形でゼノボットに法的位置づけを与えようとするアプローチや、特許法における遺伝子技術の位置づけに引き付けて特許の問題を考えようとするアプローチを紹介・検討されました。
報告後の質疑応答では、生物とそうでないもの、あるいは法主体とそうでないものの境界線として、既に生物・法主体として認められた存在からそのように承認されることを基準とするアプローチが、議論されました。
(文:松田和樹・早稲田大学比較法研究所助手)
参考
開催案内

