- ニュース
- 【開催報告】<比研共催講演会>「通貨を巡る国際シンポジウム 」6/7(金)が開催されました
【開催報告】<比研共催講演会>「通貨を巡る国際シンポジウム 」6/7(金)が開催されました

Dates
カレンダーに追加0607
FRI 2024- Place
- 早稲田キャンパス8号館B101教室
- Time
- 18:30-20:00
- Posted
- Mon, 10 Jun 2024
比研共催講演会:「通貨を巡る国際シンポジウム」
共 催:早稲田大学比較法研究所、国際商事研究学会、国際取引法学会国際契約法制部会
日 時:2024年6月7日(金)18時30分~20時30分
場 所:早稲田キャンパス8号館B101教室およびZoom
世話人:久保田隆(早稲田大学法学学術院教授、早稲田大学比較法研究所研究所員)
参加者:103名(うち学生78名)
暗号資産やステーブルコイン、中央銀行デジタル通貨(CBDC)など、通貨のデジタル化の進行に対応して法も新たな課題に果敢に取り組んできました。そこで、最先端を担う研究者と実務家を国内外からお招きし、フロアやZoomに100名余りの学者(法学・経済学・暗号学等)・実務家および本学学生を交えて徹底的に議論しました。
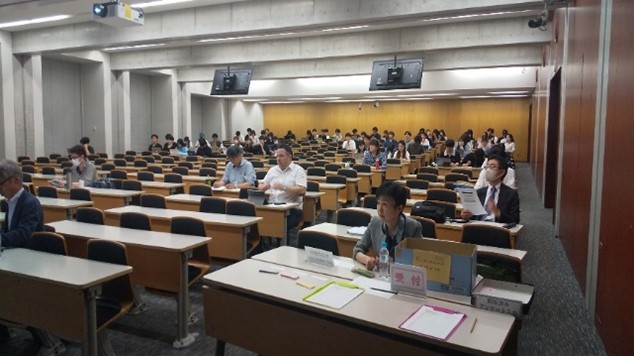 はじめに経済学者の鈴木純一武蔵野大学教授(国際商事研究学会会長)から挨拶があった後、第一報告は憲法学者のWill Bateman豪州国立大学教授が「Legal Teder and the Micro Structure of Financial Stability」(法定通貨と金融安定性のミクロ構造)と題する英語報告を行い、①法定通貨には裁判所における弁済機能(=tender)だけでなく金融システムにおける信用供与の機能があるが、②法定通貨を伴わない金融システムはモラルハザードを生じるため、CBDCは法定通貨として発行されるべきと主張しました。第二報告は国際金融法学者の久保田隆早稲田大学教授が「中央銀行デジタル通貨(CBDC)と経済安全保障を巡る法的視座」と題する日本語・英語報告を行い、①通貨は経済安全保障に含まれ、国内外で先行研究は乏しいが、従来の金融法に比べて憲法と国際公法の分析が必要になり、②CBDC導入に際しては日銀に議会・国民への説明責任が生じる(例:CBDC開発費用を巡り憲法83条で議会説明責任が存在)ほか、④BISと日銀等が推進するプロジェクト・アゴラが成功しCBDCクロスボーダー取引基盤が成立したら、これにIMFも協力して国際法における通貨や通貨主権の法整備に繋がるソフトロー合意をコード化すべきと提案しました。第三報告はブロックチェーンに詳しい真鍋泰治公認会計士が「暗号資産を巡る制度上の問題」と題して日本語・英語報告を行い、①ステーブルコインの必要性をミクロ・マクロ両面から検討し、②貨幣の3機能のうち交換機能の拡張について、資金決済法上の位置づけを細かく検討した上で、③中央管理者が前払・同時払・後払式を管理する前提で成立する日本のステーブルコイン規制は、分散型のブロックチェーンでビジネスが展開する今後は機能しにくくなるのではないかとの問題提起を行いました。
はじめに経済学者の鈴木純一武蔵野大学教授(国際商事研究学会会長)から挨拶があった後、第一報告は憲法学者のWill Bateman豪州国立大学教授が「Legal Teder and the Micro Structure of Financial Stability」(法定通貨と金融安定性のミクロ構造)と題する英語報告を行い、①法定通貨には裁判所における弁済機能(=tender)だけでなく金融システムにおける信用供与の機能があるが、②法定通貨を伴わない金融システムはモラルハザードを生じるため、CBDCは法定通貨として発行されるべきと主張しました。第二報告は国際金融法学者の久保田隆早稲田大学教授が「中央銀行デジタル通貨(CBDC)と経済安全保障を巡る法的視座」と題する日本語・英語報告を行い、①通貨は経済安全保障に含まれ、国内外で先行研究は乏しいが、従来の金融法に比べて憲法と国際公法の分析が必要になり、②CBDC導入に際しては日銀に議会・国民への説明責任が生じる(例:CBDC開発費用を巡り憲法83条で議会説明責任が存在)ほか、④BISと日銀等が推進するプロジェクト・アゴラが成功しCBDCクロスボーダー取引基盤が成立したら、これにIMFも協力して国際法における通貨や通貨主権の法整備に繋がるソフトロー合意をコード化すべきと提案しました。第三報告はブロックチェーンに詳しい真鍋泰治公認会計士が「暗号資産を巡る制度上の問題」と題して日本語・英語報告を行い、①ステーブルコインの必要性をミクロ・マクロ両面から検討し、②貨幣の3機能のうち交換機能の拡張について、資金決済法上の位置づけを細かく検討した上で、③中央管理者が前払・同時払・後払式を管理する前提で成立する日本のステーブルコイン規制は、分散型のブロックチェーンでビジネスが展開する今後は機能しにくくなるのではないかとの問題提起を行いました。
 これら3報告に対し、予定質疑として大矢伸EBRD東京事務所長から更に掘り下げたコメントと予定質問がなされ、各報告者がこれに返答し、活発な質疑が行われた。末尾に久保田隆が早大教授が早稲田大学と国際取引法学会を代表して閉会の辞を述べ、閉会しました。
これら3報告に対し、予定質疑として大矢伸EBRD東京事務所長から更に掘り下げたコメントと予定質問がなされ、各報告者がこれに返答し、活発な質疑が行われた。末尾に久保田隆が早大教授が早稲田大学と国際取引法学会を代表して閉会の辞を述べ、閉会しました。
(文:久保田隆・比較法研究所研究所員)

