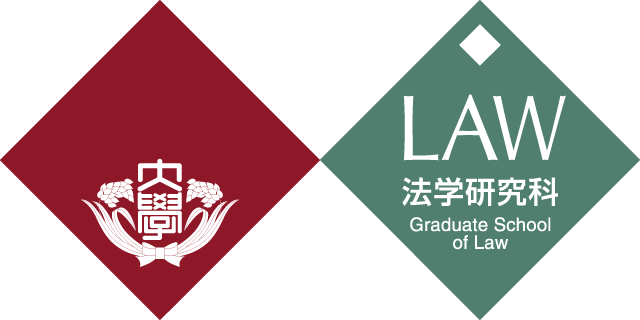- ニュース
- 高木 一嘉
高木 一嘉
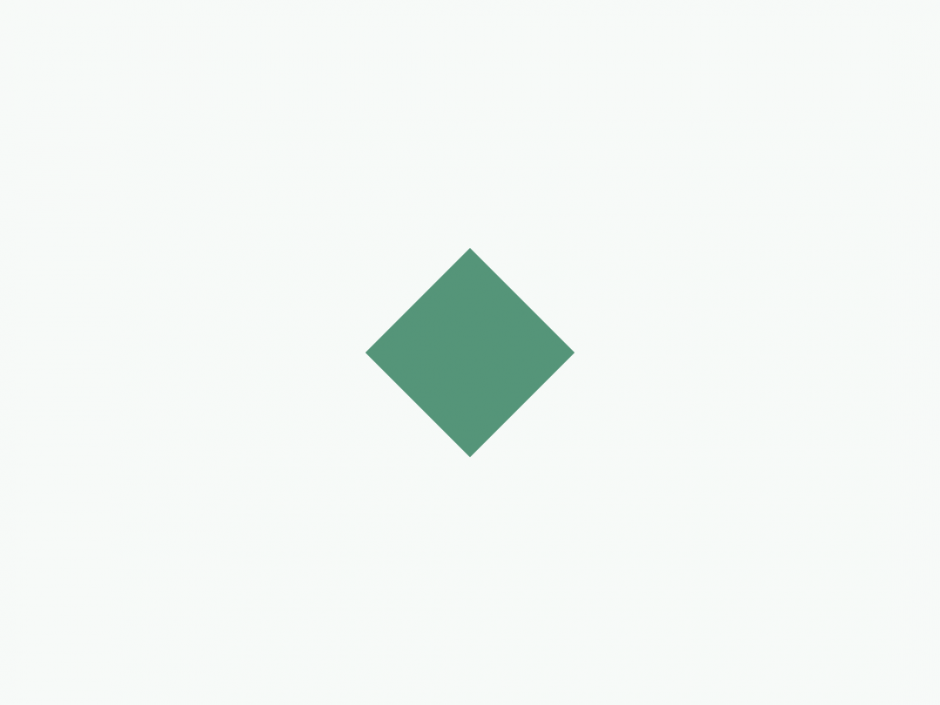
- Posted
- Thu, 16 Oct 2014
実務法曹のスキル向上と、専門分野形成に不可欠となる制度
高木 一嘉
弁護士。平成17年度、18年度委託履修生。
私は、個人事務所を経営している弁護士です。早稲田大学大学院法務研究科には、平成17年度から18年度にわたり委託履修生として学びにきていました。17年度は工業所有権法、競業法、知的財産紛争処理法、18年度は工業所有権法、著作権法を選択しました。
私は以前から、日弁連で知財法の自主研修や発明協会で講義を受けるなどして、独学で勉強していたのですが、知財法全体について正しく理解を深めることはなかなか困難で、しっかりとした基礎を身につけるには大学での講義しかないと日頃から思っていました。たまたま日弁連が早稲田大学法務研究科の委託履修生募集を広報していたのを知り、迷わず応募することにしました。早稲田での講義はいずれも新鮮で、毎週講義のある日が楽しくてしようがないという感じでした。既知の知識も講義を受けることでさらに新鮮な知識に衣替えし、新たに受けた知識は記憶の定着度や理解度が高く、生きた講義ならではの効果があったと思います。
しかも、この委託履修制度には望外の派生効果がありました。1つは、著作権の共有を巡る紛争に関して、受講したての知識を活かして訴訟を提起し無事解決することができました。もう1つは、17年度の特許法と競業法の講義で1人の弁護士の委託履修生と知り合いになりました。“同好の士”という感じで始めた彼とのつきあいは、弁理士や弁護士仲間との知財全般にわたる判例研究会仲間という形で現在も続いています。
早稲田の委託履修制度は、他の法科大学院には存在しないようですが、弁護士実務でのスキル向上や専門分野形成のための能力向上には極めて有用であり、理論を実務で活かすためにも、弁護士がこれから必要とする不可欠な制度となるだろうと思います。今後は、知財法だけでなく、会社法やその他諸分野の法律についても委託履修制度の適用・拡充をぜひ図っていただきたいと願っています。司法試験合格のための法科大学院という位置づけだけではなく、実務家となった以降も、長い生涯に亘って研鑽し続けなければならない能力向上の研修拠点として、法科大学院がフルに活用できるようになることを切にお願いしたいと思います
私は以前から、日弁連で知財法の自主研修や発明協会で講義を受けるなどして、独学で勉強していたのですが、知財法全体について正しく理解を深めることはなかなか困難で、しっかりとした基礎を身につけるには大学での講義しかないと日頃から思っていました。たまたま日弁連が早稲田大学法務研究科の委託履修生募集を広報していたのを知り、迷わず応募することにしました。早稲田での講義はいずれも新鮮で、毎週講義のある日が楽しくてしようがないという感じでした。既知の知識も講義を受けることでさらに新鮮な知識に衣替えし、新たに受けた知識は記憶の定着度や理解度が高く、生きた講義ならではの効果があったと思います。
しかも、この委託履修制度には望外の派生効果がありました。1つは、著作権の共有を巡る紛争に関して、受講したての知識を活かして訴訟を提起し無事解決することができました。もう1つは、17年度の特許法と競業法の講義で1人の弁護士の委託履修生と知り合いになりました。“同好の士”という感じで始めた彼とのつきあいは、弁理士や弁護士仲間との知財全般にわたる判例研究会仲間という形で現在も続いています。
早稲田の委託履修制度は、他の法科大学院には存在しないようですが、弁護士実務でのスキル向上や専門分野形成のための能力向上には極めて有用であり、理論を実務で活かすためにも、弁護士がこれから必要とする不可欠な制度となるだろうと思います。今後は、知財法だけでなく、会社法やその他諸分野の法律についても委託履修制度の適用・拡充をぜひ図っていただきたいと願っています。司法試験合格のための法科大学院という位置づけだけではなく、実務家となった以降も、長い生涯に亘って研鑽し続けなければならない能力向上の研修拠点として、法科大学院がフルに活用できるようになることを切にお願いしたいと思います