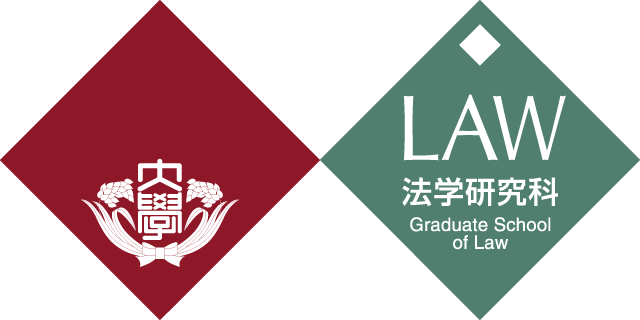- OB・OGの声
- 橋本 小智:OB・OGの声
橋本 小智:OB・OGの声
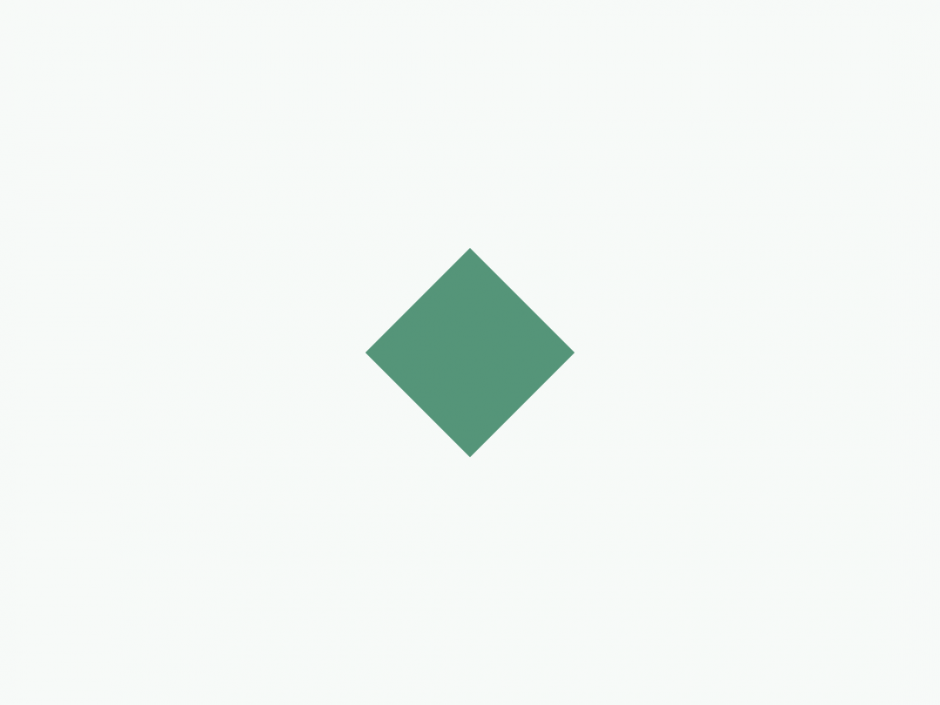
- Posted
- 2014年11月4日(火)
エントリーシートの作成は早めに。募集が告知されたら、すぐエントリーを!
橋本 小智[3年標準課程] 
- 2009年
- 同志社大学法学部法律学科卒業
早稲田大学大学院法務研究科入学[3年標準課程] - 2012年
- 法務研究科修了/司法試験合格/新66期司法修習生
- 現在
- 弁護士登録/弁護士法人大江橋法律事務所
ご自身の就職活動を振り返り、その流れについて教えてください。
就職活動を始めたのは、司法試験終了後の6月頃からです。11月末に修習が始まってからは、地方(奈良修習)だったこともあり、あまり就職活動をしていなかったのですが、企業の説明会や法務部の募集にエントリーしたり、修習地近辺の弁護士会主催の就職説明会に参加したり細々と就職活動を続けていました。関西は東京に比べて一般公募が少なく、弁護士会内で、その県の修習生だけに募集がかかることが多いので、その地方で就職したい場合は有利だと思います。逆に東京で就職したい場合は、修習を休んで面接に行かなければならないので、時間的にも費用の面においても大変でした。
最終的には、修習中の7月頃に東京の公募の事務所を2か所ほど受け、そのうちの1つから内定をもらいました。
就職情報はどうやって収集されていましたか。
私は、アットリーガルとひまわり求人求職ナビのメーリングリスト、京都弁護士会の就職活動メーリングリストに登録していました。また、弁護士会主催の合同就職説明会には参加するようにしていました(東京、大阪、兵庫、京都)。その他、修習先の弁護士会内での募集をチェックしたり、修習先の教官や友人から紹介していただくこともありました。
就職のために、在学中に取り組んだことはありますか。
また、その取り組みが就職活動や現在の仕事にどう影響しましたか。
ロースクール在学時から就職のことも見据えて、エクスターンシップには積極的に参加していました(2年次と3年次)。また、企業法務の実務基礎や金融法特論など、実務に関連する授業を積極的に受講しました。さらに授業でお世話になった弁護士の先生のご紹介で、ある会社の法務部が主催しておられる勉強会に参加させて頂いたり、事務所訪問をさせて頂いたりしました。このように積極的に実務家の方のお話を伺う機会を持てたことで、弁護士にどのような仕事が求められているのかを具体的に知ることができ、自分が弁護士としてどのように仕事をしていきたいかのイメージを持つことができました。そしてそのことは、就職活動において、事務所を選ぶ際、また志望理由を書いたり面接を受ける上でとても役に立ちました。
現在の仕事においては、民法や会社法、民事執行・保全法の内容は、そのまま役に立っています。具体的には、相談を受けた時に、これら実体法の知識を頼りに問題点を見つけ出し、分からないところは調べて依頼者に回答することになります。そのため、基本的な問題点は網羅的に頭に入っていないと、どこに問題があって、何を調べればいいのかが分からず苦労することになります。特に民法は本当に基本なので、もっとしっかり勉強しておけば良かったと思うことも多々あり、日々勉強の毎日です。
後輩へのアドバイスをお願いいたします。
エントリーシートは色々な友人に読んでもらい、アドバイスを受けながら、何度も書き直しました。自分では気付かない点を指摘されながら書き直す中で、客観的に自分を見つめ、自分のやりたいことや適性などが見えてきました。これから就職活動をする方には、ぜひ早いうちから丁寧にエントリーシートの作成をされることをお勧めします。またエントリーシートを書くのに時間がかかり応募が遅くなることが多々あったのですが、そのような事務所からはまず良い返事がきません。たくさん応募がある中で面接に呼んでもらうためには、募集が出たらできるだけ早く(できれば1週間以内に)エントリーすることを心掛けてください。
また、当然のことですが、面接前には必ずその事務所や企業のことをホームページなどでよく調べて、事務所や企業に対する質問事項などを準備するよう心掛けて下さい。そして面接の後は、何を訊かれて何を答えたかを書き留めておくことも大切です(これを怠ると、同じ会社の次の面接の時に全然違うことを答えてしまう危険性があります)。最終的には、就職先の先生との相性もあるかと思いますが、自分が弁護士としてどのように仕事をしていきたいか、ということを上手く面接で伝えることが大切です。
履歴書の書き方、写真も重要な選考ポイントとなるようです。とは言っても、それほど特別なことではなく、履歴書は読みやすく書く(字の大きさ、文章の読みやすさ、分量など)、写真はきちんと写真屋さんで撮る、といったことを心掛けていれば大丈夫です。