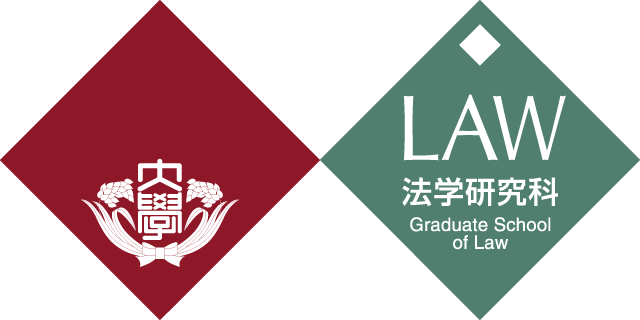- ニュース
- 上田 明彦
上田 明彦
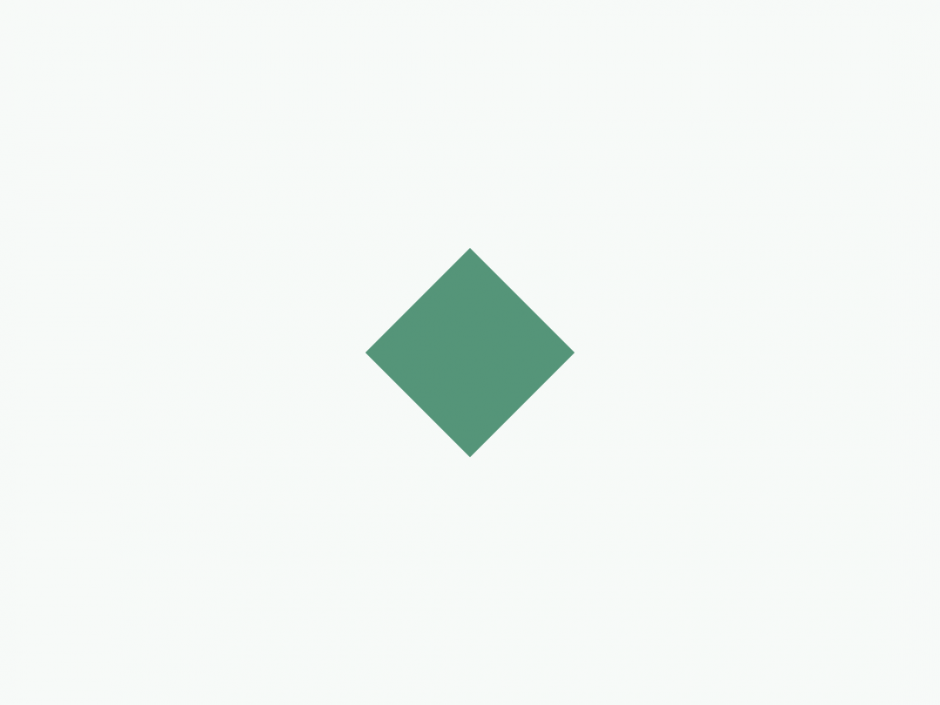
- Posted
- Thu, 16 Oct 2014
専門分野が高い次元で学べる、刺激となった早稲田での学修体験
上田 明彦
信州大学医学部卒業。大学病院医局・市中病院勤務を経て、平成19年上智大学法科大学院修了。
私は、相互科目履修生として早稲田大学大学院法務研究科で学ぶことができるとのアナウンスがあった時、即座に決意しました。私の場合は、医師という職業柄、以前から医療過誤訴訟については強い興味と関心をもっていたのですが、今までは医事法の教科書や判例百選を斜めに読んだり、雑誌の記事を眺めたりするくらいのもので、系統立てて学ぶような機会も経験もなかったので、これは好機であると考えたのです。また、お互いの大学の距離が比較的近く、昼休みを移動に利用して上智大学の午後の講義に十分間に合うので履修も容易でした。
私法的な視点から医療に関する法律問題を扱う「医事法I」の講義は、先端的分野であることもあって、いわゆるソクラティックメソッドの形式よりも講義形式が主体となりがちでしたが、そこからは多くのことが得られたように思います。これまで自分ひとりで判例を読んでいても、判例相互の関係を読み解くことはやや困難でした。実のところ、医療過誤訴訟の分野は、単に損害賠償や不法行為の延長であって、私は医療過誤訴訟に特有の考え方などはないのではないかとさえ考えていました。しかし、多数の判例をみていく講義の中で、判例の変遷やその背景など、判例集や教科書には表現されない多くの部分を補充することによって、初めて枝葉をつなぐ幹のようなものが見えてきました。これは、早稲田で体系的な講義を受けなければ得にくいものであったといえます。
また、医療過誤訴訟を専門に手がける実務家教員の講義のなかでは、実務の様子を学びながら弁護士の強い思いも伝わってくるような貴重な話を聞くこともでき、非常に良い刺激となりました。