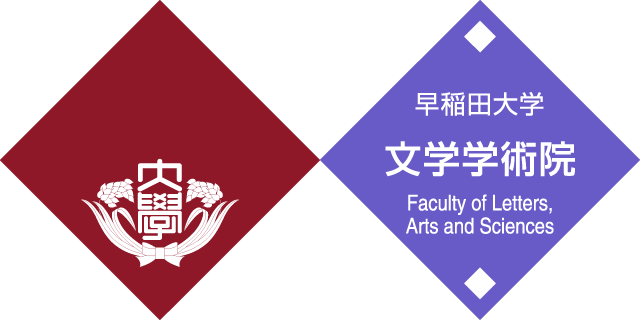- 学生報告書
- 草野勝 文学研究科 日本語日本文学コース
草野勝 文学研究科 日本語日本文学コース
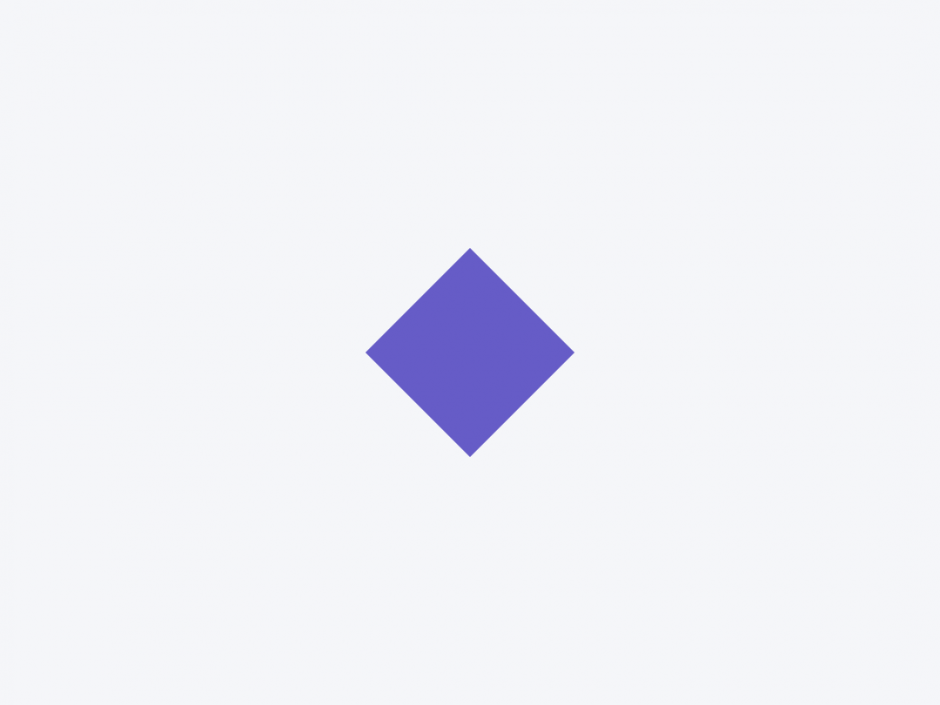
- Posted
- Tue, 19 Dec 2023
ブリティッシュコロンビア大学ワークショップ参加報告
博士後期課程3年 草野勝
2023年11月23日から26日(日本時間)にかけて、UBC(ブリティッシュコロンビア大学)に滞在した。その成果を報告する。
滞在は実質2日間で、その間のプログラムは第一にUBCの学内施設の見学、第二にUBC所蔵の飛鳥井雅章「吉野記」を中心とした学術交流である。
学内施設の見学では、日本大学の組織運営との異なり、また教員・学生の思考の異なりが見えてきた。例えば、学内施設には至るところに先住民の事績を意識させるようなモニュメントや、現地語の標識(英語を相対化させるような工夫がなされている)が見られる。大学や土地の歴史性を、学校全体で共有していく試みであるとの事らしい。日本ではそうした人種や土地性と大学が結びつく環境は少ないであろう。
また、ちょうどイスラエルの凄惨な攻撃が起こっている最中、戦死者の顔写真と、それに薔薇を手向ける空間があったことも印象的である。彼らは我々よりもはるかに、自分とは異なる社会で起こっている問題や変化に鋭敏である。それは、環境問題への取り組みが極めて意識的になされていることからも明らかである――例えばゴミの分別に多くのエネルギーを割いているし、些細な気づきだが、カフェのマドラーにプラスチックでも木材でもなく、パスタを用いていたのが象徴的であった――。
さて、学術交流では、私も発表させていただきながら、日本文学を研究することについて考えることになった。『吉野記』は近世の紀行文学だが、私はややさかのぼって、平安から鎌倉期の旅の文学を扱い、旅において鳥がいかに扱われるか、さらに今回のテーマに関わる形で、吉野という空間に鳥がどのように表れるのかを報告した。質疑では、『伊勢物語』に登場する都鳥の問題に触れた指摘など海彼の研究の質の高さをうかがわせるもの、動植物の擬人化の問題といった文学の本質に関する指摘など研究の拡がりを志向する姿勢がうかがえるものもあり、刺激的であった。
ディスカッションの席上ではなく懇談の場での発言だったと思うが、私も関心を持っている環境文学(ecocriticism)をめぐる研究状況をうかがえたのは僥倖であった。日本でも近年、近現代文学を中心に環境文学はよく手法として取り入れられているが、現在は「greenstudies」という枠組みも提唱されつつ、やや視点を異にしながら研究が進展しているようである。理論の流入は書物を通して数年遅れで日本にやってくることが多いが、直接先進の研究が摂取できるのは、直接的な学術交流の賜物である。
また、日本研究の視点で言えば、カナダの研究者は日本古典文学を新たな見方で見る視点を提供しつつも、日本側の研究の発信を待ち望んでもいるという。理論を用いての日本古典文学の研究が、恣意的になっていないか常に不安を抱えているからとのことである。これはひとえに、我々古典文学研究側の発信力の乏しさ、あるいは海彼の問題意識を受け止める意識の欠如ゆえであろう。世界的な取り組みの中で、日本の古典文学研究がどのように役割を持てるか、改めてその問い自体の意義を感じるとともに、やるべき課題の多さを実感した次第である。