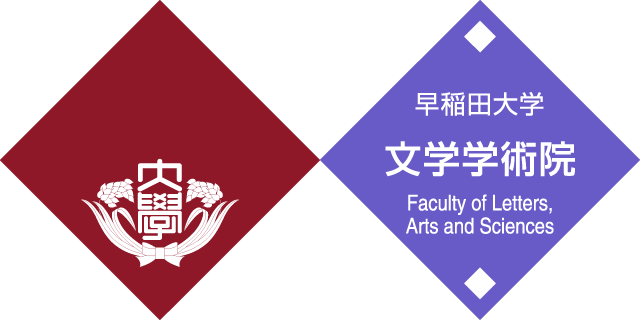- 学生報告書
- 榎戸渉吾 文学研究科 日本語日本文学コース
榎戸渉吾 文学研究科 日本語日本文学コース
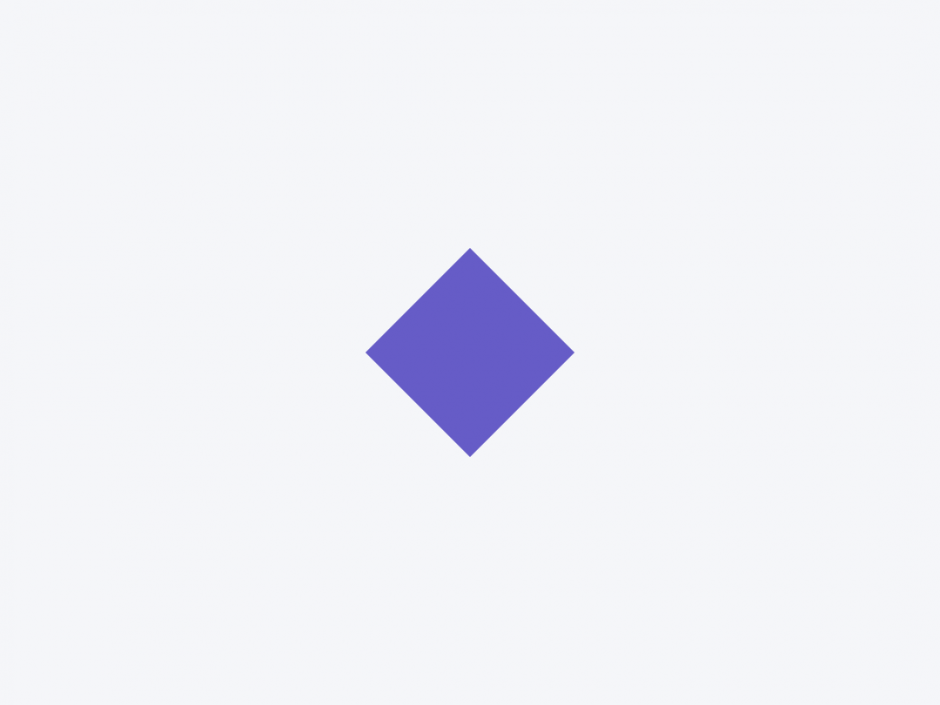
- Posted
- Thu, 01 Jun 2023
UCLAシンポジウム参加報告
文学研究科日本語日本文学コース博士後期課程4年 榎戸渉吾
この度、2023年4月28日から30日にかけて、UCLAにて行われた国際シンポジウムに参加した。シンポジウムの表題は“Kyarachters: On the Other Side of Narrative”であった。日本の様々な文化現象を、「キャラクター」をキーワードにして分析してみるという趣旨である。発表内容は多岐にわたり、文学や語学だけでなくサブカルチャーを扱ったものなど、古典文学を専門とする私にとって意外な題材を扱った研究が多くあった。「キャラクター」の定義は発表者によって様々であり、多様な視点を学ぶことができたとともに、アメリカの日本研究の方法・水準を知ることができた。
プログラムの内容で特に印象深かったのは、NHKで大河ドラマ制作に関わっていたお二方による、大河ドラマにおける徳川家康のキャラクター造形についての講演である。ドラマ作りの場面では、論文を書くこととは異なり、歴史的な正確さというよりはわかりやすさや視聴者ウケの良さといった点に気を使わなければならない場面も多いのだろうと想像するが、ドラマとしての面白さを保障するために、きわめて細かい事柄にまで歴史的な正しさを求め、その上で演出を行っているということに関心を持った。
私は、常日頃から研究をどうしたら研究者以外の方々に興味を持ってもらえるか、研究成果をどうしたら矮小化することなく、しかしわかりやすく伝えることができるのか、という点を模索しているが、ドラマ制作の最前線に立っている方が、歴史研究の成果を十分に受け止めつつ、そのうえでフィクションとしての面白さを追究しているということに、大きな感銘を受けた。
さて、最後にプログラム外のことについても少々述べておきたい。あちらでの滞在は、UCLAのキャンパス内にあるホテルであった。大学院生は、より密な交流を目的として原則別の大学の大学院生と相部屋になる。プログラムは朝から晩まで非常に充実したものであり、さらに、私は時差ボケがひどかったために、帰って寝るだけとなってしまいルームメイトとあまり深く交流できなかった。心残りである。
海外で行われる国際シンポジウムでは、日本にとどまっていては経験できないことが多くある。講演や研究発表から学ぶことも多いが、こういった時代・分野横断的なシンポジウムでは、日本の日本文学研究の場面で主流であろう時代別の学会に出ているだけでは絶対に知り合えなかった方と話すチャンスが多くある。毎年行われている柳井イニシアティブによるシンポジウムでは、英語の能力は全く問われず、また、金銭的な負担も極めて少ない。本研究科の大学院生、特に将来研究者になろうと思っている学生の積極的な参加を勧める。