- その他
- 古屋憲章(日研修士6期生)『今に続く始まりの場所』
古屋憲章(日研修士6期生)『今に続く始まりの場所』
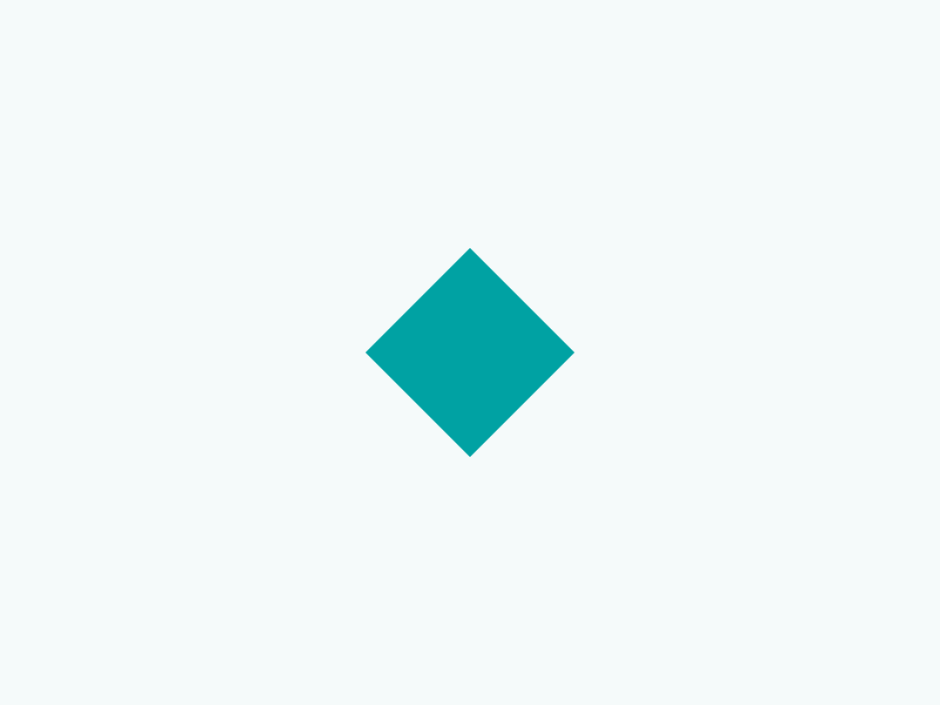
- Posted
- Fri, 01 Apr 2011
現職:早稲田大学日本語教育研究センター インストラクター(任期付)
僕は、2003年秋学期に日研に入学した。別にそれほど積極的な理由があったわけではない。当時勤めていた日本語学校を辞める理由が欲しかった。そこで、「大学院に行きます」と口走ってしまったというだけの話だ。3月に日本語学校を辞めた。そのとき、すぐ受験できるのは、日研だけだった。で、適当なテーマをでっち上げ、研究計画書を書き、受験した。なぜか受かった。
全く予備知識なく入学したわりに、日研はすごく面白かった。いろいろな先生がそれぞれの観点から様々な理論や実践を展開していた。僕はそのときはじめて、日本語教育という営みが多様で、豊かで、奥深い営みであることを知った。そうして、日本語教師をずっとやっていこうと決めた。フラフラしていた僕が、自分の人生の方向性を決めたのは、このときだ。が、肝心の研究のほうはさっぱりだった。修論のテーマはなかなか定まらず、データ収集は遅れに遅れた。何とか修了したものの、満足というにはほど遠かった。
僕が研究らしき活動を行うようになったのは、日研修了後だ。活動型クラスを担当したことが、その直接的なきっかけになった。活動型クラスで日本語によるやり取りを重ねる過程で学生たちが変化していく様子を見た。その変化を記述してみたいと思った。が、どうやって記述すればいいかわからなかった。そこで、日研を修了した仲間たちと記述の方法を探究した。そして、少しずつ書き始めた。それが、今に続く僕の研究の出発点となった。僕にとっての日研は、今もまだ続いている。
