- Featured Article
オープンラボ2025開催のお知らせ
所沢キャンパスで1日間の研究体験
Mon 12 May 25
所沢キャンパスで1日間の研究体験
Mon 12 May 25
2025年度から、人間総合研究センター事業の一環として、高校生の方向け来場型イベント「オープンラボ」を実施いたします。各分野の先生方による1日間の研究体験ができます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
概要
日程:2025年7月28日~8月27日の1日間(研究テーマによって実施日が異なります)
場所:早稲田大学所沢キャンパス アクセス
対象:高校1年生~3年生
参加費:無料
※当日の集合時間・集合場所は事前登録者に個別にご連絡いたします。
申込方法
➡8/4(月)すべてのプラグラムが定員に達したため募集を締め切らせていただきました。スマートフォンの方はQRコードから
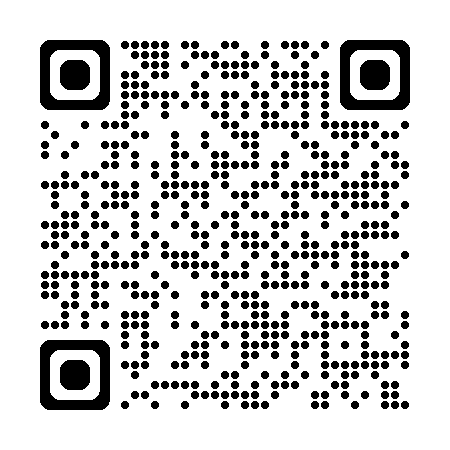
企画一覧
環境
- 7月31日(木)
-
-
森林生態系をはかる!:身近な里山を解析入門
担当教員:平塚 基志教授
※7/15(火)定員に達したため募集を締め切りました本プログラムでは、森林生態系が持つ生態系サービスの評価手法を学ぶ。特に、CO₂吸収量の定量化や生物多様性の評価について理解を深める。所沢キャンパスのコナラ二次林を対象に、レーザー機器を用いた毎木調査や植物の同定を行い、フィールドでのデータ収集方法を体験する。その後、得られたデータを解析し、CO₂吸収量を算出。さらに、森林の機能について代表的な指標を用いて観察し、環境科学的な視点を養う。
集合時間9:15 実施時間9:30~16:00(12:00-13:00昼休憩)
野外実施するため、保険に加入していただきます。自己負担は発生しません。
<ラボからのお知らせ>
森林調査及び登山のできる服装でお越しください。
・長袖シャツ、長ズボン←黒い服装は避けること(ハチ対策)、半袖は避けること(→蚊が出ます)
・登山ができる丈夫な靴(スニーカーで可)←底の薄いクツは避けた方が無難
・帽子←黒い帽子は避けること(ハチ対策)
雨天の場合、研究室の雨合羽を貸し出します。(自前で用意しても可)
筆記用具等はザック(リュック)に入れて参加ください。←手提げカバンは不可です。
-
- 8月1日(金)
-
-
ジオな世界:大地の科学入門 ミクロの世界からなにがわかる!?編
担当教員:山田 和芳教授
※7/25(金)定員に達したため募集を締め切りました古環境学的手法を用いて、大地や水域の環境履歴を復元する方法を学ぶ実習である。
とくに微古生物学の一分野として、所沢キャンパスの三ヶ島湿地にてピートサンプラーを用いた堆積物の採取を行い、円柱状試料を得る。その後、地層の観察やサブサンプリングを実施し、顕微鏡を使って花粉、珪藻、植物珪酸体などの微化石を観察・同定する。これにより、湿地の堆積環境とその変遷について理解を深め、地球科学の視点から環境変化を捉える力を養う。集合時間10:00 実施時間10:00~16:00 (12:00-13:00昼休憩)
<ラボからのお知らせ>
フィールド調査がありますので、動きやすい服装、タオルは持ってくるとよいです。(長靴は貸与します)
水筒(ペットボトルも可)も推奨
-
生物
- 7月28日(月)
-
-
光る微生物から光るタンパク質を取り出す
担当教員:赤沼 哲史教授
※7/22(火)定員に達したため募集を締め切りました暗闇で光るクラゲのように、光るタンパク質をつくる能力を持つように改変された微生物がいます。この実習では、そんな“光る微生物“から、実際に“光るタンパク質“を自分の手で取り出し、光らせる体験ができます。微生物細胞を壊して中身を取り出し、アフィニティーカラムクロマトグラフィーと呼ばれる実験手法を利用して、光るタンパク質をキレイに集めてみましょう。未来のバイオ研究をのぞいてみたい人にぴったりの実験です!
集合10:30、実施時間10:30~15:30
<ラボからのお知らせ>
実験の記録用にノートと筆記用具があるといいでしょう。
写真が撮れるようにスマホあるいはデジカメなどもあるといいです。
実験中に汚れる可能性もゼロではないので、勝負服は避け、動きやすい服装、靴で参加してください。
-
- 8月1日(金)
-
-
老化の大敵である酸化ストレスとは何か:ポリフェノールの機能性と抗酸化力の測定
担当教員:千葉 卓哉教授
※7/16(水)定員に達したため募集を締め切りましたポリフェノールは自然界に 4000 種類以上存在すると示唆される機能性成分であり、抗酸化活性を有する。赤ワインに含まれるレスベラトロールが有名であるが、果汁100%のジュース類にも多く含まれている。本プログラムでは、老化の原因の一つとされる活性酸素種による酸化ストレスについて解説し、それらを無毒化する抗酸化物質について概説する。身近な抗酸化物質としてポリフェノール類の含有量を、各種のジュース類をもちいて測定し、どのような果物にポリフェノールが多く含まれるかを実験して考察する。
集合12:45、実施時間13:00~17:00
<ラボからのお知らせ>
筆記用具をご準備ください。
-
工学
- 8月18日(月)
-
-
デジタルファブ体験!センサーで運動計測デバイスを作ろう:簡易筋電計
※7/31(木)定員に達したため募集を締め切りました本プログラムは、電子回路・3D プリンター・身体運動を組み合わせた体験学習で、参加者は簡易筋電計を組み立て、3D プリンターで専用ケースを設計・製作する。完成した装置を使って筋電位を計測し、身体活動との関係を探究する。電子工作や 3Dモデリングの基礎を学び、実際の運動を通じて身体の仕組みへの理解を深められる。データ収集・分析により、科学的思考力や探究力を養う機会ともなる。医工学分野への関心を育むことも期待される。
受付開始時間9:30 集合時間9:50 実施時間10:00~17:00
<ラボからのお知らせ>
筋電計を貼り付け身体を軽く動かしていただきますので,肘関節や膝関節が出せるような服装,動きやすい服装・靴が望ましいです。
-
- 8月27日(水)
-
-
未来のアイケア:3Dプリントとメタバースキャンパス体験
担当教員:岡崎 善朗准教授、高橋 麻衣子講師(任期付)、巖淵 守教授
※8/4(月)定員に達したため募集を締め切りました本プログラムでは、高校生を対象に、生体計測とものづくりを体験し、医療福祉への応用を考えます。3Dプリンターで製作した機器をスマホに装着し、目を測定することでアイケアデバイス開発の一端に触れます 。また、スマホ内視鏡による体内観察の体験、途上国向け眼科支援機器の紹介、VRでメタバースキャンパスを巡りながら目の健康状態を可視化します 。障害支援ツールやインクルーシブな教育環境についても紹介し、多角的にテクノロジーの可能性を探ります。
集合時間10:00 実施時間10:00-15:30
<ラボからのお知らせ>
持ち物や服装等、特に指定はございません。
-
情報
- 8月25日(月)(※8月26日(火)は中止となります。)
-
-
AIは人間の感情を理解できるか?「人と技術の共生」を目指した人間の感性・感情への情報科学的アプローチ
担当教員:松居 辰則教授
※7/25(金)定員に達したため募集を締め切りました※応募者に8/21に所沢総合事務センターからアクセスのご案内メールを差し上げております。ご登録いただいたアドレスにメールが届いていない場合には、[email protected]までご連絡ください。
本プログラムでは、「人間と技術の共生」をテーマに、松居研究室が取り組む AI と人間の深いインタラクションに関する研究を紹介する。感情理解や感性の扱いを中心に、ロボットとの安心感ある対話、学習支援、脳波を用いた心的状態の推定、感情の数理モデル化、スキル分析、人工感性の構築、倫理観の獲得支援など多岐にわたる研究を、ポスター発表とデモンストレーションを通じて体験できる内容である。
集合時間13:00 実施時間13:00~16:00
<ラボからのお知らせ>
筆記用具をご準備ください。
-
- 7月30日(水)
-
-
プログラミングの力で身近な問題を解決しよう
担当教員:尾澤 重知教授
※7/25(金)定員に達したため募集を締め切りました本オープンラボでは、micro:bit を用いたワークショップ形式で、人間中心の発想に基づいた問題解決を体験する。高校の「情報」と異なり、大学では人の役に立つ視点や問題解決力が重視される。初心者はブロックプログラミングで音やセンサーの基礎を学び、防犯や聴力検査を目的とした装置を設計。経験者は加速度センサーや機械学習を通じて人間の行動を推測・改善する装置の設計に挑戦。道具の活用やプロトタイピングの思考を養う参加型学習である。
集合時間10:00 実施時間10:00-16:00(うち1時間お昼休憩)
<ラボからのお知らせ>
通信機能を有するスマートフォンを持っている人は、持参をいただくとスムーズに進められます。
PCもしくはタブレット端末を持っている人は、持参をいただくとご自身の端末で操作ができます。
PCについては貸し出しも行いますが、体験内容が限定される場合があります。
-
心理
- 7月28日(月)
-
-
「目から見た発達臨床心理学」:こころと行動のプロセスを追う
担当教員:大森 幹真准教授
※7/10(木)定員に達したため募集を締め切りました※応募者には7/10に心理プログラム担当者から当日のご案内等のメールを差し上げております。ご登録いただいたアドレスにメールが届いていない場合には、[email protected]までご連絡ください。
本プログラムは、参加者にいくつかの実験を体験していただき、その中で言語コミュニケーションや意思決定といった心理学的な反応を起こすまでのこころのプロセス
を、視線機能計測を用いて可視化する。そのうえで、行動が変わることで視線機能にどんな変化が起きるのか、または「得意」と「苦手」でどのような違いがあるのかを体験的に学習していただく。さらには、視線や行動での評価が発達障害児の評価と支援にどのように活用されているかを紹介し、発達臨床心理学や療育の世界の一端に触れていただくことを目的とする。集合時間10:00 実施時間10:30-15:30
<ラボからのお知らせ>
筆記用具をご準備ください。
-

