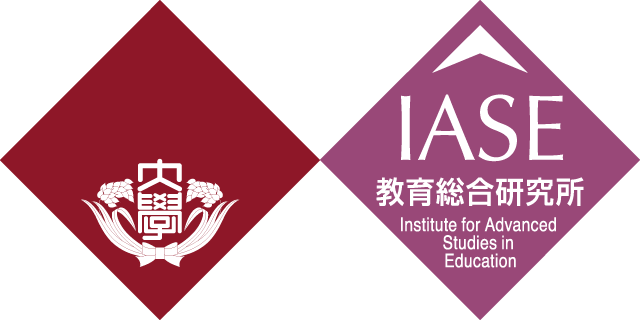- News
- 教育現場に届ける金融経済教育
教育現場に届ける金融経済教育

- Posted
- Fri, 28 Mar 2025
早稲田大学教育総合研究所とみずほ証券との産学連携で取り組む
教育現場に届ける金融経済教育
金融経済教育を日本全体に行き届かせるため、教育総合研究所(藁谷研究室、熊谷研究室)ではみずほ証券とともに、金融について教育ができる教員養成支援の共同研究を行っています。
学校現場における金融経済教育は、誰が、どの教科・科目で、何を教えるかが既存の枠に収まらず、十分な教育を実施できていない状況です。新学習指導要領では「公共」、「家庭」等で、金融分野の取扱いが拡充されたものの、教えるための授業時間・教員・適切な教材がいずれも十分ではありません。特に教材に関して、学校教育、金融実務、さらにいかに自分ごととして生徒に学んでもらうか、多様な知見が必要とされるものの、これらを満たす教材は不足しています。
教育総合研究所とみずほ証券は、みずほ証券による実経済における金融と早稲田大学教育学研究科による学校現場での実践研究を通じ、金融経済、学校教育、金融実務を踏まえた教材の開発・改良と、教室での授業実践活動を行ってきました。

取り組み内容の工夫
学校現場の時間不足の対応も踏まえて、学校が取り扱いやすいテーマとあわせて学べる工夫を行ってきました。
- 18歳成人に備える消費者教育×金融経済教育
- 将来の自立のためにキャリア教育×金融経済教育
- 社会とつながる主権者教育×金融経済教育
- 地域を興す起業家教育×金融経済教育
- 国の事業に参画し、デジタル教材の開発。STEAM※ライブラリーの無償公開。
https://www.steam-library.go.jp/about
※科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、芸術・リベラルアーツ(Arts)、数学(Mathematics)の頭文字を組み合わせた造語。知る(探究)とつくる(創造)のサイクルを生み出す、分野横断的な学びです。
2024年度は、更に高崎健康福祉大学高崎高等学校(以下、健大高崎高校)や、佼成学園女子中学高等学校、日本女子大学附属中学校などで、金融経済教育の出張授業を実施しています。このうち、健大高崎高校で実施した授業の様子について、3月6日付日本経済新聞に掲載されました。
健大高崎高校で金融経済授業 みずほ証券と早稲田大学 – 日本経済新聞
今後も早稲田大学を起点とした教員のネットワークを拡大しつつ、教育の現場に根ざした研究・実践を進め、教材プラットフォームを活用した全国の学校、教員への支援拡大を行って参ります。

出張授業の様子 ©みずほ証券提供
藁谷友紀教授コメント
日本の教育現場では、金融教育、投資教育の遅れと重要性が指摘されてきています。私たちは2015年から、教職員の皆さんと連携して、企業や個人のお金の流れや投資行動を通じて、私たちの暮らしがどのように変わるのかを考えてきました。実践の場は「教室」です。その窓は小さく見えるかもしれませんが、子供たちにとっては、自分の足元や世界の大きな流れを観察する大きな窓となりつつあります。
これまで授業の中では「お金」についてあまり語られてきませんでした。学校現場では、金融の仕組みと役割について教えることが必要だとする強い声があります。また、文部科学省をはじめとする関係省庁や広範囲の関係者は学校現場で取り上げることの必要性が強く唱えられていますが、教えるべき内容や体系についての共通理解が必ずしも進んでいません。扱うべき科目や時間として、社会科、家庭科、総合的な学習の時間等が挙げられ、内容についてもキャリア教育、消費者教育等が含まれ、多様な有り様が議論されています。扱うべき領域は教科横断的であり、教えるべき内容の体系を示すことが求められています。
生徒を取り囲む環境は、成年年齢引き下げ(18歳成人)や少子高齢化等、急速に大きく変化しています。「お金」に関する知識や判断力の習得は、消費者教育、キャリア教育、主権者教育の観点からはもちろん、生徒たち自身の人生と彼らがこれからいかなる社会を作り上げるかを考える時、欠かすことができません。現場で「お金」について教えることができる教員を増やすことは喫緊の課題になっています。
我々は、「お金」について「教える人材の育成」支援に産官学連携で取組むため、教育支援に注力しているみずほ証券と共同で研究と実践を進めています。はじめに「教えるべきコンテンツ」について授業実践を通じた研究を開始しました。その議論を踏まえて全国のさまざまな地域の自治体、教育委員会、現場の教員の方々とのやり取りを通じて、継続的に教員をサポートできる体制が必要と痛感しています。
授業を実践しながら、社会と教育現場双方で求められるコンテンツに従った教材を作成し、改良を進めています。また、コンテンツ素材を取り出せるライブラリーや、授業の実践例を教員同士で紹介し意見を貸すことができる教員、支援者間双方向のネットワークを構築することを目指しています。また学校や地域との連携の強化に努めています。
共に研究・実践を進め、教育支援の仕組みづくりにご協力いただきたく、一層のご指導をお願いいたします。
早稲田大学 教育・総合科学技術院教授 藁谷 友紀