村上春樹文学とわたし
2023.11.30
- 楊炳菁
2023年も年末になってきましたが、「村上春樹文学に出会う」シリーズに、日本近現代文学を研究されている楊炳菁先生より、ご寄稿をいただきました。
文中の「村上春樹の小説に出てきた登場人物は文学世界における人々であると同時に、小説を読む『私』であり、現代社会に生きている個々の人間でもある」というご指摘をはじめ、多くの示唆に富む楊先生のエッセイを、どうぞお楽しみください。
監修:権慧(早稲田大学国際文学館)
村上春樹文学とわたし
楊 炳菁
村上春樹文学との出会いは1998年の時だった。修士一年生、しかも日本文学を専攻とするわたしは村上春樹の小説を読んだことはない、これを聞いたルームメートの張苓さんは目を丸くした。1998年と言えば、村上春樹の作品はまだ漓江出版社から出されていた時代で、外国文学出版の老舗である上海訳文出版社が版権を取得し、全国的に「村上春樹ブーム」を巻き起こす前夜と言っていい時期だった。
それはともかくとして、これから日本文学を研究しようとするわたしはルームメートの表情に刺激され、急遽図書館から『ノルウェイの森』の日本語版を借りて読み始めた。上下二冊の『ノルウェイの森』は二、三日で読み終わり、これは中学校時代、瓊瑤の「恋愛小説」を夜更かしで読んで以来最も早いスピードだった。一方、スピードとは別に、わたしは今でも『ノルウェイの森』を読んだ時の感覚をはっきりと覚えており、それを長い間不思議に思っていた。『ノルウェイの森』はワタナベという日本人の男性の物語だったのに、彼と全く違う環境の中で育ってきた中国人の女性のわたしには、なぜか自分のことが書かれているような気がしてならなかったのだ。これは今まで読んだ日本語の小説、いや中国語で書かれた作品の中にも感じられなかったもので、一体何故こういう感覚が生まれたのかについて解明したかった。
修士の三年間はあっという間に過ぎてしまい、村上春樹の小説を研究対象に修士論文を書こうとしたわたしは、結局芥川龍之介の「藪の中」論で修士号を取った。死後二十年経たないと研究対象にできないという日本語学科の暗黙のルールもあり、読書経験が浅いわたしには到底村上春樹論が書けないのではないかと自ら判断した。とはいえ、『ノルウェイの森』を読む時の不思議さがずっと心に留まり、その後出来る限り村上春樹の小説を読み漁ることになった。
こういう結果から言えば、当時村上春樹の小説の読書経験が皆無ということにびっくりしたルームメートの張苓さんはわたしと村上春樹文学の「仲人」と言えよう。彼女の「驚き」がなければ、わたしと村上春樹文学との出会いは遅くなり、あるいは永遠にすれ違っていたかもしれない。ちなみに、彼女は後日『1Q84』などの版権を他社と競い合った「新経典」という新鋭出版関連会社に就職し、村上春樹文学と深く関わる編集者になった。
2005年わたしは吉林大学文学院の博士コースに入った。入学してからまもなく博士論文のテーマについて聞かれたが、迷わずに村上春樹文学と答えた。時代の変化(当時、日本の大学ではすでに村上春樹文学で博士号を取った例があった)と「中文系」独特の自由な雰囲気のおかげで、わたしは四年後の2009年に「後現代語境中的村上春樹」(ポストモダンのコンテクストにおける村上春樹文学)で博士号を取った。今振り返ってみれば、入学直後の選択はいかにも生意気なもので、恥ずかしく感じるが、当時の勇気は心に深く刻まれ忘れられないものだ。
当然なことではあるが、小説を楽しく読むこととそれを対象に研究することとは全く次元が異なっている。いくら物語の世界に浸かっていても、作品を相対化しないと研究できないし、自分の結論に導いていくには適切な視角と厳密な論証が必要であるのは言うまでもない。したがって、「好き」という一言でスタートしたわたしの村上春樹研究は悪戦苦闘の連続で、博士論文を基に出版された著書『後現代語境中的村上春樹』(中央編訳出版社、2009)はいま読み返したら十分に論じられていなかったところも少なくなかった。だが、村上春樹研究の道を歩んだわたしは一度も後悔したことはなく、村上春樹文学を研究対象に選んだことはありがたく、至宝でも見つかったように感じられた。

2007年10月、和敬塾の西寮、以前村上さんが住んでいた部屋にて。
前述のように、村上春樹文学との出会いはルームメートの張苓さんのおかげだった。実は村上春樹文学の研究で、張さん以外にもたくさんの親友ができて、生涯に渡って感謝したい先生たちとも知己を得ることができた。指導教官の靳叢林先生をはじめ、自分の研究プロジェクトに誘い、常に励ましてくれた元東京大学の藤井省三先生や台湾淡江大学の曾秋桂先生、日本語の論文を毎回迅速にチェックし、助言もしてくれた元北京外国語大学の寺内伸介先生の諸先生方、年齢の差はあるが、友達扱いをしてくれた中国語圏における村上春樹文学の「三大訳者」の頼明珠先生、林少華先生、葉恵先生、それに張明敏さん、王嘉臨さん、謝恵貞さん、徐子怡さん、権慧さん、張瑶さんといった一緒に成長してきた若手研究者など、枚挙に遑がないが、村上春樹研究でこれほどたくさんの親切な方と巡り合えたことに感謝の気持ちでいっぱいだ。勿論、出会いの中には夫も含まれていて、村上春樹文学に関する討論や論文の作成などは現在私たちの生活の主な内容となっている。
人との出会いは貴いものである一方、村上春樹文学の研究において、わたしは常に新たな自分にぶつかり、周りの世界に対しても新たな認識が生まれた。評論家や研究者は作家より優れていないとうまく評論(研究)できない。こういう言い方はよく耳にするが、果たしてそうだったのか、首をかしげる時はむしろ多かった。ここで文学創作に携わる作家とそれを評価する評論家あるいは研究者との関係をめぐって論ずるつもりはないが、互いに誰が誰より優れているというような高下を競う関係ではないと断言できる。そして村上春樹文学に関して言えば、小説、ノンフィクション、エッセイ、紀行文集、多岐にわたる作品はむしろそれを解読する人々にいろいろ考えさせると言っていいだろう。例えば、『ノルウェイの森』を読んだ時に生まれたあの不思議さについて、わたしは以下のように考えている。
一般的には小説の読者が自分のことが書かれたように感じるのは、作中人物の誰か(多くの場合それは小説の主人公であるが)に自分の感情を投影し、同化するためと考えられる。そしてその作中の誰かの性質、特徴などは登場人物の名前に集約され、感情の投影、同化は登場人物の名前に抱いた特別な感情に転換すると言っていいだろう。ところが、村上春樹小説の場合はどうだろう。すでに前田愛が指摘したように、村上春樹の小説、特にデビュー作をはじめとする初期の作品には「登場人物の名前が、意識的に消される場合」[i]が多い。例えば『風の歌を聴け』には語り手の「僕」が登場し、その友人は仇名の「鼠」と名付けられた。そしてバーテンダーの「ジェイ」は本名でもないし、「僕」と付き合った女性はずっと「小指のない女の子」と呼ばれたままだったのである。つまり、「三四郎」や「時任謙作」のような登場人物(主人公)と異なって、村上春樹の小説には「無名」の登場人物が現れた。
前田愛は、村上春樹のデビュー作を例として、作中人物の「無名化」について、さらに次のように指摘した。
つまりわれわれは、名前を持った、名付けられた、そういう確固とした存在としてあるよりも、むしろ無名の存在、そしてまた他人と交換可能な存在に近づきつつあるということを、この主人公の名前の無化という現象が表しているわけです。[ii]
前田愛が指摘した文学世界に現れた主人公の名前の無化は、単なる小説創作の技巧にとどまらないと思われる。「主人公の名前の無化」は確かに文学世界で起きた現象だが、1970年代から始まった日本社会における単独性(singularity)の喪失を意味しているのではないだろうか。つまり、巨大なシステムの前で、人の単独性が吸収されており、そのため単独性を表す固有名が失われたということである。そして、単独性を失った現代人の様々な状態を、村上春樹文学は敏感に捉え、物語で表現したとわたしは思う。こういう意味から言えば、村上春樹の小説に出てきた登場人物は文学世界における人々であると同時に、小説を読む「私」であり、現代社会に生きている個々の人間でもあると言えよう。おそらく、村上春樹小説を読んで強くその主人公や登場人物に同感を覚える原因は、ここにあると思われる。勿論、村上春樹文学は単に現状の反映だけでなく、打開策を模索し、物語による救いの可能性も常に提供している。
わたしの考えは以上のようなものだが、この結論は村上春樹の小説を読むときに生まれた不思議な感覚を持ち続けながら、短編小説の「貧乏な叔母さんの話」や長編の『ねじまき鳥クロニクル』など、人の名前をキーワードにして人間の本質を追求する小説を解読することによってたどり着いたものである[iii]。これは言うまでもなく村上春樹文学に関する研究であるが、わたし自身およびまわりの世界に対する認識と重なってもいるだろう。
わたしと村上春樹文学との付き合いは今後も続いていくと思うが、最後に村上春樹文学とノーベル文学賞に関する考えを述べたい。日本近現代文学を専攻とするわたしはよく村上春樹のノーベル文学賞受賞の可能性について聞かれる。村上春樹文学の愛読者として、一日も早くノーベル文学賞を受賞してほしいと願っているが、研究者としてノーベル文学賞が取れる取れないを言えるのかどうか疑問だし、それ以前に、ノーベル文学賞は一体何を意味しているか考えてみたい。ノーベル文学賞は試合の優勝者に与えるものではない。つまり他の文学より優れているから賞を与えるというわけでもないし、受賞されていなくても優れた作品を創作した優秀な作家も多数存在している。
そもそもノーベル文学賞はある国や民族の文学と世界文学との関係を表すもので、言い換えれば、ノーベル文学賞を受賞することはその文学が世界文学として認められ、世界文学としての価値を有することを意味しているだろう。受賞が世界文学とつながるルートとなるが、世界文学として認められる唯一の道ではないということもすぐわかると思う。
こういう前提で考えれば、ノーベル文学賞を受賞するかどうかは村上春樹文学にとっておそらくそれほど緊迫したことではないだろう。なぜかというと、いま51種類の言語に翻訳され、58の国や地域で出版された村上春樹の作品は、日本国内だけでなく、世界とすでに結ばれており、各地の文学評論家や研究者に高く評価されているからである。常に先鋭性を追求する村上春樹文学は、たとえノーベル文学賞を受賞しなくても、優れた世界文学として存在し続けているのではないだろうか。
[i] 前田愛『文学テクスト入門(増補)』筑摩書房1993年P107
[ii] 前掲書P107-108
[iii] 具体的な論述は「“穷婶母”的生成与小说的二重结构——论村上春树的短篇小说《穷婶母的故事》」(<貧乏な叔母さん>の生成と小説の二重構造――村上春樹短編小説「貧乏な叔母さんの話」論、『福建江夏学院学報』2021.2)や「村上春樹文学における「紐帯」―「貧乏な叔母さんの話」と『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』における無名の人々―」(『村上春樹における紐帯』淡江大学出版中心2023.6)及び「村上春树文学中的名字认识」(村上春樹文学における名前、『日本学研究』第35輯 2023.10)などの拙論において展開されているので、参考していただければ幸いである。

プロフィール
1972年生まれ。2009年中国・吉林大学文学院で博士号取得、現在北京外国語大学日本語学院(北京日本学研究センター)、朝日大学経営学部准教授を務める。村上春樹文学を中心に、日本近現代文学研究を専門としている。著書に『後現代語境中的村上春樹』(中央編訳出版社、2009年)があり、村上春樹文学に関する研究論文を多数発表。
Related
-

“Letters from the Haruki Murakami Library”―アンドリー・セティアワン(Andry Setiawan)
2026.01.08
-

“Letters from the Haruki Murakami Library”―レベッカ・ブラウン(Rebecca Brown)
2025.12.02
-

“Letters from the Haruki Murakami Library”―カミラ・グルドーヴァ(Camilla Grudova)
2025.10.20
-
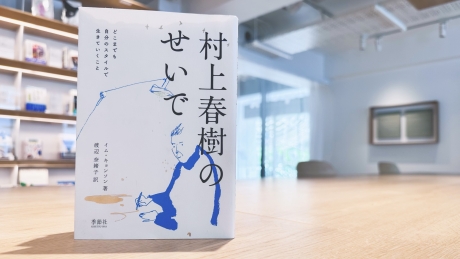
まるで空気のように
2023.07.26
- イム キョンソン
-
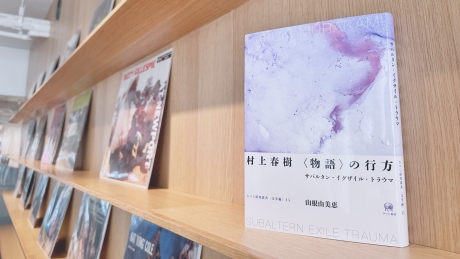
重なり合うドラマ/「森」の行方
2023.05.02
- 山根由美恵
-

村上春樹のマジックと私
2022.11.01
- アンナ・ツィマ
